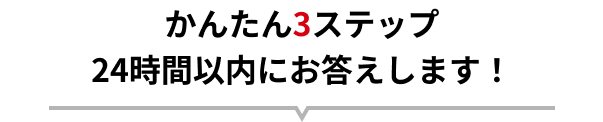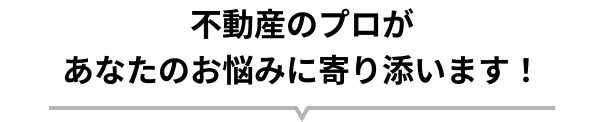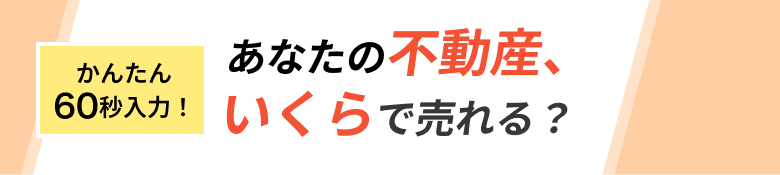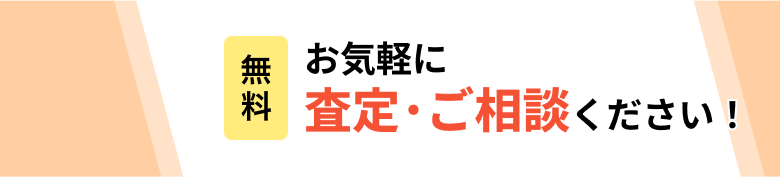老後の生活にどれほどの資金が必要か、不安に感じている方は多いのではないでしょうか。とくに持ち家がある家庭では、住宅ローンの有無や維持費の負担などによって、資金計画の立て方に迷いが生じやすくなります。この記事では、安心して老後を迎えるための備えや、自宅を活用するための考え方についてわかりやすく解説していきます。

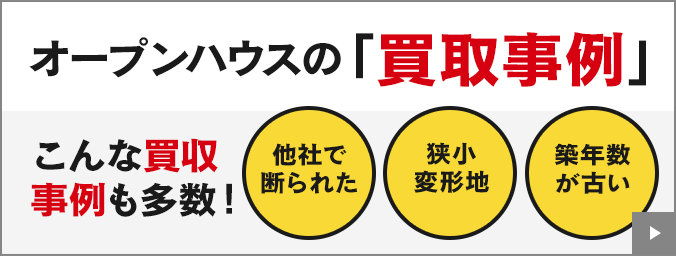
老後に必要な資金はいくらか
老後にどれほどの生活資金が必要になるかは、住まいや暮らし方によって異なります。ここでは、持ち家と賃貸のケースに分けて、老後資金の目安を確認していきましょう。
持ち家の場合
老後に持ち家で暮らす場合、家賃の支払いは不要になる一方で、維持費や固定資産税などの出費がかかります。とはいえ、賃貸に比べると住居費の負担が軽くなる傾向があり、生活全体の支出を抑えやすいのが特徴です。
総務省が公表している「家計調査年報(家計収支編)2020年(令和2年)」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の支出の月平均額は24万9,399円でした。この金額には、食費や光熱費、医療費など日々の生活に必要な項目が含まれています。
上記の支出の内訳から住居に掛かっている1万4,518円を除いた23万4,821円が、持ち家世帯の月の支出平均額になります。この額をもとに計算すると、年間では約280万円、20年間で約5,600万円が必要となります。
ただし、この23万4,821円はあくまで目安です。個人によって生活水準なども異なるため、自身で計算する場合には上記の項目を参考にしてどれくらいの支出があるかを計算するようにしてください。
実際の支出はリフォームや修繕費の有無、地域の物価差などによっても変動します。老後資金を見積もる際は、自分の生活スタイルに即した現実的な金額でシミュレーションすることが大切です。
賃貸の場合
老後に賃貸住宅で暮らす場合、家賃が継続的に発生するため、持ち家と比べて住居費の負担は大きくなります。退職後の収入が限られる中、毎月の家賃を確保し続けることは、資金計画における大きな課題といえるでしょう。
たとえば、月8万円の家賃で暮らす場合、年間では約96万円、20年間で約1,920万円が必要になります。これに日常の生活費や医療費などを加えると、持ち家世帯よりも老後に必要な資金総額はさらに大きくなります。
また、高齢になると賃貸契約の更新を断られるケースや、退去を求められるリスクもあるため、安定した住環境を維持するには不確定な要素が多くなりがちです。そのため、賃貸で暮らす場合には、持ち家以上に余裕を持った資金計画を立てておくことが望まれます。

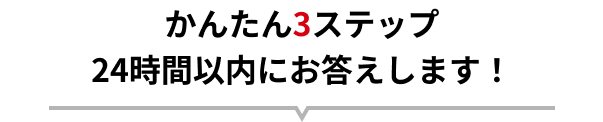
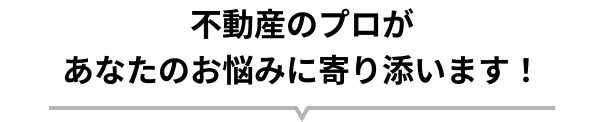
持ち家が老後資金に与える影響
持ち家があるかどうかは、老後の資金計画に大きく関わります。家賃が不要な分、住居費を抑えられる点では有利ですが、修繕費や管理費などのコストも発生します。ここでは、持ち家が老後資金に与える「プラス」と「マイナス」の影響を整理してみましょう。
持ち家が老後資金にプラスに働く点
老後に持ち家があることは、資金面で大きなメリットがあります。なかでも最大の利点は、家賃がかからないことです。住宅ローンを完済していれば、固定費の中でも重い住居費を抑えられます。
また、持ち家は住まいであると同時に資産でもあります。売却や、リースバック・リバースモーゲージといった制度を活用すれば、住みながら現金を得ることも可能です。必要に応じて資金化できる点は、老後の備えとして大きな強みです。
さらに、築年数が浅く状態の良い住宅なら、将来的な売却価格にも期待できます。住居費を抑えつつ資産価値も活用できることから、持ち家は老後資金において心強い存在といえるでしょう。
持ち家が老後資金にマイナスに働く点
持ち家には住居費の削減や資産価値といった利点がある一方で、老後資金の面ではマイナスに働く要素もあります。まず挙げられるのが、維持費の負担です。固定資産税や修繕費、住宅設備の交換費用などは、住宅ローンを完済していても毎年発生します。
また、持ち家を売却して資金化する場合も、想定通りの価格で売れるとは限らず、すぐに現金化できない可能性があります。リースバックやリバースモーゲージといった制度もありますが、利用には条件があり、すべての家庭に適しているとは限りません。
さらに、築年数が経った住宅は老朽化や耐震性の問題から資産価値が下がっていることもあります。売却時に解体費が必要になったり、買い手が見つからないといったリスクも想定されます。
このように、持ち家があるからといって安心とは限らず、老後の資金計画では維持費や資金化の難しさといったマイナス面にも目を向けることが重要です。

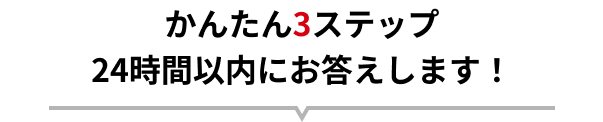
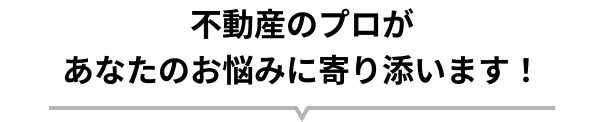
持ち家がある場合の老後生活費と必要資金
老後に必要な資金を考えるうえで、生活費と収入のバランスを把握することが重要です。とくに夫婦で持ち家に暮らす場合は、住居費を抑えられる一方、日々の支出に対して年金でどれだけ賄えるかを見極める必要があります。
たとえば、65歳で定年を迎えた夫婦が88歳まで暮らすと仮定し、毎月の生活費を23万4,821円(総務省「家計調査年報」による持ち家世帯の支出)とした場合、必要な生活費は以下のように試算されます。
23万4,821円 × 12カ月 × 23年(66歳〜88歳)= 約6,481万円
このように、老後のおよそ20年間で必要となる生活費は約6,500万円に達します。ここからは、生活費と年金の関係、必要な貯蓄額、世帯構成による違いについて整理していきます。
夫婦世帯の生活費と年金のバランス
持ち家のある夫婦世帯では家賃がかからない分、賃貸より住居費は抑えられますが、それでも老後の生活費は決して少なくありません。たとえば、65歳で定年を迎え、88歳までの23年間を毎月23万4,821円で暮らすと、必要な生活費はおよそ6,500万円にのぼります。
一方、年金だけでこの金額をまかなえるかというと、厳しい現実があります。国民年金の平均支給額は約5万6,000円で、老齢年金が14万6,000円でした。たとえば、国民年金のみを夫婦で受け取ったときの支給額は約13万円です。65歳以上の夫婦のみの無職世帯(持ち家)の支出の月平均額は約23万円だとすると、毎月10万分生活費が足りない計算になります。
夫が会社員で老齢年金、妻が専業主婦で国民年金の場合の支給額は約20万円です。そのため、この年金支給額であっても毎月3万円分生活費が足りません。このように、夫婦世帯でも年金だけで生活費をまかなうのは難しく、老後の安定した暮らしには、一定の貯蓄や別の補填手段が必要になります。
老後に必要な貯蓄額の目安
老後の生活費が約6,500万円にのぼるという試算がありますが、この全額を貯蓄で用意する必要があるわけではありません。年金などの収入でまかなえる分を差し引き、不足する金額をどのように準備するかが重要です。
老後資金は最低でも約6,481万円必要だと説明しました。しかし、この金額はあくまで目安の金額になります。一般的にはどれくらい老後の資金が不足するかを理解したうえで、自身の経済状況から老後の資金を計算する必要があります。
その不足額の目安として話題になったのが「老後2,000万円問題」です。。金融庁の金融審査会議「市場ワーキング・グループ」の報告書によると、老後の資金は2,000万円不足すると報告されています。
この報告では、定年退職後の夫婦のみ世帯は毎月5万5,000円の赤字になるとされ5万5,000円 × 12カ月 × 30年 = 1,980万円という試算結果が示されています。
このように、将来的に資金2,000万円程度に不足する可能性があるため、老後の資金を捻出することは非常に重要です。不足額は家庭ごとに異なりますが、公的年金以外の備えが必要である点はすべての家庭に共通しています。
単身世帯と夫婦世帯で異なる資金計画
老後に必要な資金は、世帯構成や生活スタイルによって大きく異なります。夫婦世帯は生活費の総額が多くなる一方で、光熱費や住居費などを分担できるため、1人あたりの負担は比較的抑えやすい傾向があります。
一方、単身世帯はすべての支出を1人でまかなう必要があり、費用が想像以上にかさむこともあります。
また、年金の受給額にも差があります。夫婦の場合は2人分の年金を合算できますが、単身では1人分のみ。とくに国民年金だけの場合、月6万円程度の支給にとどまるケースも多く、十分な貯蓄がなければ生活の維持が難しくなる可能性もあります。
このように、老後資金の必要額は世帯によって大きく変わるため、自身の立場に応じた計画を早めに立てておくことが大切です。

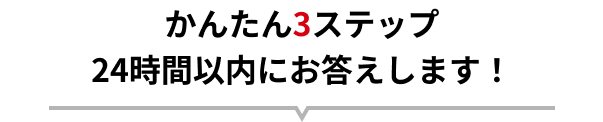
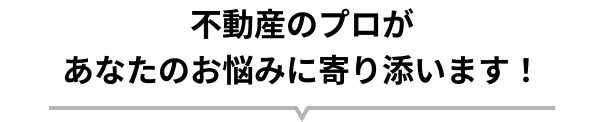
老後資金が不足する場合の対応策
年金だけでは生活費をまかなえず、十分な貯蓄も確保できていない場合でも、老後の生活を支える方法はあります。状況に応じた対策を知っておくことで、不足分を補う選択肢が広がります。
余裕のある老後を過ごすためには、老後資金の捻出方法について理解しておくことが重要です。老後の捻出方法を理解しておくことで、老後の資金が足りない場合に資金を準備することができるためです。
ここでは、生活費の見直しから持ち家を活用した資金化まで、老後資金を補うための現実的な対応策を紹介します。
家をすぐに売りたい場合については「家をすぐに売りたい!早期売却を実現するためにやるべきこと」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
住まいを見直して生活費を抑える
老後資金が不足しそうなとき、まず取り組みたいのが支出の見直しです。特に毎月発生する固定費を抑えられれば、継続的な節約効果が見込めます。
老後の資金を捻出するための方法として最も簡単なのが支出を見直す方法になります。支出を見直して赤字を無くすことで、家計収入だけで生活を送ることが可能です。なかでも、住まいや暮らし方の見直しは効果的です。たとえば都市部で車を所有している場合、車を手放すことによって、車の維持費を節約することができます。
また、広すぎる家や築年数の古い住宅に住み続けることで、光熱費や修繕費がかさむケースもあります。生活規模に合った住まいへ住み替えることで、負担の少ない生活に調整することも可能です。
上記のように食事や電気代ではなく、固定費を見直すのが有効な方法です。まずは家計の中でも大きな割合を占める住居費や自動車関連費などを確認し、節約できる余地がないか検討してみましょう。
住みながら自宅を資金化する
自宅を手放さずに老後資金を確保したい場合は、「住みながら資金化できる方法」を検討するとよいでしょう。最近では、こうしたニーズに応える制度も整ってきています。
代表的な方法が「リースバック」です。これは自宅を不動産会社に売却し、その後は賃貸として住み続ける仕組みです。売却によってまとまった資金を得られ、引っ越しも不要なため、生活環境を変えずに現金を確保できるのがメリットです。
もうひとつが「リバースモーゲージ」です。自宅を担保に金融機関から融資を受け、生存中は住み続け、死亡後に自宅を売却して返済に充てるという制度です。資金は年金のように分割して受け取れる形式が一般的です。
また、住まいの一部を賃貸に出して家賃収入を得る方法もあります。空き部屋を貸したり、2世帯住宅の一部を活用するなど、工夫次第で資金化が可能です。
このように、自宅に住み続けながら資金を得る選択肢は複数あります。不動産の条件や自身の生活設計に応じて、最適な方法を検討しましょう。
持ち家を売却して資金を確保する
老後の生活費が心もとない場合、まとまった資金を得る方法として「持ち家の売却」を検討するのもひとつの選択肢です。老後の生活費が足りない場合は、持ち家を買い取ってもらって資金調達をする方法もあります。住宅という資産を現金化することで、生活の安心につなげることができます。
この方法では、不動産の売却金が手に入るため、売却金を生活費に充てることが可能です。とくに、早期の現金化が必要な場合は、不動産会社による「買取」という方法が有効です。買取なら買い手を探す手間がかからず、比較的スムーズに資金を確保することができます。
ただし、不動産を売却してしまった場合は住む場所が必要になります。売却後はマンションや賃貸住宅など、生活スタイルに合った住まいに住み替えることも検討しましょう。持ち家を売却した資金を使用して、新しい住居に住み替える方法もおすすめです。
例えば、戸建住宅からマンションに住み替えるなどです。このように、持ち家がある場合は、持ち家を売却して老後の資金を捻出する方法も検討してみてください。「住まいの見直し」と「資金確保」を同時に実現できる方法として、不動産買取の活用は現実的かつ実行しやすい選択肢といえるでしょう。
家の売却や査定ついては「家を売るときの査定ガイド|相場・流れ・注意点までわかりやすく解説」や「家を売却するときの基礎知識!流れ・税金・不動産会社の選び方【完全ガイド】」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

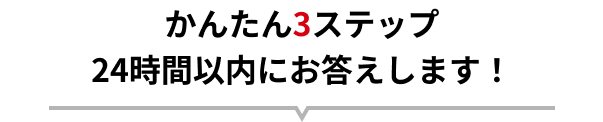
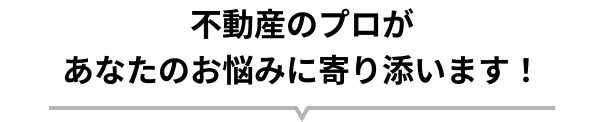
老後資金や持ち家に関するよくある質問
老後に向けた資金計画や、持ち家をどう活用すべきかについては、多くの方が共通する不安や疑問を抱えています。ここでは、実際によく寄せられる質問の紹介と解説をします。
持ち家があると老後費用はいくらかかる?
持ち家がある場合、家賃が不要なため、賃貸よりも老後の生活費は抑えやすい傾向にあります。ただし、支出がゼロになるわけではありません。固定資産税や修繕費、水回り・屋根のメンテナンスなど、住み続けるには定期的な出費が必要です。
総務省「家計調査」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の月平均支出は約24万9,000円。そのうち住居費は約1万4,000円とされており、持ち家世帯の月間支出は実質約23万4,000円と見積もられます。
持ち家のある70代の平均貯蓄額はいくら?
70代の持ち家世帯の平均貯蓄額は、およそ1,500万円といわれています。夫婦世帯ではこれに近いケースが多い一方で、単身世帯では1,000万円未満も珍しくありません。また、平均値と中央値には差があり、実際には貯蓄が少ない世帯も多く存在します。
老後の備えとしては、金額の多寡だけでなく、自分の生活スタイルに合った資金計画が重要です。
老後に余裕を持って暮らすにはいくら必要?
老後を安心して暮らすためには、日々の生活費に加えて、医療費やレジャー費などの「ゆとり費」も考慮する必要があります。総務省の家計調査によると、70代夫婦の平均的な月間支出はおよそ25万円前後で、年金などの収入だけでは不足する場合もあります。
さらに、突発的な出費や旅行・趣味などに備えるためには、生活費とは別に月数万円程度の余裕資金があると安心です。そのため、老後に余裕を持って暮らすには、月額30万円前後を目安に資金を見積もっておくとよいでしょう。
老後に必要な資金はどうやって計算すればいい?
老後に必要な資金を把握するには、まず家計の収入と支出を整理することが大切です。年金だけでなく、その他の収入も含めて家計収入を計算し、日常の支出や将来的な出費も見込んで家計支出を把握します。
そのうえで、キャッシュフロー表を作成し、長期間のシミュレーションを行うことで、老後に不足しそうな金額や貯蓄の目安が見えてきます。具体的な数字をもとに計画を立てておけば、安心して老後を迎えることができるでしょう。
老後資金の準備はいつから始めるのが理想?
老後資金の準備は、できるだけ早い段階から始めるのが理想です。収入が安定している現役世代のうちに少しずつ備えておくことで、将来の負担を大きく減らすことができます。
ライフステージの変化に合わせて見直しながら、無理のない範囲でコツコツと準備を進めていくことが、老後の不安を軽減する第一歩となります。

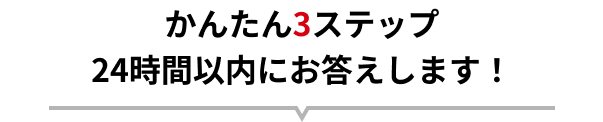
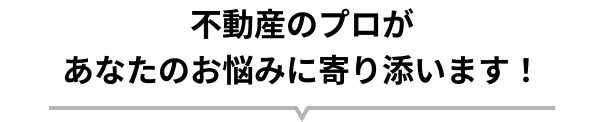
老後資金に不安がある方は、持ち家の買取も検討しよう
年金や貯蓄だけでは将来の生活に不安が残るという方は、持ち家を活用した資金確保の方法を考えてみるのも一つの手段です。特に、早めに現金を確保したい場合には、不動産会社による「買取」という選択肢があります。
買取であれば、買い手を探す手間がなく、スピーディーにまとまった資金を得ることが可能です。また、住み替えを前提とした売却であれば、老後の生活に適した住環境へ移るきっかけにもなります。
持ち家を資産として捉え、必要に応じて現金化するという発想は、老後資金の不安を減らす有効な選択肢の一つです。状況に応じて専門家に相談しながら、無理のない資金計画を立てていきましょう。