家を売却するとき、「どんな税金がかかるのか」「いくら支払うことになるのか」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。譲渡所得税や住民税といった基本的な税金のしくみに加え、「3,000万円特別控除」などの特例制度を知っておくことで、売却後の資金計画が立てやすくなります。この記事では、家を売却した際に関係する税金についてわかりやすく解説し、よくある疑問にもお答えします。税金の不安を解消し、安心して売却に進めるために、ぜひ参考にしてください。
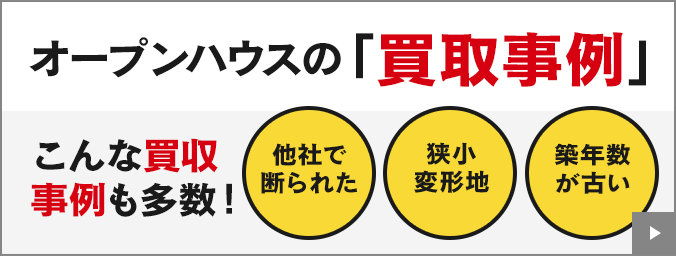
家の売却でかかる税金とは?

まずは家の売却に伴う税金を把握しましょう。家の売却とともに発生する税金は以下の5つです。
- 譲渡所得税(所得税・住民税)
- 固定資産税
- 印紙税
- 復興特別所得税
- 登録免許税
これらは「いつ・誰に・いくら払うのか」という仕組みがそれぞれ異なります。ここでそれぞれの内容を詳しく解説します。
①譲渡所得税(所得税・住民税)
譲渡所得税・住民税とは、不動産を売却して得た利益である「譲渡所得」にかかる所得税および住民税です。譲渡所得は他の所得と分離して課税される仕組みとなっており、税率は物件の所有期間によって異なります。
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):税率20.315%(内訳:所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):税率39.63%(内訳:所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)
算出された所得税は原則として翌年3月15日までに納付しなければなりません。住民税は翌年度に自治体から課税されます。
②固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日時点の不動産所有者に課される税金です。年の途中で家を売却した場合でも、1月1日時点の所有者である売主には、その年度分の固定資産税を全額納税しなければなりません。
とはいえ、引き渡し後の期間分まで売主が全額負担するのは不公平という考えから、実際は売主と買主で税額を按分するのが一般的です。
売買契約書には「固定資産税等精算条項」を設け、引き渡し日を基準に負担割合を明記します。具体的には、引き渡し日以降に対応する固定資産税の相当額を買主が負担し、決済時に物件代金と合わせて売主へ支払うケースが多く見られます。
固定資産税そのものは家の売却に直接伴う税金ではありませんが、売却年度の税負担調整が必要となる点を押さえておきましょう。
③印紙税
印紙税とは、不動産売買契約書などの課税文書を作成する際に収入印紙を貼付して納める税金です。
2025年現在は軽減税率が適用されており、税額は取引金額に応じて200円、500円、1,000円、5,000円、1万円、3万円、6万円の7段階です。取引金額が上がるたびに、段階的に印紙税額も増えていきます。
たとえば、家の売買価格が3,000万円の場合、本来なら印紙税は2万円ですが、軽減税率が適用され1万円となります。取引金額が5,000万円を超え1億円以下の場合は軽減税率適用で3万円、1億円を超え5億円以下の場合は6万円です。
現行の軽減措置は2027年3月31日までです。期限を過ぎると税率が本則に戻る点に注意しましょう。
売主と買主がそれぞれ原本を保管する場合、双方の契約書に収入印紙を貼る必要があります。貼り忘れや不足が後日判明すると、過怠税が課される恐れもあります。
④復興特別所得税
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源確保のために設けられた税金です。2013年から2037年までの各年分の所得税額に対して付加されます。その年の基準所得税額の2.1%相当額を、所得税とあわせて申告・納付する仕組みです。
物件の譲渡所得に対する所得税にも、復興特別所得税が適用されます。
たとえば、譲渡所得に対する所得税額が100万円の場合、復興特別所得税として課される金額は2万1千円です。譲渡所得税と合わせて102万1千円を納付することになります。
復興特別所得税は所得税に上乗せされる形で賦課されるため、納付時期も所得税と同じ翌年3月15日までです。不動産売却で譲渡所得税を申告する際には、自動的に復興特別所得税も計算されることを覚えておきましょう。
⑤登録免許税
登録免許税とは各種登記の際に発生する税金のことです。
家を売却する際は、売主から買主への所有権移転登記をしなければなりません。その際、「固定資産税評価額」という不動産の価格に所定の税率をかけて、登録免許税が課されます。負担するのは通常、登記申請人である買主側です。
不動産の売買による所有権移転登記の場合、税率は原則、固定資産税評価額の2.0%です。
2025年現在は税制優遇措置が適用されており、土地の売買による所有権移転登記は本則2.0%から1.5%に軽減されています。住宅用家屋の所有権移転登記についても一定の要件を満たせば、本則2.0%から0.3%に軽減されます。
ただし、軽減措置には期限がある点に注意しましょう。土地の売買による所有権移転登記の場合は2026年3月31日まで、住宅用家屋の所有権移転登記の場合は2027年3月31日までです。
なお、同じ土地でも、相続する時と売却する時とで別の税金が発生します。
家の売却時に活用できる特例制度

家の売却にかかる税金が「意外と高い......」と感じる方もいるかもしれません。しかし、実は税制上の特例制度がいくつか用意されており、適切に活用すれば税負担を減らせる可能性があります。
ここで、家の売却時に活用できる5つの特例制度について解説します。
3,000万円特別控除
3,000万円特別控除とは、家を売却して譲渡所得が発生しても、最大3,000万円までの譲渡所得を非課税にできる制度です。たとえば、売却して発生した譲渡所得が2,500万円の場合、全額を控除でき、所得税・住民税ともにかかりません。
譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、3,000万円までは課税されず、超えた部分についてのみ課税されます。主な適用条件は次の通りです。
- 居住用財産であること
- 住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までに売却すること※
- 家屋を取り壊し、売却までに他の用途に利用しないこと
※ 転居後に家を取り壊した場合、取り壊し後1年以内に譲渡する必要がある
3,000万円特別控除を適用するには確定申告が必要です。たとえ譲渡所得が3,000万円以下で納税が発生しない状況でも、確定申告で申告しないと控除は受けられない点に注意しましょう。
3,000万円特別控除の要件については、「土地のみ売却でも3,000万円特別控除は使える?特例適用の条件や必要書類とは」でも詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
家を売却する場合、物件の所有期間が10年を超える際に、譲渡所得にかかる税率を軽減する特例を受けられます。
通常、物件の所有期間が5年を超える長期譲渡所得の税率は、所得税15%・住民税5%です。しかし、特例を適用すると、譲渡益のうち6,000万円までの部分については、所得税が10%、住民税が4%に引き下げられます。
ただし、譲渡所得の金額のうち6,000万円を超える部分については通常の税率が適用される点に注意しましょう。
適用を受けるには、家が自分の居住用財産であり、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年以上である必要があります。
この特例は3,000万円特別控除と併用できますが、買換え特例との併用はできません。利用する方は確定申告を通して申請しましょう。
特定の居住用財産の買換え特例
マイホームを売却し新たな家に買い換える場合、発生した譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べできるのが、特定の居住用財産の買換え特例です。
この制度は、売却したマイホームの金額よりも、新しく購入する家の購入価格が高いときに使えます。売却金額が新居の購入価格を上回る場合は、超過した金額に課税されます。
買換え特例はあくまで課税の繰延べであり、免除ではありません。将来、新居を売却する際は、繰り延べられた譲渡所得も含めて課税されることになります。
買換え特例の主な適用要件は次の通りです。
- 元の不動産の売却価格よりも新しい不動産の購入価格が高いこと
- 元の不動産売却の前年・当年・翌年いずれかで買換えすること
- 売却の相手が親族ではないこと
- 売却する不動産は10年以上保有していること
- 売却の翌年に所得税の確定申告をすること
買換え特例は、3,000万円特別控除や、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例との併用はできません。
買換え特例については、「不動産の買い替え特例をどこよりもわかりやすく解説」でも解説しているので、ぜひご覧ください。
居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームを売却した際に、売却額が取得費などを下回って損失が生じることもあるでしょう。このとき、新たなマイホームに買い換えた場合は、売却時の損失を他の所得と相殺し、控除しきれない部分を翌年以降3年間にわたって繰り越して控除できる特例があります。
これが「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」です。主な要件は次の通りです。
- 売却期限が2025年12月31日までであること
- 売却資産が自身の居住用財産で所有期間が5年を超えていること
- 売却の前年から翌年末までの間に日本国内で新たな居住用住宅(床面積50㎡以上)を取得し、取得年の翌年末までに居住を開始すること
- 新居について償還期間10年以上の住宅ローン残高があること
適用には、確定申告で所定の明細書や住宅ローン残高証明書の提出が必要です。
居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームを売却し売却額が取得費を下回る損失が出た場合、新しい住宅に買換えなくても利用できる特例が「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」です。
一定の条件を満たせば、売却時の損失を他の所得と相殺し、控除しきれない部分を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。新たな住宅への買い換えは要件ではないため「売り切り」の場合でも利用可能です。
この制度は、住宅ローン残高がある状態でマイホームを売却し、その売却額がローン残高を下回っている、いわゆるオーバーローンのケースが対象です。控除できる損失の上限は、売却時点の住宅ローン残高から売却額を差し引いた金額までとされています。
主な適用要件は次の通りです。
- 譲渡資産が本人の居住用であること
- 売却時点で所有期間が5年を超えていること
- ローンの償還期間が売却前年末時点で10年以上あること
- 売却先が親族などの特別関係者でないこと
- 売却期限が2025年12月31日までであること
居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用にも、期限内の確定申告が必須です。
不動産売却に関連する税金の特別控除については、「国税庁の制度をもとに解説!相続した土地の売却にかかる税金と特別控除とは?」「不動産売却にかかる税金支払いを抑えられる特別控除について解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
家の売却にかかる税金の計算方法

家の売却時にかかる税金の種類はわかったものの、実際にどれくらいの税金がかかるのかよくわからないという方もいるでしょう。ここで、家の売却にかかる税金の計算方法を解説します。
なお、税金の計算は条件によって異なります。確定申告や具体的な納税額の判断については、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
譲渡所得税・住民税の計算方法
まずは譲渡所得=売却益の求め方と、それに対する税額の計算方法を確認しましょう。譲渡所得は次の式で計算します。
- 譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除(該当する場合)
取得費とは購入時の物件価格や購入手数料など、家を手に入れたときにかかったコストです。長く所有している間に建物の価値が下がっている場合は、その分を差し引いて計算します。
譲渡費用とは売却のためにかかった費用のことで、不動産仲介会社への仲介手数料や売買契約書の印紙代、測量費用などが該当します。これらを差し引いてプラスの利益が出れば、その利益部分に税金がかかる仕組みです。
このようにして譲渡所得が算出できたら、次にその額に対して税率をかけて税額を計算します。税率は、所有期間に応じて次のように異なります。
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):税率20.315%(内訳:所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):税率39.63%(内訳:所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)
譲渡所得税・住民税(復興特別所得税含む)の計算式は次の通りです。
- 譲渡所得税・住民税の税額 = 課税譲渡所得 × 所有期間に応じた税率(20.315%もしくは39.63%)
【ケース別】課税額のシミュレーション
実際に家を売却した場合の税金額をケースシミュレーションで確認しましょう。ここでは、よく利用される3,000万円特別控除を適用できるケースを例に、税金の計算手順を説明します。
<売却条件>
- 購入価格(取得費): 3,000万円(新築で購入)
- 売却価格: 5,000万円
- 売却時にかかった費用(仲介手数料などの譲渡費用): 80万円
- 所有期間: 15年(長期譲渡所得に該当)
- 適用する特例: 居住用財産の3,000万円特別控除
1.譲渡所得の計算
物件を長期間所有したため建物の価値が目減りしている場合、譲渡所得を算出する際に減価償却費も考慮しなければなりません。今回の場合、購入時の取得費3,000万円のうち、建物の減価償却分を差し引き、実質取得費を約1,660万円として考えます。
譲渡所得
= 5,000万円(売却価格)-1,660万円(取得費)-80万円(譲渡費用)
= 3,260万円
2.特別控除を適用して課税譲渡所得を計算
譲渡所得3,260万円に、マイホーム売却時の特例である3,000万円の特別控除を適用します。
課税譲渡所得
=3,260万円(譲渡所得)- 3,000万円(特別控除)
= 260万円
3.課税譲渡所得に税率を掛けて税額を計算
課税譲渡所得260万円に対して税率を掛けて税額を計算します。所有期間15年の長期譲渡所得なので、適用される税率は20.315%(所得税15%・住民税5%+復興特別所得税)です。
税額=260万円×20.315%=約52.8万円
算出された税額は約52.8万円となりました。
税金の計算は条件によって大きく異なります。確定申告や具体的な納税額の判断については、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
家の売却にかかる税金に関するよくある質問

最後に、家を売却する際にかかる税金に関連するよくある質問にお答えします。
①自宅を売却した場合、いくらまでなら非課税ですか?
自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」という制度を利用することで、最大3,000万円までの譲渡所得に税金がかからなくなります。この控除が適用されれば、所得税・住民税ともに非課税です。
仮に譲渡所得が3,000万円を超えた場合でも、超えた分だけが課税対象となり、3,000万円までは非課税となります。ただし、この特例を受けるには、売却した家が自分で住んでいた住宅であることや、過去2年以内に同じ特例を利用していないことなどの要件を満たす必要があります。
②家を売却したら、確定申告は必要ですか?
家を売却した場合、税金を適正に納めるため、基本的に確定申告が必要です。マイホームの譲渡で3,000万円控除を適用して税額がゼロになるケースであっても、特例適用を受けるためには確定申告をして控除額を申告する必要があります。
確定申告をしなければ特例が適用されず、本来非課税となるはずの譲渡益にも課税されてしまう恐れがあるため注意しましょう。譲渡損失が発生して損益通算や繰越控除の特例を受ける場合も、確定申告は必須です。
③家を売却したときの税金はいつ納付しますか?
家を売却して譲渡所得が出た場合、その税金(所得税・住民税)は原則として売却した翌年に納付します。売却した年の翌年に確定申告を行い、通常2月16日~3月15日の申告期間内に譲渡所得税を納めなければなりません。
住民税については確定申告後、売却の翌年の6月以降に自治体から通知があり、給与からの天引き(特別徴収)や納付書での支払い(普通徴収)によって納めることになります。
家の売却の注意点については「家の売却でやってはいけないこと・注意することをまとめて紹介」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
税金の不安をなくして、安心して売却へ進みましょう

家を売却する際には、譲渡所得税や住民税、印紙税、固定資産税など、さまざまな税金が関わってきます。「どれくらい税金がかかるのか」「非課税にできる方法はあるのか」といった疑問を感じる方も多いでしょう。
税金の仕組みは内容が複雑で、条件や対応方法もケースごとに異なります。思わぬトラブルや申告の漏れを防ぐためにも、売却前から専門家に相談し、準備を整えておくことが重要です。
安心して売却を進めるために、税に関する正しい知識を持つことが第一歩となります。不動産の売却を検討している方は、まずはオープンハウスの買取サービスをチェックしてみてください。






