相続が発生した場合、借地権も通常の不動産や預貯金等と同じように相続財産の対象になります。
今回は、借地権を相続する場合の注意点を紹介します。相続人が複数いるケースや相続放棄に関しても確認しましょう。
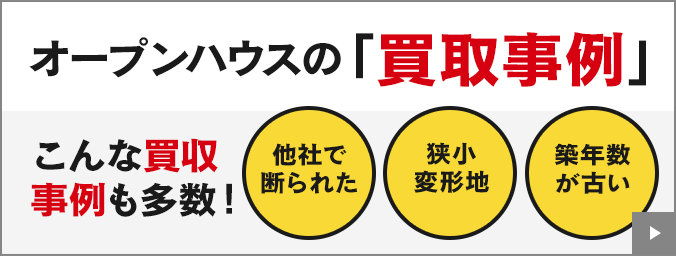
借地権の遺産分割における注意点
通常、相続が発生し相続人が複数いる場合は、財産を分割しなければなりません。借地権も分割の対象になります。
しかし、借地権の相続は、兄弟や孫など相続対象が複数いる場合は、注意が必要です。
兄弟や孫など複数人が借地権の相続を受けるときの主な注意点は3つです。
- 借地権相続後の費用・税負担
- 相続人全員の合意がなければ何もできない
- 相続人が亡くなるとさらに相続人が増える可能性がある
それぞれの注意点についてわかりやすく説明します。
借地権相続後の費用・税負担
借地権を相続すると、相続人には固定資産税などの費用負担が発生します。また、借地権を売却するためには地主の許可が必要で、場合によっては承諾料を支払う必要があります。
借地権を複数の相続人に相続した場合には、借地権は共有名義となり、上記した費用も共有名義人全員が負担することになります。
相続後、そういった費用負担や手間を省くために1人の名義を変更するためには、名義変更の費用や譲与税が発生するため注意しましょう。
そのため、できるだけ遺産分割協議書を作成する時点で、借地権を1人の人が相続するように作成することをおすすめします。
関連記事
「不動産を共有名義で相続したときの注意点」
相続人全員の合意がなければ何もできない
借地権は家を建てるために土地を借りる権利です。
借地権を相続した人が複数いれば、借地権のある敷地内の建物に住み続けたい人、借地権を売却したい人、建物を他人に貸して家賃収入を得たい人など、例え兄弟であっても考え方に違いが生じるかもしれません。
複数人に相続され、共有名義となった借地権は、売却などを行う際には共有名義人全員の合意が必要になります。当然、トラブルが起こりやすいため、注意が必要になります。
借地権を相続した人が亡くなるとさらに相続人が増える
借地権を相続した人(相続人)がいずれ亡くなると、借地権はその子供などに引き継がれることになります。もし相続によって、複数の人が相続人になることが代々繰り返されると、時間が経つにつれて権利を持つ人が増えてしまいます。
関わる人が増えれば合意形成が難しくなり、より借地権の売却などが困難になってしまいます。
借地権の相続放棄(返還)における注意点
借地権は、預貯金や普通の不動産のように相続放棄することが可能です。ここでは、借地権の相続放棄に関する次の2つの注意点を説明します。
- 相続放棄のために更地にする必要はない
- 相続放棄をした後、借地権がどうなるのか
ちなみに地上権も借地権の一種なので基本的なポイントは一緒です。
関連記事
「不動産の相続放棄の方法と必要書類をご紹介」
相続放棄のために更地にする必要はない
借地権を相続放棄するためには、更地にして返還する必要はありません。
また、相続放棄とは相続財産の一切を放棄するということを指します。つまり、更地にしてしまうことは、放棄する財産に手を加えてしまうことになり、相続を承認したとして相続放棄が認められないケースもあります。
相続放棄をした後、借地権がどうなるのか
借地権を相続放棄した場合、一般的な相続と同様に相続順位に応じて借地権が引き継がれます。
全員が相続放棄した場合や相続を受ける人がいない場合は、借地権は国に返還されることになります。これにより国が保有することになりますが、国が借地権を保有して地代を支払うことにメリットはないので、通常、弁護士等が相続財産管理人となり借地権売却が行われます。
このように、借地権を相続放棄する際には注意すべき点がいくつかあります。しかし、借地権を相続するか相続放棄するかを決めるポイントは、借地権相続で財産がプラスになるかどうかでしょう。相続した後に借地権を売却するケースも考えられるため、借地権がいくらで売却できるかを調べておくことも大切です。






