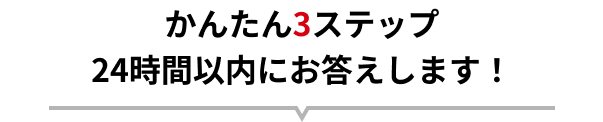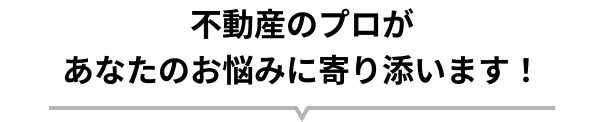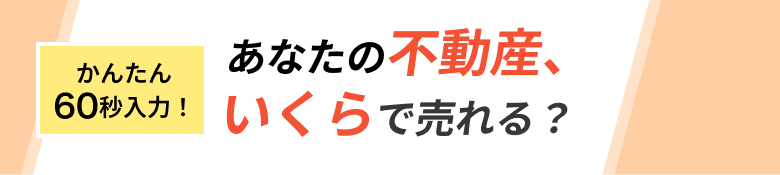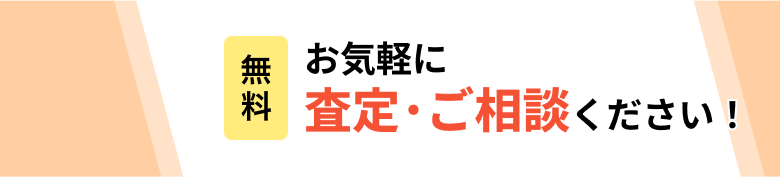親や親族から土地を相続したものの、どう扱うべきか迷う人は多いです。特に、売却するかどうかの判断には慎重になるものですが、相続した土地は3年以内に売却すると、税金の優遇措置が受けられる可能性が高くなります。本記事では、相続した土地を売却するときに知っておくべき税制優遇措置や注意点を詳しく解説します。知らないと損をするポイントを押さえて、最適なタイミングで売却を進めましょう。

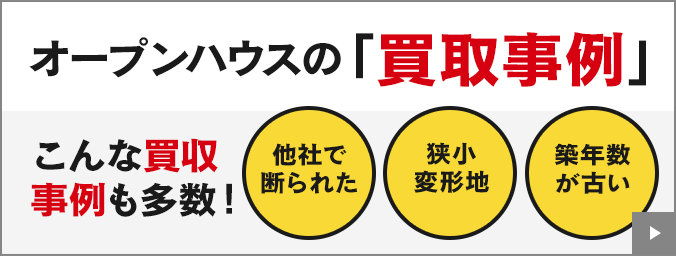
相続した土地を3年以内に売却するメリット
相続した土地を売却するかどうかは多くの人が悩むポイントですが、3年以内に売却すると税金の優遇措置を活用でき、結果的に手元に残る金額が増える可能性があります。
早めに手続きを進めることで、税負担を抑えながら売却できるのが大きな利点です。ここでは、主なメリットについて解説します。
取得費加算の特例や特別控除を受けられる
相続した土地を売却すると譲渡所得税などの税金がかかります。ただし、相続から3年以内に売却すれば、一定の条件を満たすことで税負担を大幅に軽減できる特例や控除が適用されます。
具体的には、次の特例が適用される可能性があります。
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
これらの特例を利用すれば、支払う税金を抑えられるため、売却を検討する際の重要なポイントです。
また、税負担が軽くなることで、手元に残る売却益が増える可能性があるため、適用条件を確認し、3年以内の売却を検討しましょう。
固定資産税や管理費などの維持コストを削減できる
不動産は持っているだけで税金がかかります。
具体的には、固定資産税や都市計画税といった税金です。固定資産税や都市計画税は毎年1月1日時点の所有者に各市町村の自治体が請求する地方税です。
それぞれの税額は以下の通りです。
- 固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%
- 都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%
土地の固定資産税評価額が1,000万円、建物の固定資産税評価額が1,500万円、総額2,500万円のケースで固定資産税と都市計画税を算出してみましょう。
- 固定資産税 ... 2,500万円 × 1.4% = 35万円
- 都市計画税 ... 2,500万円 × 0.3% = 7万5千円
合計で42万5千円の固定資産税が発生します。
相続して住まない家でも、これらの維持費が毎年発生します。住まないのであれば、早く売却することで税負担を少なくすることができます。
地価変動のリスクを回避しやすい
相続した土地は、早めに売却することで地価下落のリスクを回避しやすいです。不動産市場は常に変動しており、売却のタイミングを逃すと価格が下がる可能性があります。
特に、人口減少が進む地域では、時間が経つにつれ土地の需要が減少し、売却価格が下がるリスクが高いです。
さらに、買い手がなかなか見つからず、売却までに時間がかかるケースも考えられます。早めに売却を決断することで、より良い条件で取引できる可能性が高くなるでしょう。

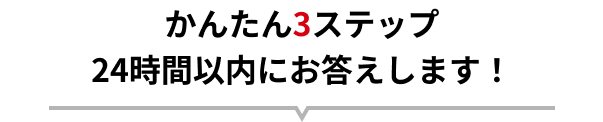
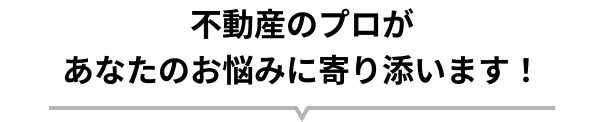
相続財産を3年以内に売却した場合の取得費の特例
相続した土地を売却する際、譲渡所得税がかかるため、税負担が気になる人は多いでしょう。税額は保有期間によって異なり、譲渡所得の20%、もしくは39%と比較的大きな税率で税額の計算をします。
しかし、相続してから3年10カ月以内に不動産を売却することで、取得費加算の特例を受けられることがあります。これにより、譲渡所得の計算上、取得費を増やすことができ、結果的に税負担を軽減が可能です。
適用条件
取得費加算の特例を受けるには下記の要件を満たさなければいけません。
- 相続で譲り受けた不動産を売却した
- 相続によって不動産を取得した人が相続税を支払った
- 相続が発生してから3年10カ月以内に売却した
つまり、3年以内に売却することで取得費加算の特例を受けることが可能です。これらの要件にあてはまれば、相続税の一定額を、相続した不動産を売却したときに発生する譲渡税を計算する際の所得費として加算することができます。つまり、譲渡した際の利益を少なく計算できるため、税金を抑えることができます。
手続き方法
取得費加算の特例を適用するためには、確定申告が必要です。まず、譲渡所得の計算を行い、支払った相続税のうち不動産に対応する部分を取得費に加算します。
計算方法は下記の通りです。
取得費の加算 = 支払った相続税 × 売却した不動産の相続税評価額 ÷ その者が取得した相続財産総額
例えば支払った相続税100万円、売却した不動産の相続税評価額3,000万円、相続財産総額5,000万円の取得費を算出しましょう。
500万円 × 3,000万円 ÷ 5,000万円 = 300万円
このようなケースであれば300万円を取得費として売却時に加算できます。
次に書類を揃えます。申告には確定申告者や相続税の申告書の控えなどが必要です。
最後に確定申告をします。確定申告書には、取得費加算の特例を適用する旨を記載し、税務署へ提出します。
申告が完了すれば、取得費加算の特例が適用され、税負担を抑えた状態で売却益を受け取ることが可能です。
必要書類
取得費加算の特例を適用するためには、次の書類を準備する必要があります。
| 相続税の申告書の写し | 相続税の計算に含まれていた不動産であることを証明するために必要です。 |
| 売買契約書の写し | 売却価格や売却日を明確にするための書類です。 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 売却した不動産の所有権が相続によって取得されたことを証明するために必要です。 |
| 確定申告書 | 取得費加算の特例を適用するためには、譲渡所得の確定申告が必要になります。 |
相続した土地を売却する際は、取得費加算の特例を活用することで、譲渡所得を抑え、税負担を軽減できます。適用条件や必要書類を事前に確認し、売却時に適用できるかどうかを検討することが重要です。

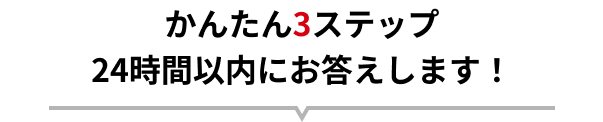
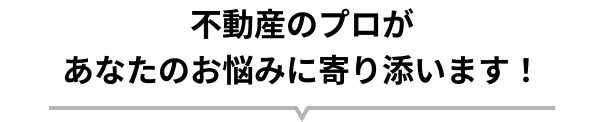
居住用財産(空き家)を3年以内に売却した場合の3000万の特別控除
相続不動産の売却における譲渡所得については、一定の要件を満たすことで特別控除を受けることができます。
これは、被相続人が居住していた住宅(空き家)を売却した場合に適用される制度で、税負担を大幅に軽減できる可能性があるため、相続後の売却を検討する際には重要な要素です。
適用条件
3,000万円の特別控除を適用するためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 被相続人が一人暮らしをしていた居住用財産であること
- 相続後、居住用として使用されていないこと
- 耐震基準を満たす建物、または更地で売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 相続開始から3年以内に売却すること
要件のひとつに、「相続発生時から3年を経過する日が属する年の12月31日までに相続人が売却した、もしくは取り壊しを行った後の土地を売却する場合は、特別控除の3,000万円を課税譲渡所得から差し引くことが可能」というのがあります。
他の要件を満たしているか確認する必要はありますが、一定期間内に売却することで税負担を小さくできます。
手続き方法
3,000万円の特別控除を適用する手続きには、確定申告が必要です。
まずは譲渡所得の計算を行い、特別控除を適用して減額を行うかを判断しましょう。
譲渡所得の計算式は次の通りです。
売買価額 - (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡所得
次に必要書類として、確定申告書や売買契約書などを準備します。
最後に確定申告を行って手続きを完了させます。
必要書類
3,000万円の特別控除を適用するためには、次の書類を準備する必要があります。
| 住民票の除票など | 被相続人が一人暮らしだったことを証明する書類です。 |
| 建物の耐震基準適合証明書または取壊し証明書 | 耐震基準を満たす、もしくは更地で売却したことを証明する書類です。 |
| 売買契約書の写し | 売却価格や売却日を明確にするための書類です。 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 売却した不動産の所有権が相続によって取得されたことを証明するために必要です |
| 確定申告書 | 特別控除を適用するためには、譲渡所得の確定申告が必要になります。 |
3,000万円の特別控除が適用できれば、税額は大きく変わります。適用条件を確認し、必要書類をしっかり準備しましょう。
相続不動産を売却したときの税金については「相続した不動産の売却にかかる税金は?控除や特例を解説」 にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

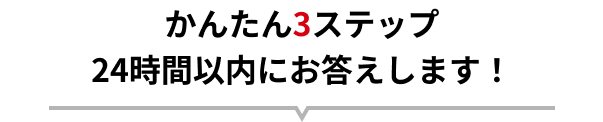
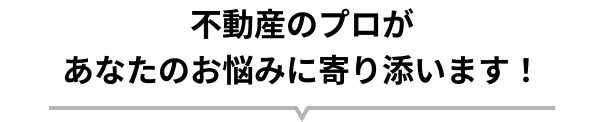
相続不動産にかかる税金や特別控除をシミュレーションで解説
3年以内に売却したらどのくらいの節税効果が見込めるのでしょうか。イメージしやすいよう、具体例でご紹介します。
500万円の土地を相続し、売却したときの税金は?
実家を取り壊した後に残った土地(評価額 500万円、保有期間 8年)を5年後に売却した場合と2年後(3年以内)に売却した場合で比較してみましょう。
(購入時の土地価格は不明のため、売却金額の5%の25万円、譲渡費用50万円とします。)
◇5年後に売却した場合
500万円 − 25万円 − 50万円 = 425万円(課税譲渡所得)
425万円 × 20% = 85万円
譲渡税85万円です。
◇2年後に(3年以内)売却した場合
500万円 − 25万円 − 50万円 − 3,000万円 = 0万円(課税譲渡所得)
譲渡税はかかりません。
1,000万円の土地を相続し、売却したときの税金は?
次に1,000万円の土地を相続した場合の譲渡税を計算してみましょう。
実家があって取り壊しを行った土地(評価額 1,000万円、保有期間 8年)を5年後に売却した場合と2年後(3年以内)に売却した場合で比較してみましょう。
(購入時の土地価格は不明のため、売却金額の5%の50万円、譲渡費用80万円とします。)
◇5年後に売却した場合
1,000万円 − 50万円 − 80万円 = 870万円(課税譲渡所得)
870万円 × 20% = 174万円
譲渡税は、174万円です。
◇2年後(3年以内)に売却した場合
1,000万円 − 50万円 − 80万円 − 3,000万円 = 0万円(課税譲渡所得)
となるので譲渡税はかかりません。
あえて2つの土地評価額で同様の計算をしましたが、ポイントは、譲渡税が3,000万円に近くなればなるほど特別控除の恩恵を受けやすくなるということです。
これは、相続した不動産に限った話ではありません。売却価格や課税譲渡所得が大きい土地においても、3年以内に売却した方が税制上において、非常に有利だということを理解しておきましょう。

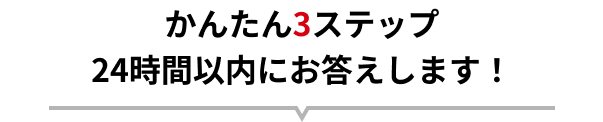
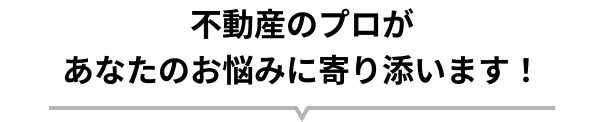
相続した土地を3年以内に売却する際の注意すべきポイント
相続した土地を3年以内に売却すれば、税制優遇を受けられる可能性があります。ただし、特例を適用するには一定の条件を満たす必要があります。
そのため、売却を検討する際には、手続きや税制の仕組みを理解し、適切なタイミングで進めることが重要です。
ここでは、適用条件を満たすために必要なポイントを解説します。
特例を利用するには確定申告が必要
相続した土地を売却し、取得費加算の特例や3,000万円の特別控除などの税制優遇を受けるには、確定申告が必須です。確定申告をしないと、控除や税負担軽減のメリットを受けられません。
確定申告は、売却した翌年の2月16日~3月15日の期間内に行います。期限を過ぎると特例を適用できなくなるため、事前に必要書類を準備し、早めに手続きを進めることが大切です。
さらに、申告書の記入ミスや必要書類の不足があると、適用が認められない場合があります。申告書には、特例を適用する旨の明記が必要です。また、相続税の申告書の控えや売買契約書、登記事項証明書などの書類を添付しなければなりません。
確定申告の詳しい手続きや必要書類については、国税庁の公式サイトで最新の情報を確認し、不備のないように準備を進めましょう。
適用できる特例を併用できるか確認する
相続した土地を売却する際、複数の特例があるものの、同時に適用できるとは限りません。どの特例を選ぶかによって、税負担が大きく変わるため、事前に確認することが重要です。
例えば、「取得費加算の特例」と「3,000万円特別控除」は、どちらか一方しか適用できません。したがって、どちらを利用するほうが税負担を抑えられるのかを事前に試算し、有利な方を選択する必要があります。
また、売却時に他の特例(居住用財産の軽減税率など)が適用できるケースもあるため、税理士や専門家に相談し、最適な特例を選択することが大切です。
売却時期を決める際は市場動向を考慮する
相続した土地の売却価格は、市場の動向によって大きく左右されるため、売却時期の見極めが重要です。市場が低迷している時期に売却すると、想定よりも安い価格で手放すことになりかねません。
売却時期を決める際は、次のポイントを意識するとよいでしょう。
- 不動産市場の相場(同じエリアの売却事例を調べ、相場価格が上昇しているタイミングを狙う)
- 需要の高い時期を考慮する(一般的に、春(1月~3月)と秋(9月~11月)は不動産売買が活発になる傾向がある)
- 景気や金利の動向(住宅ローン金利が低いときは買い手が増え、売却しやすくなる)
しかし、売却を急ぐあまり、市場が低迷している時期に売却すると、本来よりも低い価格で手放すリスクがあります。ただし、3年を過ぎると適用できる特例がなくなるため、市場の状況を見極めつつ、特例の期限内に売却できるよう計画を立てることが大切です。
相続した土地を売るタイミングについては「相続した土地を売るタイミングはいつがベスト?判断基準と注意点を徹底解説」や「相続した土地をすぐ売却するべきケースとは?メリット・手順・税金・特別控除を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

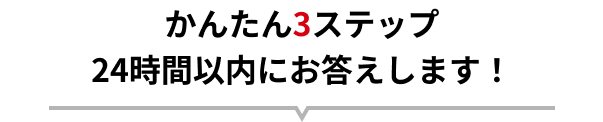
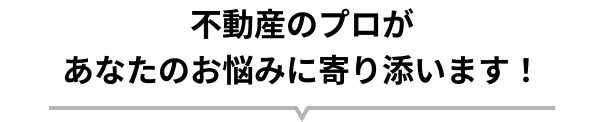
相続した土地を売却した際にかかる税金の種類とは?
相続した土地を売却する際には、いくつかの税金が発生するため、しっかりと把握しておきましょう。ここでは、主な税金について簡単に紹介します。
譲渡所得税・住民税
土地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その所得に対して譲渡所得税と住民税が課税されます。税額は保有期間によって異なり、譲渡所得の20%、もしくは39%と比較的大きな税率で税額の計算をします。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下) → 税率 39.63%(所得税30.63% + 住民税9%)
- 長期譲渡所得(所有期間5年超) → 税率 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)
相続した土地の場合、被相続人が取得していた期間も含めて所有期間をカウントするため、相続直後の売却でも長期譲渡所得として扱われるケースが多いです。
印紙税
売買契約書を作成する際には、契約金額に応じた印紙税が必要です。例えば、売却価格が1,000万円超~5,000万円以下の場合、印紙税は1万円(軽減税率適用時)となります。
消費税
土地の売却には消費税はかかりませんが、仲介手数料などの不動産会社への支払いには消費税がかかります。
土地を相続したときの税金については「土地の相続税はいくら?評価額の計算方法や控除を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

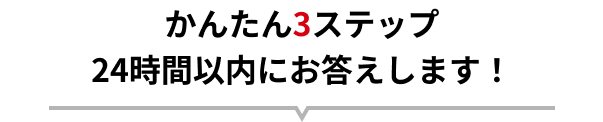
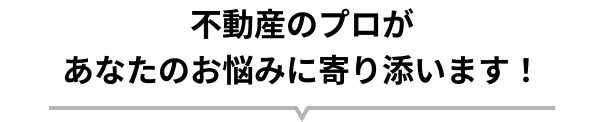
相続した土地を3年以内に売却する際のよくある質問
相続した土地を売却する際には、税制や手続きについて疑問を持つ人が多いです。ここでは、特に多く寄せられる質問について解説します。
相続と譲渡は何が違うの?
相続と譲渡は、財産の移転方法と税金の負担が異なります。
相続は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が引き継ぐことで、原則として相続時に税金は発生しません。ただし、一定の条件を満たすと相続税が課税されることがあります。
一方、譲渡は、相続した土地を売却して第三者に所有権を移すことを指し、売却益(譲渡所得)が発生すると譲渡所得税や住民税の負担が生じます。そのため、相続と譲渡では税金の取り扱いが異なる点に注意が必要です。
家を相続したときについては「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
3年以内に売却するのと、5年以内に売却するのはどっちがいいの?
3年以内に売却すると、「取得費加算の特例」が適用され、相続税の一部を取得費に加えることで譲渡所得税を軽減できます。税負担を抑えたい場合は、3年以内の売却が有利です。
一方、5年を超えても長期譲渡所得の税率(約20.315%)は変わらないため、市場価格の動向を見ながら最適なタイミングで売却するのも選択肢の一つです。
相続した土地を5年以内に売却したときについては「相続した土地を5年以内に売却するメリット・デメリットとは?税金・特例・注意点を徹底解説!」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

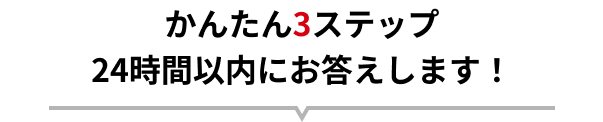
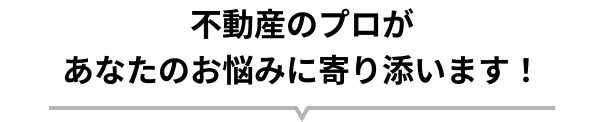
相続した土地は3年以内に売却するのがおすすめ!特別控除などを利用して賢く手放そう
相続した土地の売却を検討する際、3年以内に売却することで税制優遇を活用でき、負担を抑えることができます。特に、取得費加算の特例や3,000万円の特別控除が適用されるかどうかが大きなポイントです。
また、土地や空き家を所有しているだけで固定資産税や管理費がかかるため、使う予定のない不動産は早めに売却することで、余計なコストを削減できます。
売却を検討する際は、適用できる特例を確認し、不動産市場の動向を考慮しながら、最適なタイミングで進めることが重要です。税制を賢く活用し、負担を抑えながらスムーズに売却を進めましょう。