抵当権とは何か、ご存じでしょうか? 住宅ローンを組むときに登場する仕組みですが、具体的にどんなものなのか分かりにくいと感じる方も多いでしょう。この記事では、抵当権の基本的な仕組みから、設定・抹消の手続き、メリット・デメリットまで詳しく解説します。初心者の方にもわかりやすく、具体的にまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。
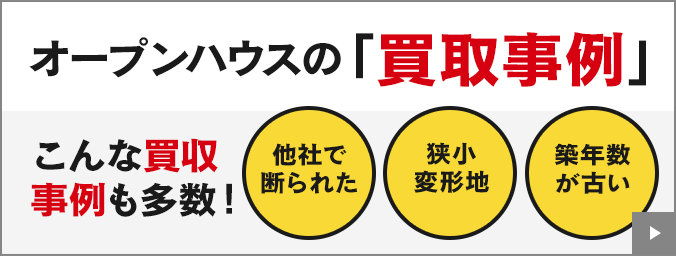
抵当権とは?仕組みをわかりやすく解説
抵当権とは、銀行などの金融機関が住宅ローンを貸し出す際に、不動産を担保として設定する権利のことです。
簡単にいうと、住宅ローンを返済できなくなった場合、担保としている不動産は手放さなければなりません。金融機関はその不動産を売却し、貸したお金を回収します。この仕組みによって、銀行はリスクを抑えながら融資を行えるため、私たちは 住宅ローンを利用しやすくなっています。
法律用語が多く、少し難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえながら丁寧に説明していくので、理解を深めていきましょう。
抵当権の概要
抵当権とは、住宅ローンを利用するときに設定される「担保権」の一種で、返済が滞った場合に銀行が不動産を売却して貸付金を回収できる仕組みです。
例えば、2,000万円の家を購入するために1,500万円の住宅ローンを借りた場合、銀行はその家を担保に1,500万円を貸します。もしローンの返済が滞った場合、銀行は抵当権を行使し、その不動産を競売にかけて売却し、貸したお金を回収します。
また、抵当権には「物上代位」という仕組みがあり、これは、火災などで不動産が損害を受け、保険金が支払われる場合、その保険金についても銀行が優先的に回収できる権利を指します。これにより、銀行は貸したお金が戻らなくなるリスクを減らせます。
一方で、ローンを完済すると抵当権が解除され、借りた人が正式な所有者として登記できます。
移転登記の内容については「所有権移転登記とは?意味・費用・手続きの流れをわかりやすく解説!」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
抵当権の設定は専門家が代行することが多い
抵当権の設定は、多くの場合、司法書士が代行します。 特に住宅ローンを組む際は、銀行が指定した司法書士が登記担当するケースがほとんどです。
抵当権を設定するには、「抵当権設定登記」という手続きを法務局で行う必要があります。これは、家や土地の権利関係を明確にするためのものです。
手続きは自分でも行えますが、専門的な知識が必要なため、多くの人が司法書士に依頼します。司法書士に依頼すれば、手続きのミスを防ぎ、スムーズに進められます。
ただし、その分の費用が発生するため。事前に確認が必要です。費用は地域や司法書士によって異なりますが、一般的に数万円から十数万円ほどが相場です。
抵当権と担保の違い
抵当権は、担保の一種であり、特に不動産を対象とする「物的担保」に分類されます。
「担保」とは、お金を借りたときに、返済できなくなった場合に備えて提供する保証のことです。担保には、大きく分けて以下の2種類があります。
| 人的担保 | 保証人や連帯保証人が返済を保証するもの。 |
| 物的担保 | 不動産や車などの財産を担保にするもの。 |
抵当権は、物的担保の一種です。不動産を担保として提供することで、銀行が安心してお金を貸せる仕組みになっています。つまり、「担保」という広い概念の中に「抵当権」が含まれているのです。
抵当権を設定する際の費用
抵当権を設定する際には登記費用が必要です。登録免許税や必要書類を集める経費のほか、前述の通り司法書士に依頼する場合では手数料もかかります。
こうした費用は決して安くありませんが、抵当権の設定は住宅ローンをスムーズに利用するために必要な手続きです。
ここでは抵当権を設定する際の費用について、詳しく解説します。
抵当権設定の登記費用とは?
抵当権の登記には、「登録免許税」と「司法書士の報酬」の2つの費用が発生します。
| 登録免許税 | 抵当権を設定するための税金 |
| 司法書士の報酬 | 司法書士への手数料 |
登録免許税とはその名の通り、抵当権を登録するために必要な税金のことです。借入金額に応じて計算され、通常は借入金額の0.4%が登録免許税としてかかります。
登記手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬が発生します。
自分で手続きをする場合、司法書士への報酬は不要です。ただし、登録免許税は必ず支払わなければなりません。
司法書士に依頼する場合の費用相場
司法書士に依頼する場合の費用は、一般的には数万円〜数十万円程度が相場です。ただし依頼する地域や事務所によって異なります。
| 基本手数料 | 5万円~7万円 |
| 登録免許税 | 借入金額の0.4% |
| その他の費用(書類作成費用や郵送費など) | 1万円程度 |
具体的な費用は司法書士事務所によって異なるため、依頼する前に見積もりを取ることをおすすめします。
抵当権と根抵当権の違い
抵当権は1回の借入に対して設定する担保、根抵当権は繰り返し借入ができる担保です。
どちらも不動産を担保とする権利ですが、その仕組みには大きな違いがあります。
抵当権は、一度設定するとローンを完済した時点で自動的に消滅します。新たに借り入れをする場合は、その都度新しい抵当権を設定する必要があります。
根抵当権は、あらかじめ設定した限度額の範囲内で、繰り返し借入や返済が可能です。完済後も新たな借入ができる仕組みになっています。
根抵当権の特徴と仕組み
根抵当権は、限度額の範囲内で繰り返し借入や返済ができる担保です。
企業の資金調達や事業資金の借入時に活用され、一度設定すれば、その限度額内で何度でも借り入れが可能です。
通常の抵当権は、一度設定すると特定のローンに紐づき、完済すれば自動的に消滅 します。一方、根抵当権は特定のローンに限定されず、継続的な取引の担保として利用されます。 そのため、追加の借入をする際に新たな抵当権を設定する必要がなく、資金調達がスムーズになります。
どんな場合に根抵当権を利用するのか?
根抵当権は、長期間にわたって資金の借入と返済を繰り返す場合に適しています。
例えば、企業が運転資金を確保するために、必要に応じて借入と返済を繰り返すケースがあります。また、不動産投資では、物件の購入や改修の際に、限度額の範囲内で資金を調達できます。
この仕組みにより、根抵当権は企業や投資家にとって便利な資金調達の方法となります。
抵当権のメリットとは?
抵当権には、借りる側(融資を受ける側)にもメリットがあります。抵当権を設定することで得られる、借りる側にとって大きなメリットは次の2つです。
- 住宅ローンの借入が可能になる
- 低金利で融資を受けられる
それぞれ具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
住宅ローンの借入が可能になる
抵当権を設定することで、住宅ローンを利用しやすくなります。
銀行は貸したお金を確実に回収するため、不動産を担保として確保します。抵当権があることで、「返済が滞っても不動産を売却して回収できる」と判断され、銀行は安心して融資を行えます。
その結果、個人でも大きな金額の住宅ローンを利用しやすくなり、マイホーム購入が可能です。
低金利で融資を受けられる
抵当権を設定すると、住宅ローンの金利が低く抑えられます。
銀行は貸したお金を確実に回収できるようにリスクを考慮し、金利を決定します。抵当権があれば銀行のリスクが減るため、無担保ローンと比べて低金利で融資を受けやすくなります。
これにより、毎月の返済負担を軽くすることができ、長期的に見ても住宅ローン返済総額を抑えられる点が大きな利点です。
抵当権のデメリットとは?
抵当権には、いくつかのデメリットがあります。
抵当権を設定すると、費用や手続きが必要になり、返済が滞った際のリスクも伴います。主なデメリットは以下の3つです。
- 設定にコストがかかる
- 返済できないと競売のリスク
- 売却前に抹消手続きが必要
これらのデメリットを事前に理解し、適切に対応できるようにしておきましょう。
設定にコストがかかる
抵当権を設定・抹消するには、それぞれ費用がかかります。
まず、抵当権を設定する際には登記費用が必要です。さらに、住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的に消えません。正式に抹消するには、「抵当権抹消登記」の手続きが必要で、これにも費用がかかります。
返済できないと競売のリスク
住宅ローンの返済ができなくなると、競売によって家が安く売却される可能性があります。
銀行は抵当権を行使し、担保となっている不動産を売却して貸したお金を回収します。このとき、通常の市場価格よりも安く売られる「競売」が行われることが多く、売却額がローン残高を下回ることもあります。
それでもローンが残れば、家を失った後も返済が続くことになります。
売却前に抹消手続きが必要
抵当権がついた不動産を売却するには、事前に抹消手続き済ませる必要があります。
抵当権を抹消するには、ローンの完済または売却代金による返済が求められます。 一括返済が必要になるケースもあるため、事前の準備が重要です。
抵当権設定登記の流れと手続き
抵当権設定登記の手続きの流れ
抵当権設定登記は、次の流れで進めます。
- 住宅ローン契約し、抵当権を設定する。
- 登記に必要な書類を用意する。
- 自分で手続きすることもできるが、多くの場合は司法書士に依頼する。
- 法務局へ登記を申請する。
- 登記が完了し、抵当権が正式に設定される。
抵当権の設定には10日から14日ほどかかるため、余裕を持って手続きを進めましょう。住宅ローンの実行は登記完了後となる点にも注意が必要です。
抵当権設定登記に必要な書類
抵当権設定登記を行う際には、次の書類が必要になります。
- 抵当権設定契約書(金融機関との契約書)
- 不動産所有者の実印
- 直近3か月以内に発行した印鑑証明
- 身分証(運転免許証など)
必要書類をそろえ、登記手続きを完了すると、正式に抵当権が設定されます。
抵当権抹消の流れと手続き
住宅ローンを完済すると、抵当権の抹消手続きが必要になります。抹消手続きが完了すると、正式に不動産の所有権が確定し、売却時もスムーズに進められます。
抵当権抹消の手続きの流れ
抵当権抹消の手続きは下記の流れで行われます。
- 住宅ローンを完済する。
- 銀行から「抵当権解除証書」などの必要書類を受け取る。
- 司法書士へ依頼する(任意)。
- 必要書類をそろえ、法務局で抵当権抹消登記を申請する。
- 抹消登記が完了する。
抵当権の抹消手続きの内容については「抵当権の抹消手続きを自分でするには?費用や必要書類まで解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
抵当権抹消に必要な書類
抵当権を抹消するには、次の書類が必要です。
| 登記原因証明情報(抵当権解除証書) | 金融機関が発行する証明書 |
| 登記済権利証または登記識別情報 | 不動産の所有者を証明する書類 |
| 抵当権者の委任状 | 金融機関が発行する委任状 |
| 抵当権抹消登記申請書 | 法務局に提出する申請書 |
| 委任状(司法書士を利用する場合) | 司法書士に依頼する際の委任状 |
必要書類の多くは、住宅ローンを借りた金融機関や保証会社などから発行されます。普段あまり目にしない書類が多いため、不明点があれば事前に確認しておくと安心です。これらの書類をそろえ、法務局で手続きを完了すると、抵当権が正式に抹消されます。
登記権利証の内容については「権利証(登記済証)とは?登記識別情報との違い・取り扱いの注意点を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
抹消手続きにかかる費用
抵当権抹消の手続きを行う際には、次のような費用が発生します。
| 登録免許税 | 一般的に1件につき1,000円 |
| 司法書士報酬(任意) | 司法書士に依頼する場合、1万円〜3万円程度 |
自分で手続きを行う場合、費用を抑えられますが、書類の準備や申請に手間がかかるため司法書士に依頼するケースも多くあります。
抵当権についてのよくある質問
抵当権付きの不動産は相続できる?
はい、抵当権が設定された不動産も相続ができます。ただし、住宅ローンが残っている場合、相続人が返済義務を引き継ぎます。
抵当権を抹消するには、住宅ローンを完済し、抹消登記を行う必要があります。
また、相続放棄すると、不動産を引き継がない選択も可能です。 ただし、その場合は 不動産だけでなく、他の財産も一切相続できなくなるため、慎重に判断することが大切です。
家の相続の内容については「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
抵当権者と抵当権設定者の違いとは?
抵当権者は、銀行や金融機関などの貸し手を指し、貸したお金を確実に回収するために不動産に抵当権を設定します。
一方、抵当権設定者は住宅ローンを借りる人で、自分の不動産を担保として提供する側です。
簡単にいうと、抵当権者は「お金を貸した人」、抵当権設定者は「お金を借りて不動産を担保にした人」になります。
債権額とは?抵当権との関係は?
債権額とは、銀行などの金融機関が貸し付けた金額を指します。抵当権は、その貸したお金を確実に回収するために設定される権利です。
例えば、住宅ローンで3,000万円を借りた場合、3,000万円が「債権額」です。銀行は、お金を担保するために、購入した住宅に抵当権を設定します。
つまり、債権額は貸し付けた金額であり、抵当権は回収を確保する仕組みです。
抵当権付き不動産を売ることはできる?
抵当権が設定されている不動産を売却することは可能ですが、売却前に抵当権を抹消する必要があります。
抵当権が残っていると、買い手が安心して購入できず、売却が難しくなります。そのため、売却前にローンを完済し、抵当権を抹消するのが一般的です。
また、売却金額がローン残高を下回る場合、不足分を自己資金で補わなければ、抵当権を抹消できません。 そのため、売却価格やローン残高を確認しながら慎重に進めることが大切です。
抵当権付き不動産の売却については「相続した不動産の売却にかかる税金は?控除や特例を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
抵当権の悩みは専門家に相談を!
本記事では、抵当権の仕組みや設定・抹消の手続き、メリット・デメリットについて詳しく解説しました。抵当権にはメリットとデメリットがあるため、仕組みを理解しておくことが大切です。
抵当権には、住宅ローンを借りやすくしたり、低金利で融資を受けられるといったメリットがある一方で、設定や抹消に費用がかかる、競売のリスクがあるなどのデメリットも存在します。
これらのデメリットを正しく理解していないと、思わぬトラブルや余計な費用が発生する可能性があります。 特に住宅ローンを利用する際は、契約内容や抵当権について理解しておくことが重要です。ただし、専門的な知識が求められるため、一人で判断するのが難しい場合もあります。
抵当権について不安や疑問がある場合は、不動産や法律の専門家に相談することをおすすめします。






