相続した土地を売却すると、確定申告が必要になるケースがあります。しかし、「必要かどうか分からない」「手続きが複雑そうで不安...」と悩む方も多いのではないでしょうか。適切な手続きを行わないと、後でペナルティが発生する可能性もあるため、事前の確認が大切です。本記事では、確定申告が必要かどうかの判断基準、税金の仕組み、申告の流れや注意点までを分かりやすく解説します。スムーズに手続きを進められるよう、具体的なステップも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
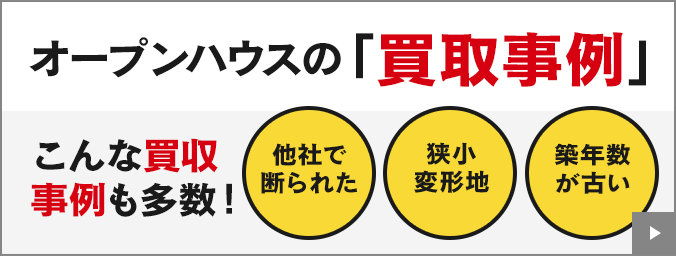
確定申告とは?
確定申告とは、所得税を計算し、納税額を確定させるための手続きです。相続した土地を売却すると「譲渡所得」が発生し、条件次第で確定申告が必要です。申告をしないと税務調査を受ける可能性があるため、確定申告が必要かどうかを早めに確認しましょう。
相続した土地の売却時に確定申告が必要な場合と不要な場合
相続した土地を売却した場合、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。確定申告を忘れると、税務署から指摘を受けたり、追加の税金が発生したりする可能性があるため、どちらに当てはまるのかを正しく判断することが大切です。
家を相続したときについては「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
売却によって利益が発生した場合は確定申告が必要
相続した土地を売却し、譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて計算されます。計算式は次のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特例控除
取得費には、もともとの購入費用や測量費などが含まれます。もし取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」が適用されます。また、仲介手数料や登記費用などの譲渡費用も控除可能です。
利益が出た場合は、確定申告して所得税・住民税を納める必要があります。早めに準備しましょう。
特例や控除を適用する場合は確定申告が必要
相続した土地の売却で特例や控除を適用するには、確定申告が必要です。適用できる主な制度には、次のようなものがあります。
①3,000万円の特別控除
被相続人が住んでいた土地を相続し、一定期間内に売却した場合、売却益から最大3,000万円を控除できます。適用条件として、「売却前に他人が住んでいないこと」「相続後3年以内に売却すること」などがあります。
②取得費加算の特例
相続税を納付した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。これにより、譲渡所得が減額され、税負担を軽減できます。特例を適用するには、相続開始から3年10か月以内に土地を売却する必要があります。
どちらも申告しなければ適用されないため、忘れずに確定申告しましょう。
売却しても利益が出なかった場合は確定申告が不要
相続した土地を売却しても、譲渡所得が発生しなかった場合は確定申告が不要です。売却価格が取得費や譲渡費用を下回った場合、所得が発生しないため、申告は不要です。
ただし、売却損を翌年以降に繰り越したい場合は、確定申告をすることで「譲渡損失の繰越控除」を適用できます。制度を利用すると、売却で出た損失を翌年以降の利益と相殺できるため、今後も不動産を売却する予定がある場合は検討するとよいでしょう。
所得の合計が20万以下の場合は確定申告が不要
不動産売却による譲渡所得と、それ以外の所得の合計が20万円以下であれば、確定申告を行わなくても問題ありません。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。
【確定申告が不要となる主な条件】
- 給与所得者である
- ひとつの会社からしか給与をもらっていない
- 勤務先で年末調整を受けている
条件を満たさない場合は確定申告が必要になるため、注意しましょう。
相続した不動産の売却については「相続した不動産の売却にかかる税金は?控除や特例を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
相続した土地の売却に関する確定申告の手順
相続した土地を売却した場合、確定申告が必要なケースでは正しい手順で申告を行うことが重要です。確定申告を適切に行わないと、税務署から指摘を受けたり、追加の税金が発生したりする可能性があるため、事前に手順を確認しておきましょう。
ここでは、確定申告までの具体的な手順を解説します。
Step 1. 売却益を計算し、課税対象かどうか確認する
まず、売却によって譲渡所得が発生するかを計算し、確定申告が必要かどうかを確認します。譲渡所得の計算式は次のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
売却価格は、不動産の売却額(実際に得た金額)です。
取得費には、相続した土地の元々の購入費用や測量費などが含まれます。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」を適用可能です。
譲渡費用には、次のようなものが含まれます。
- 仲介手数料
- 売買契約書の印紙税
- 登記費用
- 測量費用
- 建物解体費用(更地にして売却した場合)
譲渡所得がプラスなら確定申告が必要なため、事前にしっかり計算しましょう。
Step 2. 税金の特別控除や特例が適用できるか確認する
相続した土地を売却した場合には、一定の要件を満たせば税金が軽減される「特別控除」や「特例」が利用できることがあります。これらの控除や特例を活用することで、税負担が大きく軽減される可能性がありますので、適用条件を満たしているかどうかをあらかじめ確認しておきましょう
Step 3. 申告に必要な書類を準備する
確定申告を行うには、次の書類を準備する必要があります。
- 確定申告書B(所得税の申告に必要)
- 分離課税用の申告書(第三表)(不動産の譲渡所得がある場合)
- 譲渡所得の内訳書(売却価格や取得費、特例適用などを記入)
- 売買契約書の写し(売却の証明となる書類)
- 取得費を証明する書類(登記簿謄本、測量図、仲介手数料の領収書など)
- 特例を適用する場合の必要書類(相続税申告書、住民票除票など )
書類が不足すると、確定申告が受理されない、または追加提出を求められる可能性があるため、事前にしっかり準備しましょう。
Step 4. 確定申告書を作成し、提出する
必要な書類がそろったら、確定申告書を作成して提出しましょう。提出方法は次の3つがあります。
- 税務署へ持参する
- 郵送で提出(消印の日付が提出日となるため、期限内に発送)
- e-Tax(電子申告)を利用する
確定申告の提出期限は、翌年の3月15日までです。期限を過ぎるとペナルティが課されるため、余裕をもって準備しましょう。
確定申告をする際に利用できる税金の特別控除や特例
相続した土地を売却した場合、一定の条件を満たすと税金の負担を軽減できる特別控除や特例を利用することができます。
ここでは、土地の売却に関連する主な特別控除や特例を解説します。それぞれ適用条件や控除額が異なるため、自分に当てはまるものがあるかどうかをチェックしてみましょう。
被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除
相続した土地に建物があり、一定の条件を満たしている場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用できる可能性があります。控除を適用すると、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
適用条件は次のとおりです。
- 被相続人が生前、一人暮らしをしていた家である
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物である
- 相続後に耐震改修をする、または更地にして売却する
- 売却価格が1億円以下である
- 相続から3年以内に売却する
特例は、適用要件が細かく決まっているため、事前に税務署や専門家に相談し、条件を満たしているか確認しましょう。令和6年以降は、買主が耐震改修を行う場合でも適用されます。
マイホーム(居住用財産)を売却した場合の3,000万円特別控除の特例
相続した不動産を居住用として利用していた場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を利用できる可能性があります。特例を利用すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
主な適用条件は次のとおりです。
- 住まなくなってから3年以内である
- 取り壊している場合は、取り壊しから3年以内である
- 売却するまでに、その他(貸駐車場など)の用途で使用していない
- 売却先が「親子や夫婦などの特別な関係がある人」ではない
ほかにも細かな条件があるため、適用の可否については専門家に相談し、確認しましょう。
10年超所有していた居住用の不動産を売却した場合の軽減税率の特例
相続した土地を売却する際、被相続人が10年以上所有していた不動産である場合、「軽減税率の特例」を利用できる可能性があります。通常より低い税率が適用されるため、税負担を抑えられます。
軽減税率の適用条件は次のとおりです。
- 売却する土地・建物を被相続人が10年以上所有していた
- 売却価格が6,000万円以下である
特例を利用すると、6,000万円以下の部分は14%(所得税10%+住民税4%)、6,000万円超の部分は20%の税率が適用されます。該当する場合は、確定申告をして軽減税率を適用しましょう。
相続財産の取得費加算の特例
「相続財産の取得費加算の特例」は、相続税を支払っている場合に取得費に加算できる制度です。これを活用すると、譲渡所得が減り、税負担を軽減できます。
適用条件は次のとおりです。
- 相続開始後10カ月以内に相続税の申告を行っている
- 相続税の課税対象となった財産を売却する
取得費が増えることで課税所得が減るため、相続税を支払っている場合はぜひ確認しましょう。
確定申告を怠った場合のリスクと対処法
相続した土地を売却し、確定申告が必要な場合に申告を怠ると、さまざまなリスクが発生します。税務署から指摘を受けるだけでなく、加算税や延滞税が発生する可能性があるため、確定申告が必要な場合は必ず期限内に手続きを行いましょう。
ここでは、確定申告をしなかった場合に発生するリスクと、対処法について解説します。
税務署や国税庁から未申告の通知が届く
確定申告を行わなかった場合、税務署や国税庁から「未申告の通知」が届くことがあります。税務署は、登記情報や不動産会社の取引データを通じて不動産の売買情報を把握しています。
未申告の通知を受け取った場合、速やかに申告すれば追加のペナルティを避けられる可能性があります。通知が届いた時点では、税務調査の前段階のため、指摘を受ける前に自主的に申告を済ませることが重要です。
税務調査が入る
確定申告を怠った場合、税務署が詳細な調査を行うことがあります。不動産の売却に関する申告漏れは、税務署が重点的に調査する対象です。特に、次のケースでは税務調査が入りやすくなります。
- 売却価格が高額
- 長期間確定申告をしていない
- 賃貸収入など他の収入がある
税務調査が行われた場合、売却の経緯や取引内容を証明するための書類を提出する必要があります。調査の結果、確定申告が必要と判断された場合、遅れた税金に加えて、ペナルティが科されます。
加算税や延滞税を請求される恐れがある
確定申告をしなかった場合、申告期限を過ぎると加算税や延滞税が発生します。主なペナルティには次のものがあります。
①無申告加算税
申告期限までに申告しなかった場合に課される税金です。納付すべき税額に応じて、次の割合で加算されます。
| 税額が50万円以下の場合 | 本来の税額の15% |
| 税額が50万円を超える部分 | 本来の税額の20% |
| 税額が300万円を超える部分 | 本来の税額の30% |
ただし、指摘を受ける前に自主申告すれば、加算税の割合は5%に軽減されます。
②延滞税
納税期限を過ぎると、延滞税が発生します。延滞税の利率は毎年変動しますが、おおむね年8%前後となることが多く、長期間未納が続くと税額が膨らむ可能性があります。
確定申告を忘れた場合の対処法
万が一、確定申告を忘れてしまった場合は、できるだけ早く自主的に申告を行いましょう。指摘を受ける前に申告すれば、加算税が軽減される可能性があります。
確定申告を忘れた場合の対応手順は次のとおりです。
- 売却益を計算し、本当に申告が必要か確認する
- 税務署へ相談する
- 必要な書類を準備する
- 確定申告書を作成し、速やかに提出する
- 追徴課税が発生した場合は速やかに納税する
手順に沿って、速やかに納付しましょう。
相続した土地の売却時にかかる税金の種類
相続した土地を売却する際には、さまざまな税金が発生します。相続時には相続税がかかることがありますが、売却時には「譲渡所得」に対する課税が発生するため、事前に税負担を把握しておくことが重要です。
売却に関わる税金には、所得に応じたものや登記・契約に必要なものなど、いくつかの種類があります。ここでは、代表的な税金について解説します。
譲渡所得税
譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に対して課税される税金です。土地の所有期間が 5年以下 の場合は「短期譲渡所得」となり税率が高く、5年超 の場合は「長期譲渡所得」となり税率が低くなります。
住民税
住民税も譲渡所得に応じて課税され、短期譲渡所得の方が長期譲渡所得よりも税率が高くなります。これは、売却した年の翌年に課税されます。
復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源確保のために課される税金で、譲渡所得税額に一定割合が加算されます。2037年まで適用される予定です。
印紙税
売買契約書を作成する際には、契約金額に応じた印紙税がかかります。契約書に貼付する印紙の額は、売却価格によって異なります。
登録免許税
土地や建物の相続登記を行う際にかかる税金です。税率は不動産の種類によって異なり、土地の相続登記と建物の所有権移転登記では適用される税率が変わります。
相続した土地の売却に関する確定申告のよくある質問
相続した土地の売却に関する確定申告について、多くの人が疑問に思う点を解説します。申告手続きや税負担の軽減策を理解し、適切に対応しましょう。
相続した土地の売却はどのような流れで進める?
相続した土地の売却は、通常の不動産売却とは異なり、相続登記や税務処理が必要になります。一般的な流れは次のとおりです。
- 相続した土地の名義を被相続人(故人)から相続人へ変更します。名義が変更されていないと売却できないため、まずは法務局で相続登記の手続きを行いましょう
- 土地の市場価値を把握し、不動産会社に査定を依頼します。また、必要に応じて測量や境界確定を行い、売却をスムーズに進めるための準備を整えます。
- 不動産会社を通じて買主を見つけ、売買契約を締結する。または不動産会社に直接買い取ってもらいます。契約時には、手付金の受け取りや契約書の作成が必要です。
- 売買契約後、決済を行い、土地の引き渡しを完了します。この際、売却代金を受け取り、所有権移転の手続きを実施します。
- 売却益が発生した場合、翌年の確定申告期間(通常は2月16日~3月15日)に確定申告を行います。特例や控除を適用する場合は、必要書類を準備し、適切に申告しましょう。
相続登記や不動産売却には複雑な手続きが伴います。不動産売却に不安がある場合は、不動産会社や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
相続した土地の売却については「相続した土地を売却するには税金がかかる!計算方法と減額方法を解説」や「相続した土地を売るタイミングはいつがベスト?判断基準と注意点を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
相続した土地の売却時の特別控除や特例は併用できる?
相続した土地を売却する際、適用できる特別控除や特例が複数ある場合、それらを併用できるかどうかが気になるところです。特例の併用可否は次のとおりです。
1.3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用可能
「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」や「空き家の3,000万円特別控除」は、譲渡所得から3,000万円を差し引く特例です。控除を適用した後、課税対象となる譲渡所得が残っていれば、「10年超所有していた居住用不動産の軽減税率の特例」を適用できます。
2. 取得費加算の特例と3,000万円特別控除は併用不可
「相続財産の取得費加算の特例」は、支払った相続税の一部を取得費に加算し、譲渡所得を減らす制度です。しかし、「3,000万円特別控除」とは併用できません。どちらか有利な方を選択する必要があります。
3.空き家特例とマイホーム特例は併用不可
「被相続人の居住用財産(空き家)の特例」と「居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の特例」は併用できません。どちらか一方のみ適用可能で、両方を同時に利用することはできません。
特例の適用条件や組み合わせによって税額が大きく変わるため、事前にシミュレーションを行い、税理士などの専門家に相談しながら最適な方法を選択することが重要です。
土地相続の税金については「土地の相続税はいくら?評価額の計算方法や控除を解説」や「国税庁の制度をもとに解説!相続した土地の売却にかかる税金と特別控除とは?」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
特別控除以外に利用できる税制優遇はある?
特別控除のほかにも、税負担を軽減できる制度がいくつかあります。その一つが「低未利用土地の100万円特別控除」です。これは、都市計画区域内にある低未利用土地を500万円以下で売却した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除できる制度です。一定の要件を満たす必要がありますが、該当する場合は活用を検討するとよいでしょう。
また、「ふるさと納税」も税制優遇の一つとして有効です。自治体に寄付を行うことで、寄付額の一部が住民税や所得税から控除されます。控除額には上限がありますが、実質2,000円の自己負担で返礼品を受け取ることができるため、節税しながら地域貢献ができる点が魅力です。
これらの制度を上手に活用することで、税負担を抑えつつ、資産の有効活用や地域支援につなげることが可能です。適用条件を確認し、自身に合った制度を活用しましょう。
相続した土地の売却に関する確定申告は、適用できる特例を活用し、正しい手順で申告しよう
相続した土地を売却した際、確定申告が必要かどうかを確認し、適切な手続きを行うことが重要です。譲渡所得が発生した場合や特例を適用する場合は、確定申告が求められます。
特例を活用すると税負担を軽減できますが、適用条件や組み合わせには制限があるため、事前に確認が必要です。また、申告期限を過ぎるとペナルティが科されるため、必要書類を揃え、余裕をもって準備しましょう。
確定申告に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談するのも有効です。適切な申告を行い、不要な税負担を避けることができます。






