家を処分する方法には、不動産会社を通じた売却、解体後の土地売却、寄付、相続放棄などさまざまな選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、税金や手数料も発生するため、事前に費用や手続きの流れを把握することが重要です。本記事では、各処分方法の特徴や費用、手続きの流れを詳しく解説します。スムーズに進めるためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
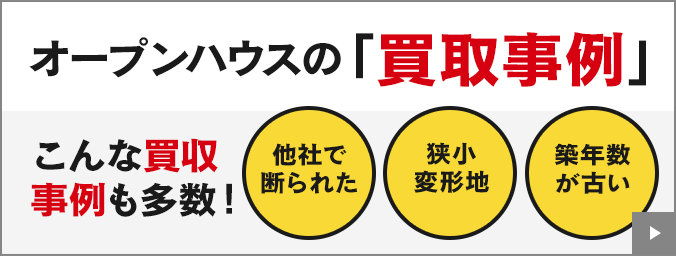
家の処分方法一覧とそのメリット・デメリット
家の処分方法には、売却、寄付、相続放棄などさまざまな選択肢があります。各方法にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。ここでは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
処分方法1.不動産仲介会社を利用して売却する
市場価格に近い価格で売却でき、仲介業者のサポートも受けられます。ただし、売却までに時間がかかることがあり、仲介手数料が発生します。
処分方法2.不動産会社に直接売却する
買い手を探す手間がなく、短期間で現金化できる方法です。仲介手数料も不要ですが、買取価格は市場価格より低い金額になることが多いです。
処分方法3.公共団体やNPOに寄付する
売却が難しい場合や社会貢献を目的とする場合は、自治体やNPOに寄付する方法もあります。ただし、すべての団体が受け入れるわけではないため、事前確認が必要です。
処分方法4.相続前なら放棄も検討可能
相続放棄をすれば、固定資産税や維持管理の負担を回避できます。しかし、不動産だけでなく他の財産(預貯金など)も放棄する必要があります。また、相続人の一部が放棄すると、残った相続人が負担を引き継ぐため、慎重な判断が必要です。
家の相続については「一人っ子の相続におけるメリット・デメリットとは?手続きの流れや注意点も解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
処分方法5.相続土地国庫帰属制度を利用する
一定の条件を満たせば、国に引き取ってもらえる制度です。ただし、更地であることが条件で、申請には手数料がかかり、負担金(原則20万円以上)が発生する可能性があります。
処分方法6.個人売買する
知人や親族に売却する、または自分で買い手を探して契約する方法です。仲介手数料がかからない点がメリットですが、契約手続きや税務処理を自分で行う必要があり、リスク管理が求められます。売却経験がない場合は、司法書士などの専門家に相談するのが安心です。
家の処分方法の具体的な進め方【方法別】
家の処分方法が決まったら、次は具体的な手続きを進めます。方法によって必要な書類や進め方が異なるため、事前に流れを整理しておくことが重要です。
ここでは、代表的な処分方法ごとの進め方を詳しく解説します。
方法1.不動産仲介会社に家を売却する手順
不動産仲介会社を通じて家を売却する場合、市場価格に近い価格で売却できる一方、買い手が見つかるまでに時間がかかることもあります。
- 不動産会社を選ぶ(複数社に査定を依頼し、比較)
- 売却価格を決定する(査定結果をもとに販売価格を設定)
- 媒介契約を結ぶ(仲介会社と契約を交わす)
- 買い手を探す(広告掲載や内覧対応を行う)
- 売買契約を締結する(契約書を作成し、手付金を受け取る)
- 決済と引き渡しを行う(残金を受領し、所有権移転手続き)
方法2.不動産会社に直接売る方法と手順
不動産会社に直接売却する方法は、買い手を探す手間が不要で、短期間での売却が可能です。
ただし、市場価格よりも低い価格での取引になることが多いため、慎重な判断が求められます。
- 複数の買取業者に査定を依頼する(オンライン査定や訪問査定を活用)
- 提示された買取価格を比較し、最適な業者を選ぶ(価格だけでなく、対応の速さや信頼性も確認)
- 売却条件を交渉し、契約を締結する(引き渡し時期や手数料などの条件を事前に確認)
- 決済と物件の引き渡しを行う(売買代金を受け取り、所有権移転手続きを完了)
方法3.公共団体やNPOへ家を寄付する手順
売却が難しい場合や、地域貢献を目的とする場合には、自治体やNPO法人に寄付することも選択肢の一つです。
ただし、寄付に際して修繕費用や登記手続きの費用が発生することもあるため、事前に確認しておくことが重要です。
- 寄付を受け付けている自治体やNPOに相談する(対象団体があるか、受け入れ可能な条件を確認)
- 受け入れ条件を確認する(建物の状態や立地、修繕費用の負担が必要かなど)
- 必要書類を準備する(登記簿謄本、固定資産税納税通知書、所有権移転に必要な書類など)
- 所有権移転手続きを行う(必要に応じて移転登記費用が発生する)
方法4.相続放棄で家を手放す手順
相続放棄をすれば、不要な不動産を引き継がずに済み、固定資産税や管理の負担を回避できます。しかし、他の財産も放棄することになるため、慎重な判断が必要です。
- 相続人全員で協議し、相続放棄を検討する(相続放棄は一部のみの放棄はできず、全財産を放棄する点に注意)
- 家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う(被相続人が亡くなってから3カ月以内が期限)
- 申立書類を準備し、裁判所に提出する(戸籍謄本、被相続人の死亡証明書などの必要書類を揃える)
- 審査が完了し、相続放棄が認められる(追加の説明や書類提出が求められることもある)
方法5.相続土地国庫帰属制度を利用する手順
相続した土地の管理が難しい場合、2023年に施行された相続土地国庫帰属制度を利用し、国に引き取ってもらうことができます。
ただし、すべての土地が対象となるわけではなく、建物が残っている土地や、管理負担が大きすぎる土地は認められないことがあります。そのため、事前に条件を確認しておくことが重要です。
- 法務局で制度の要件を確認する(対象となる土地かどうかを事前にチェック)
- 申請書類を準備する(登記情報、土地の境界確認書類、土地の状況を証明する資料など)
- 申請手数料を支払い、審査を受ける(審査には数カ月かかることが一般的)
- 審査を通過した場合、土地の管理責任が国に移る(負担金を支払う必要がある場合もあり、事前の確認が重要)
方法6.家を個人売買で売却する手順
知人や親族に売却する、または自分で買い手を見つけて売却する場合、不動産会社を通さないため仲介手数料を節約できます。しかし、個人間の取引はトラブルのリスクが高く、契約書の作成や登記手続きを慎重に進める必要があります。
特に、不動産の売買契約は法的な要素が多いため、司法書士や弁護士に相談すると安心です。
- 買い手を見つけ、売却価格を設定する(市場価格を調査し、適正価格を決める)
- 契約条件を交渉し、売買契約書を作成する(必要に応じて専門家に確認)
- 手付金を受け取り、売買契約を締結する(契約書の内容を双方で再確認する)
- 決済・引き渡しを行い、所有権移転手続きを完了する(登記の申請は司法書士に依頼するとスムーズ)
家の処分にかかる税金・費用の目安とは
家を処分する際には売却費用、税金、解体費用などのコストが発生します。特に不動産売却で利益が出た場合は譲渡所得税がかかるため、想定以上の負担になることも。
高額な費用が発生する可能性があるため、事前にコストを把握し、計画的に進めることが重要です。ここでは、具体的な税金や費用の種類と目安を解説します。
家を処分して利益が出たときは税金がかかる
家を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が発生します。税率は所有期間によって異なり、次の計算式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)
- 取得費(購入価格、登記費用、不動産取得税など)
- 譲渡費用(仲介手数料、解体費用など)
税率(売却した年の1月1日時点の所有期間による)
- 5年以下(短期譲渡所得):約39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
- 5年超(長期譲渡所得):約20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
ただし、不動産の売却には、税金の特別控除や特例が存在します。例えばマイホーム(居住用財産)を売却した場合は、所有期間に関係なく「3,000万円の特別控除」が利用できる可能性があります。処分しようとしている家の状態によって、適用できるかどうかが変わるため、実際に使えるかどうかを調べておきましょう。
不動産の売却については「【完全ガイド】親の家を売る方法とは?後悔しないための準備・流れ・税金まで徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
家を処分するのにかかる費用
家の処分には、売却時の手数料や解体費用、登記費用などの諸費用が発生します。処分方法によって金額は異なりますが、主な費用は次のとおりです。
不動産会社を通じて売却する場合、売却価格に応じた仲介手数料が発生します。
仲介手数料は「売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税」で計算されます。この費用は売却が成立した際に発生するため、売却額を見積もる際に考慮しておきましょう。
建物を解体して更地として売却する場合は、解体費用も考慮する必要があります。
| 建物の種類 | 解体費用の目安(坪単価) |
| 木造住宅 | 3万~5万円/坪 |
| 鉄骨造住宅 | 4万~7万円/坪 |
| RC(鉄筋コンクリート)住宅 | 5万~9万円/坪 |
木造住宅の解体費用は坪あたり3万円から5万円程度で、30坪の家を解体する場合、約90万~150万円の費用がかかります。鉄骨造や鉄筋コンクリート造の場合は、さらに高額になることが多いため、売却の際に解体が必要かどうかを慎重に判断しましょう。
また家の売却や、相続した不動産を処分する場合には、登記手続きが必要になります。
司法書士に依頼した場合の登記費用は、抵当権抹消登記で約1万円~2万円、相続登記で約5万~10万円程度です。
家を処分する際に知っておきたい基礎知識
家を処分する際は、法律や手続きに関する基本知識を持っておくことが大切です。特に、不動産の権利関係、市場価格の調査、リフォームの必要性などを把握しておくと、スムーズに進められます。
ここでは、家を処分する前に知っておくべきポイントを解説します。
権利関係や名義の確認方法
家を処分する前に、登記簿謄本を確認し、不動産の権利関係を明確にしておくことが重要です。登記簿謄本は法務局で取得でき、現在の所有者や抵当権の有無を確認できます。
所有者が複数人いる場合は、売却には共有者全員の同意が必要になります。また、相続によって名義が被相続人のままになっている場合は、相続登記を完了しないと売却できません。相続登記には、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要となるため、早めに準備を進めることが大切です。
また、住宅ローンが残っている場合は、売却時に抵当権を抹消する必要があります。手続きには金融機関との調整が必要となるため、残債の処理方法を検討しておきましょう。
こうした権利関係を事前に整理しておくことで、家の処分をスムーズに進めることができます。
家の相続については「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
市場価格の調査と適正価格の設定
家を売却する際は、市場価格を事前に調査し、適正な売却価格を設定することが重要です。価格設定を誤ると売れ残るリスクが高まり、最終的に値下げせざるを得ないこともあります。
市場価格を調査する方法として、次の手段があります。
- 不動産ポータルサイトで類似物件の価格を調べる
- 不動産会社に査定を依頼する
- 国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で過去の取引事例を確認する
また、不動産会社の査定額は一社だけでなく複数社を比較し、適正な価格を判断することが大切です。
売却を急ぐ場合は、不動産会社による買取を利用すると短期間で処分できますが、市場価格より安くなる傾向があります。価格と売却スピードのバランスを考えながら、最適な方法を選びましょう。
リフォームや修繕の必要性とタイミング
家を売却する際は、リフォームや修繕が必要か慎重に判断することが大切です。修繕で売却価格が上がることもありますが、費用対効果が見合わない場合もあります。
築年数が新しく軽微な傷みであれば、壁紙の張り替えやクリーニングなどの低コストな改善で印象を良くできます。一方、築年数が古い場合は、リフォームせずに売る方が有利なこともあります。
リフォームをする場合、売却前に行うか、買主に委ねるかを検討しましょう。また、費用をかけずに「現状のまま売却」する方法もあるため、状況に応じて最適な選択をしましょう。
家を処分するべき?悩んだときに参考にしたい3つのポイント
家を処分するか迷う人は多いですが、決断を先延ばしにすると維持費や税負担が増え、管理の手間もかかります。
判断する際は、「処分を検討するきっかけ」「空き家のリスク」「維持コスト」の3つを整理することが大切です。
家の処分を考えるきっかけとは
家を処分する理由はさまざまですが、主に相続や住み替えによる空き家の発生が挙げられます。築年数が古くなると修繕費がかさみ、資産価値が下がるため、活用の見込みがない場合は売却や解体を検討しましょう。
空き家がもたらすリスク
放置すると老朽化が進み、倒壊や高額な修繕費が必要になるほか、不法侵入や放火のリスクも高まります。
さらに、自治体に「特定空き家」に指定されると固定資産税の優遇がなくなり、税負担が増大するため、長期間の放置は避けるべきです。
家の維持にかかるコスト
家を所有するだけで固定資産税や都市計画税が発生し、年間10万円以上かかることもあります。さらに、修繕費用は数十万~数百万円にのぼるケースもあり、最終的に解体費用も考慮する必要があります。
長期的なコストを考慮し、早めに処分を検討しましょう。
最適な家の処分方法を選ぶためには専門家に相談しよう
家の処分方法には売却、解体、相続放棄などがあり、最適な選択肢は状況によって異なります。売却時の税金や相続登記など専門知識が必要な場面では、不動産会社・税理士・司法書士に相談することが重要です。
不動産会社は市場価格の調査や売却戦略、直接買取の提案を行います。税理士は譲渡所得税や節税対策をアドバイスし、司法書士は相続登記や抵当権抹消の手続きをサポートします。
自己判断で進めると税負担が増えたり、売却に時間がかかる可能性があります。専門家のサポートを受けることで、最適な方法を選び、スムーズに手続きを進めましょう。






