親の財産を一人で相続することになった。そのようなとき、「何から始めればいいの?」「トラブルになることはある?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。一人っ子の相続は、他の相続人との争いが起こりにくく、手続きがスムーズに進むケースが多い一方で、相続税の負担がすべて自分にかかる、親の借金を引き継いでしまうといったリスクもあります。このコラムでは、一人っ子として相続を進めるうえで、あらかじめ知っておきたい基礎知識や手続きの流れ、メリット・デメリット、そして注意点について解説します。
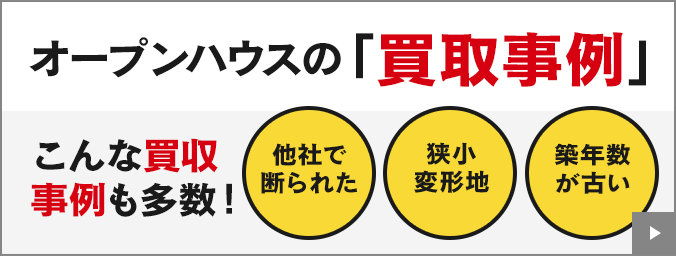
一人っ子の相続の仕組みとは?

一人っ子の場合、兄弟姉妹がいないため、相続人の数が少なくなるのが大きな特長です。
通常、相続人となるのは「配偶者」と「子ども」が中心です(これを法定相続人といいます)。一人っ子であれば、その子どもが唯一の相続人となるか、配偶者と一緒に相続する形になります。
たとえば、父親が亡くなり、母親と一人息子が相続人となった場合、民法のルールに従えば、遺産は母親と息子で2分の1(50%)ずつ分けるのが基本です。
一方、母親がすでに亡くなっている場合や存在しない場合は、一人っ子である息子がすべての遺産を相続することになります。
家を相続したときについては「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
法定相続人の基本ルール
法定相続人とは、民法で定められた「遺産を相続できる資格を持つ人」のことをいいます。誰が相続人になるかは、亡くなった方(被相続人)との関係性によって決まり、相続の順位が定められています。
相続人となる順番は、以下のとおりです。
| 順位 | 相続人の範囲 | 優先順位 | 備考 |
| 第1順位 | 子ども(養子を含む) | 最優先 | 子どもがすでに亡くなっている場合は、その孫が代わりに相続(代襲相続)します。 |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 第1順位がいない場合 | 両親がいない場合は祖父母が相続します。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(甥・姪を含む) | 第1・第2順位がいない場合 | 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続します。 |
| 常に相続人 | 配偶者 | 常に相続人 | 上記の順位の人と一緒に相続します。 |
配偶者は常に相続人となるため、たとえば父親が亡くなった場合には、母親と子どもが相続人となります。
子どもが複数いれば、子どもたちの相続分は均等に分けられます。一方、一人っ子であれば。その子どもがすべての遺産を相続する可能性があります。もし子どもがいない場合は、次に優先されるのは「親(被相続人の父母)」です。親もすでに亡くなっている場合には、「兄弟姉妹」が相続人となります。
このように、誰が相続人になるかは家族構成によって変わります。これは相続税の計算や相続手続きにも影響するため、自分がどの順位にあたるのかを事前に把握しておくことが重要です。
一人っ子と兄弟姉妹がいる場合との違い
一人っ子であることの大きな特徴の一つが、相続できる財産の割合が大きくなる点です。
たとえば、相続人が「配偶者と子ども一人」であれば、民法の規定では、配偶者と子どもがそれぞれ2分の1(50%)ずつの割合で遺産を相続します。
これに対し、相続人が「配偶者と子ども二人」の場合では、配偶者が2分の1(50%)を相続し、残りの2分の1を子ども二人で分け合うことになります。その結果、子ども一人あたりの取り分は4分の1(25%)となります。
このように、兄弟姉妹がいない一人っ子は、相続する財産の割合が多くなる傾向があるのです。
一人っ子が相続するメリット

一人っ子が相続人になる場合、手続き面や心理的な負担の少なさといった点で、いくつかのメリットがあります。ここでは代表的なメリットをご紹介します。
相続手続きがスムーズに進められる
一人っ子が相続人であれば、遺産の分け方について他の相続人と話し合う必要がないため、相続手続きがスムーズに進むのが大きなメリットです。
たとえば相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかを決めるために「遺産分割協議」を行う必要があります。話し合いがまとまらなければ、手続きが長引いたりストップしてしまったりすることもあります。
しかし、一人っ子であればこの協議が不要なため、手続きにかかる時間や労力、精神的ストレスを大幅に軽減できます。
また、提出書類も少なく済み、遺産分割協議書や印鑑証明書などの準備の手間も軽減されます。行政手続きや銀行口座の解約なども、自分一人の判断で進められるのが利点です。
不動産の相続登記も一人で進められる
相続によって不動産(土地や建物)を引き継ぐ際には、「相続登記(所有権移転登記)」の手続きが必要になります。これは、法務局に対して不動産の名義変更を届け出るもので、登記を済ませないと売却や担保設定ができません。
2024年4月からは、この相続登記が義務化されており、正当な理由なく期限内に行わない場合は過料(罰金のようなもの)が課せられる可能性もあります。
一人っ子であれば、この登記手続きも他の相続人と調整する必要がなく、自分だけで完結できるため、スムーズに進めやすいというメリットがあります。
一人っ子が相続するデメリット・注意点

一人っ子相続には、手続きがスムーズであるなどの多くのメリットがある一方で、相続人が一人であるがゆえのデメリットや注意点も存在します。
ここでは、一人っ子が直面しやすい代表的なデメリットを解説します。
相続税の支払い負担が一人に集中しやすい
相続税とは、相続した財産が一定の金額(基礎控除額※)を超える場合に課される税金です。
※ 相続税の対象となる財産からあらかじめ差し引くことができる非課税の金額のこと
この基礎控除額は、次のような計算式で決まります。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
たとえば、一人っ子が相続人で、配偶者(母親など)がいる場合、法定相続人は二人になるため、基礎控除額は3,600万円(3,000万円+600万円×2)になります。
仮に遺産総額が6,000万円だった場合、3,600万円を差し引いた2,400万円が相続税の課税対象となります。
一方で、相続人が配偶者と子ども二人(兄弟二人)の場合は、法定相続人は三人となるため、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3)に増えます。その場合、課税対象額は1,200万円に抑えられます。
このように、相続人の人数が少ない一人っ子の場合は、控除額も少なくなる分、課税対象となる金額が大きくなり、結果的に相続税の負担が重くなる可能性があるのです。
一人で相続手続きを行う必要があり、負担が大きい
一人っ子が相続人となる場合、相続に関わる手続きをすべて自分ひとりで進める必要があるという点も、大きな負担となり得ます。
通常は複数の相続人で分担できる以下のような作業も、すべて対応しなければなりません。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、自分の戸籍の取り寄せ
- 預金・不動産・株式・保険・借金などの財産目録の作成
- 金融機関や法務局での名義変更・解約・相続登記などの各種手続き
これらは基本的に平日日中に役所や銀行へ出向く必要があるため、仕事や家庭と両立しながら対応するのが難しいと感じる方も少なくありません。
もし「手続きが煩雑で不安が大きい」「仕事の合間には対応できない」と感じた場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に依頼するのもひとつの方法です。
費用はかかりますが、時間の節約や手続きミス・トラブルの回避につながるため、自分の状況に応じて専門家の力を借りることも検討するとよいでしょう。
一人っ子でも相続放棄を検討すべきケース

相続放棄とは、親などから引き継ぐ財産(資産や負債)をすべて放棄するという手続きです。「一人っ子だから、親の遺産は全部引き継がなければならない」と考える方も多いですが、場合によっては相続しない方が得策になるケースもあります。
その理由は、相続には「プラスの財産(預貯金・不動産など)」だけでなく、「マイナスの財産(借金・未払いの税金など)」も含まれているためです。
つまり、財産の中身をよく確認せずに相続すると、借金まで引き継いでしまうリスクがあるのです。
ここでは、一人っ子でも相続放棄を検討すべき典型的なケースを紹介します。
相続財産よりも借金のほうが多い場合
相続財産のなかに含まれる借金や未払い金などのマイナスの財産が、預貯金や不動産といったプラスの財産を大きく上回っている場合は、相続放棄を検討すべき典型的なケースです。
相続放棄をすることで、多額の借金を背負うリスクを避けることができ、自分の生活への悪影響を防ぐことができます。
ただし、相続放棄には注意点があります。
まず、申し立ての期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から原則3カ月以内と定められています。また、相続財産に手をつけてしまうと、放棄が認められなくなる場合があるため要注意です。
たとえば、故人の預金を引き出して使ったり、不動産を勝手に売却してしまった場合などは、相続したとみなされることがあります。
特に一人っ子の場合、代わりに相続してくれる兄弟姉妹がいないため、マイナスの財産を自分ひとりで背負うリスクがあります。そのため、財産内容を早めに確認し、相続するか放棄するかの判断を慎重に行うことがとても重要です。
被相続人が連帯保証人になっていた場合
被相続人が連帯保証人として他人の借金を保証していた場合、その保証債務も相続対象になります。つまり、保証していた相手(主債務者)が返済できなくなった場合、相続人がその借金を全額支払わなければならないという責任を負うことになるのです。
たとえば、親が知人の事業融資の連帯保証人になっていたものの、その知人が事業に失敗して返済不能になった場合、相続人である一人っ子に対して数千万円単位の返済請求が届くといったケースも起こりえます。
こうした思わぬ負債を避けるためにも、相続が発生したら財産調査とあわせて、保証契約の有無も必ず確認することが大切です。
借金と生命保険金のバランスによって判断が必要な場合
相続を放棄すべきかどうかは、借金の金額だけを見て決めてしまうのは早計なこともあります。特に注意しておきたいのが、生命保険金の存在です。
生命保険金は相続財産とは別に扱われ、受取人固有の財産とされています。そのため、たとえ相続放棄をしても、受取人として指定されていれば保険金を受け取ることができます。
たとえば、相続財産に1,000万円の借金があったとしても、あなたが受取人となっている生命保険金が2,000万円ある場合、実質的には1,000万円のプラスと考えることができます。
このように、借金がある場合でも、生命保険金などの資産とのバランスによっては、相続を続けたほうが有利になるケースもあります。放棄するかどうかは、財産全体をよく確認したうえで、状況に応じて慎重に判断することが大切です。
相続手続きに必要な書類

相続の手続きを進めるにあたっては、さまざまな書類を準備する必要があります。一人っ子の場合でも、基本的に必要となる書類は他のケースと大きく変わりません。
以下は、代表的な必要書類です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 固定資産評価証明書
- 遺言書(ある場合)
- 遺産分割協議書
これらの書類は、金融機関の手続きや不動産の名義変更、相続税の申告など、さまざまな場面で提出が求められます。あらかじめまとめて準備しておくことで、手続きをスムーズに進めやすくなります。
特に一人っ子の相続では、他の相続人の書類を集める手間はありませんが、戸籍を通じて「相続人が自分だけであること」をしっかり確認・証明することが大切です。
万が一、知らなかった兄弟姉妹や養子などが判明することもあるため、戸籍の調査は丁寧に行うことをおすすめします。
相続手続きの書類については「不動産の相続手続きに必要な書類をご紹介」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
一人っ子の相続手続きの進め方とは?

ここからは、一人っ子が相続を開始した際に知っておきたい、基本的な手続きの流れを解説します。
「相続人は自分だけか?」「遺言書はあるか?」といったポイントを順を追って確認することで、余計なトラブルを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。
①相続人が自分だけかを調査する
まずは、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を出生から死亡までの分すべて取り寄せ、他に相続人がいないかを確認します。
過去の結婚歴や認知した子どもがいる場合、異母兄弟などが相続人になる可能性もゼロではありません。他に相続人がいないことが確認できれば、一人っ子のあなたが単独で遺産を引き継ぐことができ、遺産分割協議も不要となります。
②遺言書の有無を調べる
相続の手続きでは、遺言書がある場合、その内容が優先されます。まずは遺言書の有無をしっかり確認しましょう。
- 自筆証書遺言:自宅の引き出しや金庫などに保管されていることが多いです。2020年以降は法務局に保管されているケースもあります。
- 公正証書遺言:公証役場で原本が保管されており、家庭裁判所の「検認手続き」は不要です。
- 秘密証書遺言:通常は見かけませんが、まれに存在する形式です。
なお、封がされた遺言書が見つかった場合は、勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。遺言書があるかないかで手続きの進め方が大きく変わるため、丁寧に確認しておきましょう。
③被相続人の財産を調査する
次に、被相続人が持っていた預貯金・不動産・有価証券・生命保険などのプラスの財産と、借金や未払い金などのマイナスの財産を調査します。
具体的には、以下のような手段で確認します。
- 銀行口座の通帳や取引明細の確認
- クレジットカードの利用明細や請求書の確認
- 不動産については、固定資産税の納税通知書や登記簿謄本の取得
- 借金や連帯保証契約の有無は、契約書や通帳の動き、生前の会話なども手がかりに
契約書がないケースもあるため、日常的な会話やメモ、手紙なども大切な情報源となる場合があります。
④遺産分割協議を行う(他に相続人がいた場合)
万が一、他に相続人がいた場合は、誰がどの財産を受け取るかを話し合う「遺産分割協議」を行います。一人っ子で相続人が自分だけなら協議は不要ですが、たとえば被相続人の配偶者(母親など)が健在の場合は、その方との間で協議が必要です。
協議の内容がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名と実印を押します。この書類は、銀行での解約手続きや不動産の相続登記などで提出が求められます。
万が一、意見がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判に進むこともあります。
⑤口座の解約や不動産の相続登記などを行う
財産の分配内容が確定したら、各種名義変更や解約の手続きを行います。
- 銀行口座の解約:被相続人名義の口座を解約し、相続人の口座に資金を移す。
- 不動産の相続登記:法務局で名義変更(所有権移転登記)を行う。
※2024年4月以降は、相続登記が義務化され、原則3年以内に手続きが必要です。 - 株式や投資信託:証券会社に連絡し、相続手続きを進める。
- 自動車や保険:車の名義変更や、生命保険金の請求などを行う。
⑥相続税がかかる場合は、申告と納税を行う
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要になります。申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。
この期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税といったペナルティが発生する可能性があるため、早めに準備を進めることが大切です。
また、一人っ子の場合は相続人が自分だけになるため、税負担を他の相続人と分け合うことができません。そのため、生前から生命保険の非課税枠の活用や生前贈与などの対策を講じておき、納税資金をあらかじめ確保しておくことも重要なポイントです。
一人っ子の相続に関するよくある質問

ここでは、一人っ子の相続について多くの方が疑問に思うポイントについてお答えします。一人っ子特有のケースや、相続全般に関する注意点もあわせて確認しておきましょう。
①一人っ子が亡くなった場合、遺産の相続人は誰ですか?
一人っ子ご本人が亡くなった場合でも、相続人の決まり方は民法に定められた法定相続の順序に従います。
まず、配偶者がいる場合は、常に相続人になります。そのうえで、以下のように順位が決まっています。
- 第1順位:子ども(養子を含む)
- 第2順位:親(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続)
ただし、一人っ子で兄弟姉妹もおらず、親や祖父母などの直系尊属もいない場合は、相続人がいない状態になります。
その場合、被相続人と特別な関係があった方(たとえば長年介護をしていた親族や内縁の配偶者など)が「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てを行い、財産の一部を受け取れる可能性があります。
それも該当者がいない場合、遺産は最終的に国の財産(国庫)に帰属することになります。
②一人っ子でも遺言書は必要ですか?
「相続人が自分しかいないから、遺言書は必要ないのでは?」と考える方もいらっしゃいますが、一人っ子の場合でも遺言書の作成はおすすめです。
その理由は、以下のような点にあります。
- 遺産分割協議が不要になるため、金融機関や法務局での各種手続きがスムーズに進む
- 万が一、他の親族が相続に関して意見を述べてきたとしても、遺言書があれば法的な効力によってトラブルを回避できる
- 生前に「どの財産をどのように引き継いでほしいか」を明確に伝えておくことで、残された家族の負担を減らせる
また、将来的にご自身が亡くなったときのことを考えた場合、配偶者や子どもがいない方は、誰が自分の財産を引き継ぐのかを遺言で明確にしておくことが、無用な混乱やトラブルを防ぐポイントになります。
③相続税が払えないときはどうなる?
相続財産の多くが不動産で、現金や預貯金がほとんどないという場合には、相続税の納税資金に困ることもあります。
そういったケースでは、以下のような制度を利用することができます。
- 延納:相続税をすぐに全額支払うのではなく、分割で最長20年まで支払える制度です。
- 物納:不動産や有価証券など、相続した財産そのもので相続税を納める方法です。一定の要件を満たす必要があります。
「現金がないから納税できない」と放置してしまうと、延滞税の加算や財産の差し押さえにつながる可能性もあるため、早めに税務署へ相談し、必要に応じて税理士など専門家のサポートを受けることが大切です。
被相続人(親)の家を売却、処分を検討している方は「【完全ガイド】親の家を売る方法とは?後悔しないための準備・流れ・税金まで徹底解説」や「家の処分を検討している人必見!最適な方法と手順を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
相続は一人で抱え込まず、早めに相談しましょう!
このコラムでは、一人っ子が相続をする場合の遺産の分け方・手続きの進め方・注意点について解説しました。
一人っ子の相続は、兄弟姉妹がいないため手続きがシンプルになりやすく、相続できる割合が大きくなるというメリットがあります。その一方で、相続税や借金などの負担がすべて一人に集中するリスクもあるため、冷静に全体の財産状況を見極めることが大切です。
たとえば、戸建てなどの不動産を相続したものの「納税資金が足りない」「維持管理が難しい」といったお悩みがある場合は、早めに売却や不動産会社への相談を検討すると安心です。
また、2024年4月からは相続登記が義務化されており、一定期間内に登記を行わないと過料(罰則金)が科される可能性もあります。放置せず、早めに手続きを進めるようにしましょう。






