相続した土地を「いつ売るべきか」で悩んでいませんか?使う予定のない土地を持ち続けていると、税金や管理の負担が増えるばかりか、将来的に価格が下がってしまう可能性もあります。
特に「5年以内に売却するかどうか」は、税金の優遇制度や課税対象に大きく影響する重要なポイントです。売却タイミングを間違えると、数十万円単位で税額が変わってくるケースも少なくありません。
本コラムでは、相続した土地を5年以内に売却するメリット・デメリット、節税につながる特例、注意すべき手続きや税金の種類について、わかりやすく解説します。
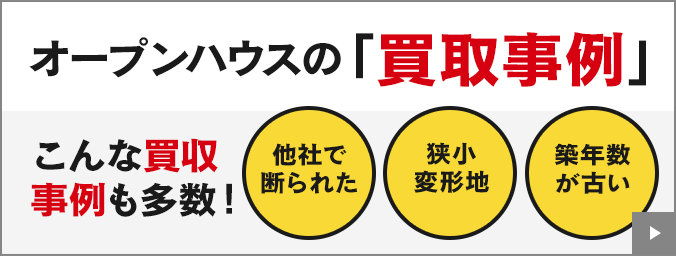
相続した土地を5年以内に売却するメリット

ここでは、相続した土地を5年以内に売却することで得られる主なメリットを紹介します。
市場価値が下がるリスクを回避できる
土地の価格は、景気や周辺の環境によって上下します。駅が近かったり、お店が増えたりすれば価値が上がる一方で、人口が減ったり、再開発が進まない地域では価値が下がることもあります。
特に地方では、買い手が少なくなることで土地の価格が年々下がっていく傾向があります。使う予定のない土地を持ち続けていると、「売っておけばよかった」というタイミングを逃してしまうかもしれません。
早めに売却を検討することで、価格が下がる前に現金化できる可能性が高まり、リスクを回避できます。将来のためにも、今の市場価値を把握しておくことが大切です。
相続した土地を3年以内に売却する場合については「相続した土地は3年以内に売却すべき?税金・控除を詳しく解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
維持コスト(管理費・固定資産税など)を抑えられる
土地を持っているだけで、毎年「固定資産税」や「都市計画税」といった維持費がかかります。たとえ何も建てていなくても、税金の支払い義務は発生します。
固定資産税は評価額の約1.4%、都市計画税は最大0.3%が目安です。年間では少額でも、10年・20年と持ち続けると、数十万〜数百万円の負担になることもあります。
特に更地のままだと税負担が大きくなり、住宅用地の軽減措置が受けられず、固定資産税が最大6倍、都市計画税が約3倍になるケースも。
今後使う予定がない土地であれば、早めに売却して維持コストをなくすことも有効な選択肢です。
相続した土地を売るタイミングについては「相続した土地を売るタイミングはいつがベスト?判断基準と注意点を徹底解説」や「相続した土地をすぐ売却するべきケースとは?メリット・手順・税金・特別控除を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
相続した土地を5年以内に売却するデメリット

相続した土地は早めに売った方がいい場合もありますが、売却時期によってはデメリットもあります。ここでは、5年以内に売るときに気をつけたいポイントをご紹介します。
短期譲渡所得として課税され税率が高くなる
土地を売って利益が出ると、「譲渡所得税」がかかります。税率は土地の所有期間によって変わり、5年以下なら「短期譲渡」として約39.63%、5年を超えると「長期譲渡」で約20.315%になります。
ただし、相続で引き継いだ土地の場合は、自分が相続した日ではなく、親など元の所有者が土地を取得した日から数えます。たとえば、親が5年以上その土地を所有していれば、相続後すぐに売っても「長期譲渡」として扱われ、税率は低くなります。
一方、親が5年未満しか所有していなかった場合は、「短期譲渡」となり、高い税率が適用されるため、事前に確認しておくことが大切です。
取得費が不明な場合、税金が増える可能性がある
土地を売るときの税金は、「売った金額から、買ったときの金額(取得費)を引いた差額」にかかります。ただし、相続した土地の場合は、親や祖父母がいくらで購入したのか分からないことも多く、取得費が不明になるケースがあります。
その場合は、税法上「売却価格の5%を取得費とみなす」というルールがあり、結果的に実際よりも利益が大きく計算されてしまい、税金が高くなるおそれがあります。
たとえば、本来2,000万円で買った土地でも、記録がなければ5%の100万円しか引けず、大きな税負担になる可能性も。こうした事態を防ぐためにも、契約書や領収書などの資料を事前に確認・保管しておくことが大切です。
売却するタイミングによっては特例が使えないことがある
相続した土地を売るときは、条件を満たせば税金を軽くできる「特例制度」が使えることがあります。ただし、これらの特例には期限や条件があり、タイミングによっては利用できないことも。
たとえば「取得費加算の特例」は、相続税を支払った人が、相続開始の翌日から3年以内に土地を売ることで適用されます。これにより、相続税の一部を土地の取得費に上乗せでき、譲渡所得税が軽減されます。
しかし、期限を過ぎるとこの特例は使えず、税金が高くなる可能性も。特例の内容や期限を事前にしっかり確認し、計画的に売却を進めることが大切です。
相続した土地を売却する際の注意点

相続した土地をスムーズに売るためには、事前に知っておきたいポイントがあります。ここでは、意外と見落としがちな注意点について解説します。
相続登記(名義変更)を済ませないと売却できない
土地を売るには、まず「相続登記(名義変更)」の手続きを済ませる必要があります。亡くなった方の名義のままでは、売却することはできません。書類上の所有者を、相続人である自分の名前に変更する必要があります。
相続登記に必要な書類には、次のようなものがあります。
- 登記申請書
- 収入印紙
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票 など
これらの書類を集めて法務局に申請する必要がありますが、専門的な内容が多いため、多くの方は司法書士に依頼しています。
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続開始を知ってから3年以内に手続きをしないと、最大10万円の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。忘れずに、早めに対応しましょう。
家の相続については「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
譲渡費用や取得費の証明資料を事前に準備しておく
土地を売る前に、譲渡所得を計算するための証明書類をそろえておきましょう。たとえば、親が土地を購入したときの契約書や領収書、造成費・測量費などの明細書、売却時の仲介手数料や印紙税の領収書などが該当します。
これらがあれば、「取得費」や「売却にかかった費用」として差し引くことができ、結果的に税金を減らせます。
証明書類が見つからないと「取得費が不明」として、売却価格の5%しか経費にできません。そのぶん利益が大きくなり、税金が高くなるおそれがあります。
売却を検討しているなら、早めに手元の資料を確認し、必要書類を整理しておくことが大切です。
売却後は確定申告が必要になる可能性がある
相続した土地を売って利益が出た場合は、翌年に「確定申告」が必要になります。たとえ会社で年末調整を受けていても、土地を売った利益は別で申告しなければなりません。
利益は「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算され、マイホームに関する特例を使う場合や、他に収入がある人も申告が必要になることがあります。
一方、売却して損が出たときは申告しなくてもよい場合がありますが、自己判断で申告を忘れると、延滞税や罰金がかかることもあるので注意しましょう。
相続した土地を売却するまでの流れ

ここでは、相続発生から実際に土地を売却し、売却代金を受け取るまでの一般的な手順を8つのステップに沿って説明します。
それぞれの段階で必要な確認事項や手続きを把握しておきましょう。
①遺言書の有無を確認する
まずは、亡くなった方が遺言書を残していないか確認しましょう。遺言書がある場合は、その内容に従って相続を進めます。
ない場合は、法律に基づいて相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。公正証書遺言は公証役場で確認できるため、念のため家の中や金庫もよく探しておきましょう。
②相続人が自分だけかを調査する
遺言がない場合は、誰が相続人かを戸籍で確認する必要があります。自分一人なら手続きは簡単ですが、配偶者や子どもなど複数いる場合は、全員で話し合って遺産を分ける必要があります。
相続人の範囲は法律で決まっており、配偶者のほか、子・親・兄弟姉妹などが該当します。故人の出生から死亡までの戸籍を集めて、見落としがないよう確認しましょう。たとえ相続人が一人でも、それを証明する書類は必要です。
③相続する人と土地の分け方を決める(遺産分割協議)
相続人が2人以上いる場合は、財産をどう分けるかを全員で話し合う「遺産分割協議」が必要です。
話し合いの結果は「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・実印を押します。たとえば「長男が土地を相続し、売却後に代金を兄弟で分ける」と決まれば、その内容を協議書に記載します。全員の同意があれば、協議成立です。
④土地の名義を変更する
遺産分割がまとまったら、土地の名義を相続人に変更する「相続登記」を行います。これを終えないと土地は売却できません。
協議書に沿って、土地を相続する人が法務局に登記申請をします。必要書類は、故人の戸籍、相続人の戸籍・印鑑証明書、協議書、評価証明書などです。
手続きは司法書士への依頼が一般的ですが、自分で行うことも可能です。
⑤不動産会社に相談し、土地の査定や調査を行う
名義変更が終わったら、不動産会社に売却の相談をしましょう。まずは土地の「いくらで売れそうか」を知るために、価格の査定を受けることが大切です。
査定には主に2つの方法があります。
- 仲介業者による査定:不動産会社が買主を探して販売活動を行い、市場価格で売却する方法です。
- 買取業者による査定:不動産会社が直接その土地を買い取る方法です。
査定時には、土地の広さや形状、周辺の利便性、古家の有無、権利関係(例:抵当権や借地権)が確認されます。こうした内容も含め、どの売却方法が自分に合っているかを不動産会社と相談しながら検討しましょう。
⑥土地の売却活動(内覧・価格交渉)を行う
不動産会社と契約を結ぶと、チラシやネット掲載などを通じて買主探しが始まります。希望者が現れると、現地での見学(内覧)が行われ、設備や利用目的などの質問に対応する必要があります。
価格交渉が入ることもあるため、不動産会社と相談しながら調整しましょう。複数の申し込みがあった場合は、内容を比較して一番納得できる相手を選ぶことが大切です。
⑦売買契約を結び、土地を引き渡す
買主が決まったら、不動産売買契約を結びます。契約当日は、契約内容の説明を受けた後、契約書に署名・押印し、手付金(通常5〜10%)を受け取ります。
その後、1〜2ヶ月ほど準備期間を経て、残代金を受け取り、所有権移転登記を行います。土地や必要書類を引き渡せば取引完了です。
最後に、不動産会社へ仲介手数料を支払い、売却手続きが終了します。
⑧税務署に申告して税金を納める(確定申告)
土地を売って利益が出た場合は、翌年の2月16日〜3月15日までに税務署で確定申告を行い、税金を納める必要があります。
必要書類は、申告書、身分証明書、源泉徴収票(給与所得がある場合)、控除証明書などです。
相続税の取得費加算や空き家特例などを利用する場合は、条件を満たしていることを示す書類も併せて提出しましょう。
相続で不動産を売却する場合の税金については「相続した不動産の売却にかかる税金は?控除や特例を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
相続した土地の売却に課税される主な税金の種類
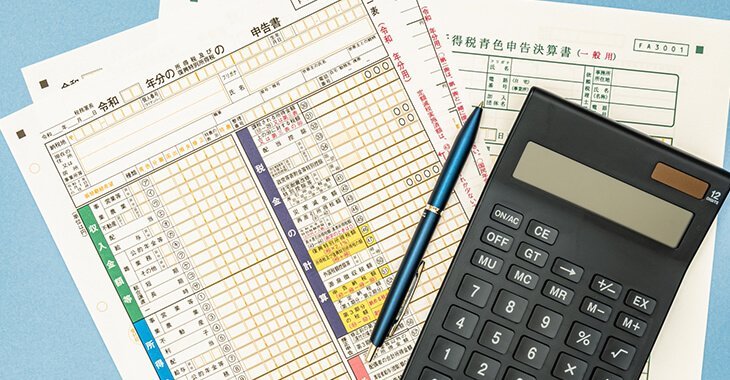
相続で受け継いだ土地を売ると、いくつかの税金がかかることがあります。ここでは、主に課税される税金の種類とポイントを簡単に説明します。
譲渡所得税および住民税・復興特別所得税
相続に限らず不動産を売却して譲渡益が出た場合、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税が課税されます。
これらの税率は、土地をどれくらい長く持っていたかによって変わります。また、復興特別所得税は、所得税額の2.1%分が上乗せされるもので、2037年まで続く予定です。
| 区分 | 所有期間 | 譲渡所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年以上 | 15% | 5% | 0.315% |
土地を相続した場合の税金については「土地の相続税はいくら?評価額の計算方法や控除を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
印紙税
印紙税は、不動産の売買契約書などに対してかかる税金です。契約書には、収入印紙を貼って納めるのがルールとなっています。
税額は、契約書に書かれている売買金額に応じて段階的に決まっており、金額が大きいほど印紙税も高くなります。
| 契約書に記載する売買金額 | 本則 | 軽減税率 |
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 | 対象外 |
| 10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
印紙を貼らずに契約書を作成すると過怠税が課されるため、忘れずに規定額の収入印紙を契約書に貼付・消印しましょう。
登録免許税
登録免許税は、不動産の名義を変更する「登記」をする際に、法務局に納める税金です。
相続によって登記する場合、税額はその土地の固定資産税評価額の0.4%です。ただし、遺言によって法定相続人以外の人が土地を受け取る場合は、税率が2%に上がるので注意が必要です。
土地売却に利用できる特例・控除

相続した土地を売却する際は、一定の条件を満たすことで適用される特例や控除が存在します。ここでは、代表的な2つの制度について、仕組みと主な適用要件を解説します。
相続税の取得費加算の特例
「相続税の取得費加算の特例」とは、相続で支払った相続税の一部を土地の取得費に加えて計算できる制度です。譲渡益(売却益)を少なく見積もることができるため、所得税や住民税の負担を軽減できます。
相続税の取得費加算の特例を適用するための主な要件は、以下の通りです。
- 相続税を支払っていること
- 相続の翌日から3年10カ月以内に売却していること
- 相続人が売却していること
- 売却翌年に確定申告をしていること
上記の要件をすべて満たしている場合に、「相続税の取得費加算の特例」が適用されます。
空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を取り壊して土地を売却した場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
空き家の3,000万円控除を適用するための主な要件は、以下の通りです。
- 相続により家屋と土地を取得していること
- 1981年5月以前に建築された建物であること
- 相続前に被相続人が一人で住んでいたこと
- 相続後も空き家であること
売却前に自治体の「被相続人居住用家屋等確認書」を取得し、確定申告時に提出が必要です。他の特例と併用できないため、早めに税理士などに相談しましょう。
また、この特例は取得費加算の特例等と併用できないため、どの特例を使うのが最も有利か検討することも大切です。
相続登記や税金、わからないことは早めに専門家に確認を
このコラムでは相続した土地を5年以内に売却するかどうかについて、メリットとデメリットを解説しました。
市場価格が高いうちに売れば、維持費の負担を減らせたり、将来のトラブルを防げたりします。一方で、売る時期によっては税率が高くなったり、特例が使えなかったりすることもあります。
相続した土地には思い入れがある場合もあるので、必ずしもすぐ売る必要はありません。ただ、放置すると後々困ることもあるため、早めに状況を整理し、冷静に判断する姿勢が大切です。
このコラムを参考に、ご自身やご家族にとってベストな方法を見つけていきましょう。






