親が亡くなったり、施設に入所したりして、住まなくなった実家をどうするか悩む人は少なくありません。売却を検討していても、「何から始めればいいのか」「誰が手続きできるのか」「税金はかかるのか」など、わからないことが多く、不安を感じやすいものです。この記事では、親の家を売る方法をケース別にわかりやすく解説し、手続きの流れや税金、注意点まで網羅しています。親の家をどうすべきか悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。
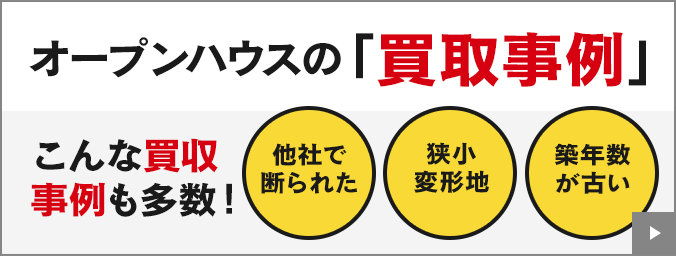
親の家を売ることができる3つのパターン
親の家を売却する際は、「誰が不動産を所有していて、誰が売却手続きを行うのか」によって方法が変わります。
大きく分けると、次の3つのケースが考えられます。
相続した家の名義を変更して家を売る
親が亡くなったあとに家を売る場合は、まず「相続登記」によって名義を自分(相続人)に変更する必要があります。相続登記とは、不動産の所有者を亡くなった親から相続人へ移す手続きのことです。
登記が完了してはじめて、相続人として家を売却できる状態になります。2024年4月からは相続登記が原則義務化されており、怠ると罰則が科される可能性もあるため、余裕を持って手続きを進めておきましょう。
なお、相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要になります。遺産分割協議書を作成し、誰が家を相続するのかを明確にしておきましょう。
相続手続きや相続不動産の売却については「相続した不動産を売却する方法・流れを解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
② 親の代理人となって家を売る
親がまだ存命で、判断能力に問題がない場合は、親本人が売却手続きを行うことが原則です。
体調や事情により親が自ら手続きできない場合は、委任状を作成することで子どもなどが代理人として売却することも可能です。
この場合、売買契約書への署名や登記手続きも代理人が行うことになります。ただし、不動産取引は法律行為のため、委任状には内容や範囲を明記し、印鑑証明書の添付も求められます。
また、後から親の意思が確認できないなどのトラブルを避けるためにも、あらかじめ不動産会社や司法書士と相談して進めるのがおすすめです。
③ 成年後見人制度を利用して家を売る
親が認知症などにより判断能力を失っている場合は、勝手に家を売ることはできません。このような場合に利用されるのが「成年後見人制度」です。
家庭裁判所に申し立てて後見人が選任されると、親の代わりに売却手続きを行うことが可能になります。ただし、売却には別途裁判所の許可が必要なため、自由に進められるわけではありません。
手続きには数ヶ月かかることもあり、また制度利用には家庭状況や親の資産管理に関する審査も行われます。
また親が施設に入所している場合でも、判断能力の有無によって家の売却手続きの進め方が異なります。
売却を円滑に進めるには、早めに制度の利用を検討し、必要な準備を始めることが大切です。
親の家を売る2つの方法(仲介・買取)
親の家を売る方法には、「仲介」と「買取」という2つの選択肢があります。それぞれの特徴を理解して、自分たちの状況に合った売却方法を選ぶことが重要です。
① 仲介業者を通して親の家を売る
仲介とは、不動産会社に依頼して買主を探してもらう方法です。市場に物件を出し、興味を持った人が見つかれば、内覧や交渉を経て契約に進みます。
仲介の最大のメリットは、市場価格に近い金額で売却できる可能性がある点です。そのため、「少しでも高く売りたい」という場合に適しています。ただし、買主が現れるまでの期間は読めないため、売却まで数ヶ月かかるケースも多いです。
また、売却活動の間は内覧対応や価格交渉、契約書類の確認などに手間がかかります。時間に余裕があり、売却金額を重視する場合に適した方法といえるでしょう。
② 買取業者を通して親の家を売る
買取とは、不動産会社が家を直接買い取ってくれる方法です。仲介のように買主を探す必要がないため、査定から契約・現金化までの流れがスピーディーに進みます。
特に、相続税の納税期限が迫っている場合や、遠方に住んでいてすぐに家の管理ができないといったケースでは、早期売却の選択肢として非常に有効です。
一方で、買取価格は仲介よりも相場より低くなりやすい傾向があります。「高く売ること」よりも「早く・確実に売ること」を重視する方向けの方法といえるでしょう。
「仲介業者」と「買取業者」の違いとは?
両者の最大の違いは、「買主を探すか(仲介)」「買主が不動産会社そのものか(買取)」という点です。仲介は時間がかかるものの、市場価格に近い金額で売却できることがあります。一方、買取は売却までのスピードが早い反面、売却価格が低くなる傾向があります。
以下のように使い分けるのが一般的です。
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
| 売却価格 | 市場価格に近くなることが多い | 仲介より低くなる傾向がある |
| 売却までの期間 | 買主が見つかるまで時間がかかることが多い | 査定から契約までが早い |
| 手間 | 内覧対応や価格交渉などが必要 | 基本的に手間は少ない |
| 向いている人 | 少しでも高く売りたい人 | 早く・確実に売りたい人 |
| 家の状態 | 修繕や掃除が必要な場合もある | 現状のままでも買い取ってもらえることが多い |
自分たちの状況に合わせて、「どちらを優先したいか」で選ぶと後悔しにくくなります。
また、迷った場合は両方の査定をとって比較してみるのも一つの手です。
親の家を売るときにかかる税金
親の家を売却する際には、いくつかの税金が関係します。
どんな税金が、いつ・どのように発生するのかを知っておくことで、余計な出費や申告漏れを防ぐことにつながります。
ここでは、代表的な5つの税金について、概要を押さえておきましょう。
相続税
親が亡くなって不動産を相続した場合、その時点で相続税がかかる可能性があります。相続税は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であればかかりません。
遺産の総額や相続人の人数によって異なるため、まずは対象になるかどうかを確認しましょう。
相続時にかかる税金については「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
相続税の申告期限は「相続の開始を知った日から10か月以内」と決まっており、売却の前に申告を求められる場合もあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
譲渡所得税・住民税
親の家を売ったときに利益(譲渡所得)が出た場合、金額に対して譲渡所得税と住民税が課税されます。譲渡所得は「売却価格 −(取得費+諸経費)」で計算され、所有期間によって税率が変わります。
- 5年超の所有:長期譲渡所得(税率約20%)
- 5年以下の所有:短期譲渡所得(税率約39%)
相続した家を売る場合は、親が購入したときの取得費を引き継ぐため、利益が出やすくなるため、税額が高くなることもあります。
相続した土地を3年以内に売却したときについては「相続した土地は3年以内に売却すべき?税金・控除を詳しく解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
登録免許税
所有権を移転する際に発生するのが登録免許税です。これは不動産登記にかかる税金で、売却時には買主が負担するのが一般的ですが、相続登記の際には相続人が支払います。
税額は、固定資産税評価額の0.4%が目安となります。
また、相続登記は2024年から原則義務化されており、放置すると過料が科されることもあるため、早めに対応をしましょう。
印紙税
不動産の売買契約書を作成する際には、印紙税がかかります。税額は契約金額によって異なり、たとえば1,000万円を超え5,000万円以下であれば、印紙税は1万円となります。印紙は契約書に貼り付け、消印をして納税します。
通常は売主と買主のどちらが負担するかをあらかじめ取り決めますが、実際には、売主側が負担するケースが多く見られます。
特別復興所得税
譲渡所得税に付随して課税されるのが、特別復興所得税です。これは東日本大震災の復興財源として設けられた税金で、2037年までの期間限定で課税されます。
税額は「所得税額 × 2.1%」で計算され、譲渡所得税と一緒に納めることになります。
確定申告時に自動的に加算されるため、申告漏れのないよう注意しましょう。
親の家を売る手続きをケース別に解説
親の家を売るときは、親が亡くなっているのか、まだ存命なのか、または認知症などで判断が難しいのかによって、手続きの流れが異なります。
ここでは3つの代表的なケースと、すべてに共通する基本的な手続きを順に解説します。
すべてのケースに共通する手続きの流れ
状況ごとの違いはあっても、基本的な流れはおおむね共通しています。
- 所有者(売主)を確定させる
- 不動産会社に査定を依頼する
- 売却方法を決定し、契約を結ぶ(仲介 or 買取)
- 必要書類をそろえ、売買契約を締結
- 代金受領・登記・引き渡しを行い、売却完了
書類やスケジュールはケースによって異なるため、早めに専門家へ相談して全体の流れを把握しておくと安心です。
家の処分については「家の処分を検討している人必見!最適な方法と手順を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
相続した家を売る場合の流れ
親が亡くなり、家を相続したあとに売却する場合は、まず相続登記(名義変更)を行う必要があります。手続きが済んでいなければ、法的に売却することはできません。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、「誰が家を相続して売却するか」を合意し、内容を協議書にまとめます。その後は不動産会社に査定を依頼しながら名義変更などの手続きを進めていきます。名義変更や相続登記の手続は不動産会社がサポートしてくれる事が多いため、相談してみましょう。
なお、相続税の申告や納税が必要な場合は、申告期限(10か月以内)も考慮しながら、計画的に進めることが大切です。
一人っ子が相続したときについては「一人っ子の相続におけるメリット・デメリットとは?手続きの流れや注意点も解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
親の代理人として家を売る場合の流れ
親が存命で、判断能力がしっかりしている場合は、親本人が売主になります。ただし、高齢や体調の都合などで手続きを本人が行うことが難しい場合は、子どもなどが代理人として売却することも可能です。
この場合、親から正式な「委任状」を作成してもらい、印鑑証明書を添付したうえで、手続きを進めていきます。委任の範囲や内容を明記し、不動産会社にも事前に共有しておくことでトラブルを防げます。
代理人による売却は、あくまでも親の意思に基づいて行われるものなので、確認や合意の経緯は記録に残しておくと安心です。
成年後見制度を利用して家を売る場合の流れ
親が認知症などにより判断能力を失っている場合、たとえ子どもであっても勝手に家を売ることはできません。このような場合は、家庭裁判所に申し立てをして「成年後見人」を選任してもらい、売却手続きは、後見人が行うことになります。
さらに、後見人が不動産を売る際には、裁判所の許可が必要です。売却理由や金額が適切かどうかも審査されるため、書類の準備や手続きには数ヶ月かかることもあります。
時間と手間はかかりますが、本人の財産を守るために設けられた、大切な制度といえます。
親の家を売るときの注意点
親の家を売却する際は、法律・税金・家族間の関係など、さまざまな面で注意が必要です。思わぬトラブルを防ぐためにも、次のようなポイントをあらかじめ確認しておきましょう。
共有名義の家は相続人全員の同意が必要
親の家を複数の相続人で共有している場合、売却には全員の同意が必要です。1人でも反対する相続人がいれば、売却はできません。
共有名義のまま放置していると、話し合いが難航したり、将来的にさらに相続が発生して名義人が増えたりと、売却がますます困難になります。相続人同士で早めに話し合い、売却に向けた合意を得ておくことが大切です。
名義変更(相続登記)を済ませてから家を売る
親が亡くなった後に家を売る場合、名義変更(相続登記)を完了していなければ売却できません。所有者が親のままでは、不動産の売却そのものが成立しないためです。
相続登記には遺産分割協議書や戸籍などの書類が必要で、場合によっては手続きに時間がかかることもあります。また、2024年からは相続登記が義務化されており、放置していると過料が科される可能性もあります。
売却を検討する段階で名義を確認し、必要な手続きを早めに始めましょう。
各種特例や控除の適用条件を確認する
親の家を売ったときに税金がかかる場合でも、条件を満たせば各種の控除や特例を利用できる可能性があります。
代表的な制度として、次のようなものがあります。
- 相続した空き家を売却する際の「3,000万円特別控除」
- 長期所有の不動産に対する軽減税率
- 被相続人の居住用財産の譲渡特例
ただし、これらの制度には申告期限や売却時期などの細かな条件があり、知らずにいると適用できないまま終わってしまうこともあります。
利用できる制度を事前に整理し、売却前に専門家に相談しておくと安心です。
親の家を売ることに関するよくある質問
親の家を売る場面では、よくある手続きや税金の疑問に直面することがあります。
ここでは特に多くの人が気になる2つのポイントについてQ&A形式で解説します
① 親の家を売る際は確定申告は必要ですか?
はい、売却によって譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要になります。譲渡所得とは、売却額から取得費や諸経費を差し引いた利益のことを指します。利益が出なければ申告不要なケースもありますが、特別控除などを適用する場合でも確定申告が必要です。
たとえば、「3,000万円の特別控除」や「被相続人の居住用財産の譲渡特例」などの制度を使いたい場合、申告をしないと適用されません。
申告の時期は、売却した翌年の2月16日~3月15日が一般的です。金額が大きくなるケースもあるため、早めの準備がおすすめです。
② 親が生きているうちに家を売ることはできますか?
はい、親が判断能力を保っていれば、家を売ることは可能です。名義が親のままでも、本人が売却に同意できる場合は、通常の手続きで進めることが可能です。
ただし、親の体調や年齢によっては手続きが難しい場合もあり、その際は子どもが代理人となって売却を進める方法(委任状の作成など)が選ばれることもあります。
一方で、認知症などで意思確認ができない場合は、成年後見制度の利用が必要です。親が元気なうちに、売却の意思やタイミングを家族で共有しておくと、あとから慌てずに済みます。
状況に合わせて、最適な売却を目指そう
親の家を売るには、相続・代理・成年後見など、状況に応じた手続きが求められます。
さらに、仲介と買取といった売却方法の違いや、関係する税金、注意点についても理解しておくことが欠かせません。
この記事を参考に、ご自身のケースに合った進め方や事前準備を確認しておくことで、トラブルや後悔を防ぐことができます。
不安な点があれば、不動産会社や専門家に相談しながら、安心して親の家の売却を進めていきましょう。






