親から土地を相続したものの、「今すぐ売るべきか」「しばらく様子を見るべきか」と悩む方は少なくありません。相続税の支払いや維持費、不動産市況など、タイミングの判断にはさまざまな要素が関係します。売り時を逃して損をすることもあるため、あらかじめ考慮すべきポイントを把握しておくことが大切です。この記事では、売却の判断基準や注意点、事前にやるべき準備についてわかりやすく解説します。
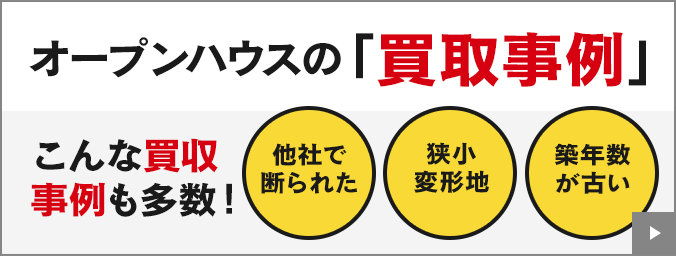
相続した土地はいつ売るべき?判断すべき4つのタイミング
相続した土地を「いつ売るか」は、売却後の損益を大きく左右する重要な判断です。タイミングによっては高く売れることもあれば、税金や管理コストで結果的に損をしてしまう場合もあります。
ここでは、売却の是非を検討するうえで意識しておきたい4つのタイミングをご紹介します。
土地の活用予定がなく、維持費や管理負担が増しているとき
相続した土地に活用の予定がない場合は、早めの売却を検討するのも一つの選択肢です。所有しているだけでも固定資産税がかかるほか、草刈りや境界管理など維持の手間と費用がかかります。放置すれば、近隣トラブルや行政指導につながることもあるため注意が必要です。
とくに遠方に住んでいると管理が難しくなりやすく、空き地の状態が悪化すると売却価格に影響を及ぼすこともあります。「いつか使うかも」と思い続けるよりも、活用の見込みがないなら現金化してリスクを手放す判断も有効です。
相続税の納付期限が迫っているとき
相続税の納付期限は、被相続人が亡くなった日から10か月以内と定められています。現金や預貯金で納税が難しい場合、相続した土地を売却して資金を確保するケースも多く見られます。
ただし、買い手がすぐに見つかるとは限らず、売却活動や契約手続きには一定の時間がかかります。期限が迫ってから動き出しても、納税に間に合わないおそれがあります。相続税の負担が見込まれる場合は、できるだけ早い段階で不動産会社へ相談し、売却を選択肢に入れておくと安心です。
取得費加算の特例や空き家控除の期限が近づいているとき
相続した土地を売却する際は、税制上の特例や控除の「適用期限」にも注意が必要です。
たとえば、「取得費加算の特例」は、相続税の一部を取得費に加算できる制度ですが、相続開始から3年10か月以内の売却が条件です。また、「相続空き家の3,000万円特別控除」も、期限内の売却や建物の状態など、細かい要件があります。
これらを知らずに期限を過ぎると、数百万円単位の税負担が発生することもあるため要注意です。
特例の内容や適用条件は複雑なので、売却を検討する段階で確認し、「使えるうちに売る」判断が損を防ぐことにつながります。
不動産市況が上向いているとき
不動産市場の動向は、売却価格に大きく影響します。 周辺で開発が進んでいたり、地価が上昇傾向にあるときは需要が高まり、高値での売却が期待できます。
ただし、相場がいつまでも上がり続けるとは限らず、景気やエリアの需要次第では急落することもあります。 「もっと高く売れるかも」と様子を見ていた結果、タイミングを逃してしまうケースも少なくありません。
市況が良好で買い手のニーズが見込めるなら、前向きに売却を検討するのが得策です。 まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、相場を把握して判断材料をそろえましょう。
売却前にしておきたい準備と確認事項
相続した土地を売るには、「タイミング」だけでなく「準備」も欠かせません。 名義変更が済んでいない、相続人の合意が取れていないといった手続きの不備は、売却の遅れやトラブルの原因になります。
ここでは、スムーズな売却に向けて確認しておきたい、4つの基本的な準備を解説します。
相続不動産の売却については「相続した不動産を売却する方法・流れを解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
相続登記を済ませて名義を自分に変更しておく
相続した土地を売却するには、まず相続登記によって名義を自分に変更する必要があります。所有者が亡くなった親のままでは、法的に売却手続きは進められません。
2024年4月から相続登記は原則義務化されており、正当な理由なく放置すると過料が科される可能性もあります。名義変更には遺産分割協議書や戸籍などの書類が必要になり、準備に時間がかかる点にも注意が必要です。
売却を考えているなら、法務局または司法書士に相談し、登記の状況を確認しておきましょう。
家の相続については「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
不動産査定で土地の価値を把握しておく
相続した土地を売却する前に、どれくらいの価格で売れるかを把握しておくことが大切です。 土地の価値は、立地や広さ、用途地域、接道状況などの条件によって大きく変わります。
近隣の相場だけに頼らず、不動産会社に査定を依頼し、実際の売却価格の目安を確認しておくとよいでしょう。 複数の会社に見積もりを依頼すれば、価格差が出たときの根拠も比較しやすくなります。
将来的に売却を検討している段階でも、相場を知っておくことは「今売るかどうか」の判断材料になります。
売却時のトラブルを防ぐため、相続人全員の同意を取っておく
相続した土地に複数の相続人がいる場合は、売却にあたって全員の同意が必要です。 代表者として手続きを進めたくても、他の相続人が合意していなければ売買契約は成立しません。
特に、遺産分割協議が済んでいない状態で売却を進めると、のちにトラブルへ発展するリスクがあります。「売却の可否」や「代金の分配」をめぐって意見が対立するケースも珍しくありません。
こうしたトラブルを防ぐためには、遺産分割協議書を作成し、誰が土地を相続し、誰が代表して売却するのかを明確にしておくことが重要です。必要に応じて、司法書士や税理士など専門家のサポートを受けながら進めましょう。
土地の境界確定を済ませておく
相続した土地をスムーズに売却するには、境界が明確であることが欠かせません。隣地との境界があいまいな状態では、買主が不安を感じて売却が進みにくくなる可能性があります。
特に、古い土地や一度も測量をしていない土地では、登記上の面積と実際の面積にずれがあることもあります。境界を確定するためには、土地家屋調査士による現地調査に加えて、隣接地の所有者との立ち会いが必要です。
作業には時間がかかることもあるため、売却を検討し始めた段階で動くのがおすすめです。あらかじめ境界を確定しておけば、売却後のトラブルも未然に防ぐことができます。
相続した土地を売るときにかかる主な税金
相続した土地を売却する際には、「相続時」と「売却時」で異なる税金がかかる可能性があります。それぞれに申告や納税が必要になるケースもあるため、全体の流れと負担の目安を事前に把握しておくことが重要です。
ここでは、相続・売却に関係する主な税金について、代表的な種類とポイントを整理してご紹介します。
相続税
相続税は、亡くなった人の財産を引き継いだときにかかる税金です。
土地を含む財産の合計額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、課税対象になります。土地の評価額に応じて税額が決まり、申告と納付の期限は「相続開始を知った日から10か月以内」です。
相続時の税金については「土地の相続税はいくら?評価額の計算方法や控除を解説」や「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
譲渡所得税・住民税
相続した土地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、「譲渡所得税」と「住民税」がかかります。 譲渡所得は「売却価格 −(取得費+諸経費)」で計算され、金額に応じて課税される仕組みです。
税率は所有期間によって異なり、相続の場合は被相続人が土地を取得した時点から年数を引き継ぎます。
- 所有期間5年超:長期譲渡所得(約20%)
- 所有期間5年以下:短期譲渡所得(約39%)
相続による売却は多くが長期譲渡に該当しますが、取得費や特例の有無によって納税額は大きく変わることがあります。売却前に簡単な試算を行い、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
相続不動産の売却に関わる税金については「相続した不動産の売却にかかる税金は?控除や特例を解説」や「相続した土地を売却するには税金がかかる!計算方法と減額方法を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記時に発生する税金で、相続した土地の名義変更を行う際に必要です。 税額は「固定資産税評価額 × 0.4%」で計算され、たとえば評価額が1,000万円なら4万円が課税されます。
登録免許税は、登記申請時に法務局へ支払う必要があり、名義変更の完了には欠かせない費用となります。売却そのものに直接関係する税ではありませんが、名義変更を済ませなければ売却は進められません。
必要経費として見込んでおくと、手続きをスムーズに進めやすくなります。
印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約書を作成する際に発生する税金です。契約金額に応じて収入印紙を購入し、契約書に貼り付けて消印することで納付します。
たとえば、契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、印紙税は1万円が目安です。
負担者は売主・買主の間で取り決めるのが一般的で、どちらかが全額を負担するケースもあれば、折半する場合もあります。契約書を2通作成する場合は、それぞれに印紙が必要となるため、事前に確認しておきましょう。
復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源を確保する目的で導入された税金です。所得税額に対して2.1%が上乗せされるしくみとなっており、たとえば譲渡所得税が100万円の場合、復興特別所得税は2万1,000円、合計で102万1,000円が課税されます。
制度は2037年まで継続され、確定申告時に自動で加算されるため、個別の申告は不要です。ただし、譲渡所得税が発生する売却では、あわせて復興特別所得税の分も見込んでおく必要があります。
売却に使える控除や特例の活用方法
相続した土地を売却する際には、条件を満たすことで税負担を大きく抑えられる特例があります。とくに「3,000万円特別控除」や「取得費加算の特例」は、譲渡所得を減らす効果が大きく、納税額に直結します。
ただし、これらの制度には期限や細かな要件があり、内容を理解して早めに申告準備を進めておくことが重要です。ここでは、代表的な控除や特例について紹介します。
相続した土地の特別控除や確定申告については「国税庁の制度をもとに解説!相続した土地の売却にかかる税金と特別控除とは?」や「相続した土地を売却したら確定申告が必要?手順や注意点まで解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
居住用財産の3,000万円特別控除
「居住用財産の3,000万円特別控除」は、自宅を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度です。相続後にその家に一定期間住んでいた場合に、適用が認められるケースがあります。
ただし、空き家のまま売却した場合は対象外となることが多いため、事前の確認が欠かせません。また、他の特例と併用できないこともあるため、確定申告前に制度内容を整理し、どの控除が最も有利かを検討しておきましょう。
相続空き家の3,000万円特別控除
被相続人が一人で暮らしていた空き家を、一定の条件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。対象となる主な条件は、旧耐震基準で建てられた住宅であること、取り壊しや耐震改修を行っていること、そして相続開始から3年以内に売却することなどです。
相続空き家の特別控除を受けるには確定申告が必要なため、制度の内容を確認し、必要書類などの準備を進めましょう。
10年超の居住財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
相続した土地が「10年以上所有された居住用財産」に該当する場合、譲渡所得の税率が軽減される特例があります。6,000万円以下の部分は14.21%に軽減され、売却益が大きいときほど効果的です。
ただし、「3,000万円特別控除」との併用はできないため、どちらが有利かを比較して判断しましょう。
相続した土地を売る際の失敗事例と成功事例
相続した土地の売却では、「売る時期」や「準備の仕方」によって結果が大きく変わることがあります。損をした例や特例を活用して有利に売却できた例などを把握しておくと、今後の判断に役立つでしょう。
ここでは、よくある失敗と成功の事例を取り上げていきます。
タイミングを逃して土地の価値が下がった事例
郊外の土地を「もっと高く売れるはず」と保有し続けた結果、地域の人口減や施設撤退の影響で地価が下落。最終的には、当初より数百万円安い価格で手放すことになりました。
不動産は必ずしも値上がりするとは限らないため、市場動向や地域の将来性をふまえた見極めが欠かせません。
相続人同士の連携不足で売却が長引いた事例
兄弟で土地を相続したものの、話し合いを後回しにしていたことで、一部の相続人が転居し、連絡が取れなくなってしまいました。その結果、遺産分割協議がまとまらず、売却も長期間停滞することに。
不動産の売却には相続人全員の合意が必要なため、方針を共有し、意思疎通をはかることがトラブル防止のポイントになります。
特例を知らずに税金を多く支払うことになった事例
空き家特例や取得費加算の特例を知らず、適用できたはずの控除が申告されずに、数十万円の税負担が増えたケースがあります。これらの特例は申告しなければ使えないため、知らないままでは損をすることに。
不安がある場合は、事前に専門家へ相談するのがおすすめです。
売却せずに土地を活用して得をした事例
売却せずに相続した土地を駐車場や資材置き場として貸し出し、継続的な収入を得ているケースもあります。特に市街地や駅近であれば賃貸需要も高く、有効な選択肢となり得ます。
市況の上昇を待って高値で売却できた事例
再開発やインフラ整備の予定をふまえて数年売却を待った結果、地価が上昇し当初より高値で売れた例もあります。新駅開業や大型施設の建設が控えたエリアでは、土地需要が高まりやすく、情報収集と判断のタイミングが成功につながります。
相続した土地を売るときのよくある質問
相続した土地をどう扱うかは、多くの人にとって初めての経験です。売却のタイミングや税金、手続きに関して不安や疑問を感じる方も少なくありません。
ここでは、よくある質問の中から特に多いものを取り上げ、わかりやすく回答していきます。
相続した土地の売却を待っても良い場合とは?
すぐに売却せず、状況を見極めるのが適切なケースもあります。たとえば、再開発による地価上昇の見込みがある、資金面に余裕がある、活用方法を検討中、登記などの整理が未完了といった場合です。
ただし、特例や控除には適用期限があるため、税制上の条件はあらかじめ確認しておきましょう。
売却益が出なかった場合も確定申告は必要ですか?
利益が出なかった場合でも、「空き家の3,000万円特別控除」や「取得費加算の特例」などを使うなら確定申告が必要です。申告しなければ控除が適用されず、結果的に税負担が発生するおそれもあります。
控除を使わず譲渡所得もない場合は申告が不要となるケースもあるため、不安なときは税務署や税理士に確認しましょう。
相続した土地を売るタイミングは状況に応じて見極めを
相続した土地を売るタイミングは、税金や特例の期限、市況、自身の生活設計などをふまえて判断することが大切です。「とりあえず保有」は思わぬ損失を招くこともある一方で、待つことで高値売却につながる場合もあります。
大切なのは、売却を急ぐかどうかではなく、自分たちの状況に合った選択ができているかどうかです。
迷ったときは、不動産会社や税理士と相談しながら進めると安心です。






