相続した土地を売却する際は、税金や控除制度の理解が欠かせません。特に、国税庁が定める各種制度を確認し、正しく適用することで、予期しない税負担を避けることができます。この記事では、売却に関わる税金の種類や特別控除について解説しています。内容は国税庁の公式サイトを参考にしています。
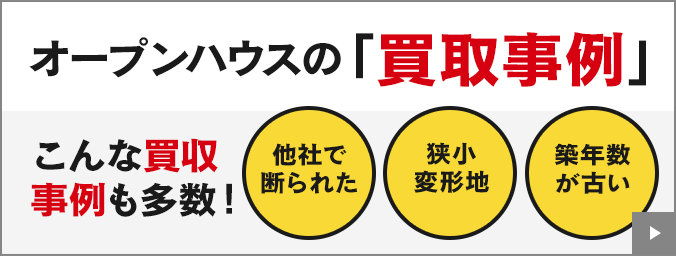
相続した土地を売却すると発生する税金の種類
相続した土地を売却する際には、いくつかの税金が発生します。主な税金には、譲渡所得税や住民税、印紙税などがあります。それぞれの税金について理解しておくことが、納税額を適切に把握するために重要です。
ここでは、売却時に発生する税金の種類について簡潔に説明します。
土地相続時の税金については「土地の相続税はいくら?評価額の計算方法や控除を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
譲渡所得税
相続した土地を売却した際、最も重要な税金は「譲渡所得税」です。譲渡所得税は、売却価格から取得費用や諸経費を差し引いた金額に対して課税されます。
相続した土地の場合、被相続人が取得した時点から所有期間が計算され、税率は長期譲渡と短期譲渡で異なります。長期譲渡に該当すれば税率は約20%、短期譲渡なら約39%の税率が適用されるため、売却時期や譲渡所得の計算が重要となります。
復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災の復興支援のために導入された税金です。譲渡所得税に対して2.1%が加算され、相続した土地を売却した場合、譲渡所得税額に基づいて課税されます。
たとえば、譲渡所得税が100万円であれば、復興特別所得税は2万1,000円となります。この税金は、譲渡所得税を納める際に一緒に支払うことになりますので、売却を決める際には合わせて見積もりをしておくことが重要です。
登録免許税
登録免許税は、相続した土地の名義変更に必要な費用です。土地の売却前に、相続登記を行う必要がありますが、その際にかかる税金が登録免許税です。
税額は、土地の固定資産税評価額に0.4%を掛けた金額で計算されます。例えば、評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円となります。
登記完了のためには必ず支払う必要があり、売却前に準備しておくべき重要な費用です。
住民税
相続した土地を売却した際、譲渡所得に対して住民税が課税されます。住民税は、譲渡所得の金額に基づき計算され、税率は通常5%です。譲渡所得税が所得税と住民税に分かれるため、住民税も必ず把握しておくことが重要です。
特に、売却後に発生する納税額をしっかりと理解しておくことで、適切な納税を行うことができます。
印紙税
不動産を売却する際には、売買契約書に印紙税が課されることがあります。印紙税は契約金額に応じて変動し、契約金額が1,000万円を超える場合に発生します。
印紙税の金額は、契約金額に基づいて決まるため、売却金額が高額になるほど納税額も増加します。売買契約書に適切な印紙を貼付し、消印を行うことが法的に定められています。
相続した土地の売却時にかかる税金の計算方法
土地を売却する際にかかる税金は、「いくら支払うのか」を正確に計算することが重要です。譲渡所得や所有期間によって税率が異なるほか、取得費の把握や経費の計上なども納税額に影響します。
ここでは、税金を計算するうえで押さえておきたい基本項目を解説します。
相続した土地や不動産の売却に関わる税金については「相続した不動産の売却にかかる税金は?控除や特例を解説」や「相続した土地を売却するには税金がかかる!計算方法と減額方法を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
譲渡所得税の計算方法
相続した土地を売却して得た利益には、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算される仕組みです。
取得費には、被相続人の購入価格や登記費用などが含まれ、譲渡費用には仲介手数料や測量費などが該当します。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を目安に算出されることが一般的です。
税率と税金額の算出方法
譲渡所得に対する税率は、土地の所有期間によって異なります。
被相続人の取得日から、土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」となり、税率は所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%の合計約20.315%です。5年以下なら「短期譲渡所得」となり、合計で約39.63%が課税されます。
所有期間の確認が重要です。
税金計算に影響する要素
譲渡所得税の額は、売却価格・取得費・譲渡費用だけでなく、適用できる特例や控除の有無にも大きく左右されます。
たとえば「取得費加算の特例」や「空き家の3,000万円控除」を使えば、課税対象額が大きく減少します。また、取得費が不明な場合には概算で計算されるため、正確な資料の保管が重要です。
相続した土地の売却時に使える特別控除の種類と条件
相続した土地を売却する際、一定の条件を満たせば税負担を軽減できる特別控除が適用されることがあります。これらの制度はそれぞれ適用期限や要件が異なるため、内容を把握しておくことが大切です。
ここでは、主に活用されている3つの特別控除制度について、基本的な仕組みと注意点をわかりやすく解説します。
取得費加算の特例
取得費加算の特例は、相続税を支払った場合に、その一部を譲渡時の取得費に加算できる制度です。これにより譲渡所得が少なくなり、結果として課税額も軽減されます。
適用には「相続開始から3年10か月以内の売却」が条件となります。また、相続税全額が対象になるわけではなく、売却する土地に対応する相続税額に限られます。
参考:国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続空き家に関する3,000万円特別控除
被相続人が一人で住んでいた住宅を相続し、一定の条件で売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
対象は旧耐震基準の建物で、取り壊しか耐震改修を行い、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。適用には確定申告が必要です。
参考:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
低未利用土地の100万円控除
相続などで取得した一定の低未利用土地を譲渡する際、条件を満たせば最大100万円の所得控除が受けられる制度です。都市部から離れた活用予定のない土地が対象で、売却価格が500万円以下であることなどの条件があります。
申請には市区町村からの証明書の取得と確定申告が必要です。土地の処分を後回しにしていた方にとって、税負担の軽減につながる可能性があります。
参考:国税庁|No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
相続した不動産の売却後の確定申告方法
相続した土地を売却し、譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。たとえ特別控除の適用によって課税額がゼロになったとしても、申告しなければ控除は受けられません。
確定申告の期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
申告には、譲渡契約書、取得費や諸経費の領収書、特別控除の適用に必要な証明書類などが必要です。電子申告(e-Tax)にも対応しており、自宅から手続きすることも可能です。
相続した土地を売却した際の確定申告については「相続した土地を売却したら確定申告が必要?手順や注意点まで解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
売却のタイミングによる税負担の違い
相続した土地を「いつ売るか」によって、税金の負担が大きく変わることがあります。特別控除の適用期限や、譲渡所得税の税率はタイミングによって変動するため、早めの判断が将来的な負担を左右するポイントになります。
ここでは、売却時期による税金の違いについてわかりやすく解説します。
相続した土地を売るタイミングについては「相続した土地を売るタイミングはいつがベスト?判断基準と注意点を徹底解説」や「相続した土地を5年以内に売却するメリット・デメリットとは?税金・特例・注意点を徹底解説!」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
相続開始から3年以内に売却するメリットとは?
相続した土地を相続開始から3年以内に売却すると、「取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円特別控除」などの税制優遇を受けられる可能性があります。
これらの特例は、適用期限を過ぎると利用できないため、税負担を軽減するには売却時期の見極めが重要です。制度の詳細は国税庁の公式サイトでも確認できます。
参考:国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
参考:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
所有期間によって異なる税率の仕組み
土地を売却した際の譲渡所得税は、所有期間によって税率が異なります。
相続による取得の場合、被相続人の取得日を引き継ぐため、多くは「5年超」として長期譲渡扱いとなり、税率は約20%です。5年以下の場合は短期譲渡となり、税率は約39%に上がります。売却前に取得時期を確認しておくことで、想定外の税負担を防げます。
相続した土地を売却する流れ
土地を相続したあと、すぐに売却を進めたい場合でも、いくつかの手続きや準備が必要です。相続登記や必要書類の準備、不動産会社とのやり取りなど、段階的に進めることでスムーズに売却が可能になります。
ここでは売却完了までの基本的な流れを解説します。
相続不動産の売却については「相続した不動産を売却する方法・流れを解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
相続登記から売却までの基本的な流れ
まずは、土地を誰が相続するかを決めるために遺産分割協議を行い、その内容をもとに相続登記を進めます。登記が完了すると、法的に名義人となり、売却活動が可能になります。
その後、不動産会社に査定を依頼し、媒介契約または買取を選んで売却を進めます。手続きは順番を守って進めることが重要です。
必要書類と手続きの詳細
土地の売却には、相続登記に必要な戸籍謄本や遺産分割協議書、固定資産評価証明書などの準備が欠かせません。売却時には登記識別情報、本人確認書類、売買契約書なども必要です。
書類が不足すると手続きが滞るため、事前に確認し、確実に揃えておくことが大切です。
不動産会社とのやり取りと契約
相続した土地をスムーズに現金化したい場合は、不動産会社による「買取」が現実的な選択肢です。買主を探す手間が不要で、手続きも短期間で完了しやすいため、早期売却を希望する方に向いています。
一方で、時間に余裕がある場合は「仲介」で買主を募る方法もあります。希望条件やスケジュールに応じて、不動産会社と相談しながら最適な売却方法を選びましょう。
相続した土地を売却する際の注意点
相続した土地の売却には、税金や特例以外にも気をつけておきたい実務的なポイントがあります。名義の問題や権利関係が整理されていないと、手続きがスムーズに進まず、売却の機会を逃すおそれもあります。
ここでは、売却前に確認すべき重要な注意点を解説します。
相続登記が完了していないと売却できない?
相続した土地を売却するには、まず名義を自分に変更する「相続登記」が必要です。
2024年4月から相続登記は義務化されており、怠ると過料の対象になることもあります。売却を検討する前に、必ず名義変更を済ませておきましょう。
家の相続については「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
共有名義の土地は相続人全員の同意が必要?
相続人が複数いる場合、土地の名義は共有状態になります。このような共有名義の土地を売却するには、原則として相続人全員の同意が必要です。1人でも同意しない相続人がいると、売却手続きは進められません。
売却を検討する前に、遺産分割協議を行い、誰が土地を相続し、どのように処分するかを話し合っておくことが重要です。
特例の適用条件と期限に注意する
相続した土地を売却する際、特例や控除を活用すれば税負担を軽減できる可能性があります。しかし、これらの制度には細かな適用条件や期限が設定されています。
たとえば、「取得費加算の特例」は相続開始から3年10か月以内の売却が条件です。期限を過ぎると適用できなくなるため、制度の概要を確認し、売却スケジュールと照らし合わせて計画を立てることが大切です。
相続した土地を売却する際によくある質問
相続した土地を売却しようと考えたとき、「価格はどう決まるのか」「売るタイミングはいつがいいのか」など、多くの疑問が生まれます。ここでは、実際によく寄せられる代表的な質問に絞って、基本的な考え方を解説します。
土地の売却価格はどうやって決まるのですか?
土地の売却価格は、不動産会社による査定をもとに決定されます。査定では、立地条件や面積、周辺の取引事例、道路との接道状況などが主な評価項目となります。
また、市場の需要や地価動向も反映されるため、タイミングによって価格に差が出ることもあります。
仲介で売却する場合は、売主の希望価格をふまえて販売価格を設定し、購入希望者との交渉を経て成約価格が決まります。一方、不動産買取では、不動産会社が直接買い取る価格を提示するため、スピードを重視したい場合に適しています。
相続した土地を売るタイミングはいつが良いですか?
相続した土地を売るベストなタイミングは、納税や特例の期限、不動産市場の状況をふまえて判断する必要があります。
たとえば、「取得費加算の特例」は相続開始から3年10か月以内、「相続空き家の3,000万円特別控除」は3年以内の売却が条件です。また、不動産市場が上昇傾向にあるときは高値での売却が期待できる一方で、市況の下落リスクもあるため慎重な見極めが必要です。
税制や市場動向、相続人の事情を総合的に判断することが大切です。
特別控除以外に利用できる制度にはどんなものがある?
相続した土地の売却にあたっては、特別控除のほかにも税負担を軽減できる制度があります。
たとえば、「長期譲渡所得の軽減税率」は、所有期間が10年を超える居住用財産の売却に適用される可能性があります(ただし、特別控除との併用不可)。また、「小規模宅地等の特例」は、相続時の土地評価額を最大80%減額できる制度ですが、売却後の譲渡所得には直接影響しない点に注意が必要です。
制度によって適用条件や対象範囲が異なるため、あらかじめ税理士や専門家に相談しながら確認することをおすすめします。
参考:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
売却の前に確認を!国税庁制度と控除の活用を忘れずに!
相続した土地を売却する際は、思いついたタイミングですぐに行動を起こすのではなく、まずは国税庁が案内している制度や控除内容をしっかりと確認しておくことが重要です。
特に「取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円特別控除」などは、一定の条件や期限があるため、知らずに売却を進めてしまうと適用できないことがあります。また、土地の状況や相続の経緯によっては、制度の対象外になることもあるため、事前に売却シミュレーションを行い、税負担や控除額の目安を把握しておくと安心です。
売却後に「申告し忘れて控除が受けられなかった」といった事態を避けるためにも、売却を検討し始めた段階で、国税庁の公式サイトや税理士など信頼できる専門家のサポートを活用しましょう。






