親が認知症になり、財産管理が難しくなると、不動産の売却を検討するケースが増えます。しかし、認知症の状態では契約の有効性に影響するため、適切な手続きが必要です。認知症の親の不動産を売却するには、意思能力があるうちに売却する方法と、成年後見制度を利用して売却する方法の2つの選択肢があります。この記事では、認知症の親が所有する不動産を売却する方法について、具体的な手順や注意点を詳しく解説します。成年後見制度の仕組みや、早めに取るべき対策についても紹介するので、ぜひ最後までご確認ください。
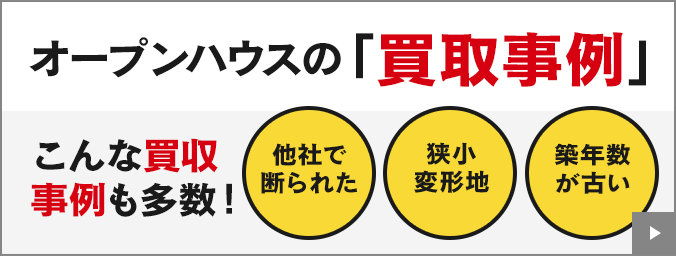
認知症の親が所有する不動産は売買できる?判断基準と法律のポイント
認知症の親が所有する不動産を売却するには、売買契約が法律的に有効かどうかを確認するのが重要です。契約の有効性は、親の意思能力が判断基準となります。
法律上、意思能力が認められれば、親が単独で不動産を売却することは可能です。しかし、認知症の進行によっては、契約の意味を正しく理解できないケースもあり、後に契約が無効と判断されるリスクがあります。
また、売却後に親族や第三者が「契約当時に本人の意思能力がなかった」と異議を申し立てた場合、裁判で契約が取り消される可能性があります。そのため、売却を進める際は、慎重な対応が必要です。
認知症の症状が進行している場合、親が単独で不動産を売却するのは難しくなります。このようなケースでは、「成年後見制度」を利用して売却する方法が一般的です。成年後見制度を活用することで、後見人が親の代わりに売却手続きができます。
親が亡くなった後の不動産処分については「親の死後、相続した家が売れない原因とは?対策や放置するリスクも解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください
認知症の親の不動産売買をスムーズに進めるために知っておきたい注意点
認知症の親の不動産を売却する際は、できるだけスムーズに手続きを進める工夫が必要です。売却のタイミングが遅れると、成年後見制度が必要になり、手続きが複雑化する可能性があります。
意思能力があるうちに手続きを進める
意思能力があれば、不動産の売却は問題なく行えます。意思能力があるうちに売却手続きを進めれば、成年後見制度を利用せずに売却が可能です。成年後見制度を利用すると、家庭裁判所の許可が必要となり、自由に売却できなくなります。
また、売却の際には、契約の適正性を証明できるようにしておくことも重要です。たとえば、売買契約の際に司法書士や弁護士の立ち会いを依頼し、契約が適正に行われたことを記録しておけば、後のトラブルを防ぎやすくなります。
スムーズに進めるためには、親の意思能力を確認し、できるだけ早く手続きを開始することが大切です。
成年後見制度で認知症の親の不動産売買をする手順
認知症の症状が進行し、意思能力が認められない場合は、成年後見制度を利用することで不動産の売却が可能です。成年後見人が親の代わりに手続きを進めることで、契約が有効になり、法的トラブルを防げます。
ここでは、成年後見制度を利用して不動産を売却する具体的な手順を解説します。
Step 1. 医師に診断書を書いてもらう
成年後見制度の申立てには、親の認知症の状態を証明する医師の診断書が必要です。診断書には意思能力や認知機能の状態が記載され、家庭裁判所の判断資料となります。
診断書は成年後見制度専用の書式で作成する必要があります。書式は家庭裁判所の公式サイトからダウンロードできるため、事前に確認しておきましょう。
Step 2. 必要書類を集める
家庭裁判所への申し立てには、複数の書類が必要です。代表的なものは次のとおりです。
- 申立書(家庭裁判所指定の書式を使用)
- 親の戸籍謄本
- 住民票(後見人候補者のものも含む)
- 親の財産を証明する書類(登記簿謄本、固定資産税の納税通知書など)
- 診断書(Step1で準備したもの)
書類に不備があると審査が長引くため、事前に家庭裁判所の窓口で確認しましょう。
Step 3. 家庭裁判所へ申し立てをする
必要書類が揃ったら、親の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見開始の申し立てを行います。申し立て後、家庭裁判所の審理を経て、成年後見制度の適用が判断されます。
自分で申し立てを行うことも可能ですが、手続きが複雑なため、弁護士や司法書士に依頼するケースも多くあります。専門家に依頼するとスムーズに進められる反面、費用がかかる点に注意が必要です。弁護士や司法書士に依頼すると、10万円以上かかることもあります。
審理では、裁判官や調査官が親の認知症の状態や財産管理の必要性、後見人の適格性を審査します。審理には数カ月かかるのが一般的です。
Step 4. 後見の登記が完了する
家庭裁判所が成年後見人を選任すると、その内容が法務局に登記されます。登記が完了すると、成年後見人の権限が正式に認められ、不動産売却などの手続きを進められます。
登記完了後、登記事項証明書を取得でき、不動産売買の手続きに活用できます。
Step 5. 成年後見人を通して不動産売買をする
成年後見人が選任された後は、不動産売却の手続きを進めることができます。成年後見人には財産を管理する権限があり、売買契約の締結や名義変更なども行えるため、スムーズに手続きを進めることが可能です。
成年後見制度を利用した場合の注意点
成年後見制度を利用すれば、認知症の親の不動産を法的に問題なく売却できます。しかし、手続きには手間がかかるうえ、売却には家庭裁判所の審査があったりと、自由に進められません。
ここでは、成年後見制度を利用する際に注意すべき点を解説します
手続きには時間がかかる
成年後見制度の申し立てから後見人が選任され、不動産を正式に売却できるようになるまでには、数カ月以上かかるのが一般的です。
申し立てには必要書類を準備し、家庭裁判所に提出する必要があります。その後、裁判所の審理を経て後見人が選任されるまでに、平均3~4カ月かかるといわれています。また、不動産売却には家庭裁判所の審査が必要なため、売却を急ぐ場合には適しません。
そのため、売却の可能性があるなら意思能力がある段階で、早いうちから売却を進めましょう。
不動産の売買には家庭裁判所の許可が必要
成年後見制度を利用して不動産を売却する際、後見人が勝手に売却を進めることはできず、家庭裁判所の許可が必要です。
裁判所の審査では、次の点が確認されます。
| 売却の必要性 | 親の生活費確保や施設入居費用の支払いなど、正当な理由があるか |
| 売却価格の妥当性 | 市場価格と比較して適正な価格であり、不当でないか |
| 売却後の資金管理 | 売却で得た資金が親の生活費や医療費など、適切な目的に使われるか |
これらの審査を通過しなければ、売却は認められません。そのため、裁判所に提出する書類として不動産の査定書や売買契約書の案を用意し、売却の正当性を証明する必要があります。
また、裁判所の許可が下りるまでに1カ月程度かかるのが一般的です。不動産の売却をスムーズに進めるためには、事前に査定を行い、必要な資料を準備しておきましょう。
成年後見制度では、法的に問題なく不動産を売却できますが、家庭裁判所の審査を受ける必要があります。
認知症になる前にできる対策
認知症が進行すると、本人が自分の財産を管理するのが難しくなり、不動産の売却も自由に行えなくなります。そのため、認知症を発症する前に適切な準備が必要です。
ここでは、事前にできる主な対策として「任意後見制度」「家族信託」「生前贈与」の3つの方法を紹介します。
任意後見制度を利用する
任意後見制度とは、判断能力があるうちに、信頼できる人(任意後見人)に財産管理を委任する制度です。本人が認知症になり、意思能力を失ったときに、家庭裁判所の監督のもとで任意後見人が財産管理や不動産の売却を行えます。
任意後見制度のメリットは、成年後見制度と異なり、後見人を自由に選べることです。信頼できる後見人を指定すれば、認知症発症後もスムーズに不動産売却や資産管理ができます。
ただし、任意後見契約を結んでも、すぐに効力が発生するわけではありません。判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで契約が発効します。そのため、契約後すぐに資産管理を任せることはできません。
家族信託を利用する
家族信託とは、本人が元気なうちに不動産などの資産を家族に託し、財産管理を任せる仕組みです。例えば、親が所有する不動産を子どもに信託すれば、親が認知症になった後も子どもが財産管理や売却を行えます。
最大のメリットは、成年後見制度のように家庭裁判所の関与がなく、契約の範囲内でスムーズに資産管理や売却できることです。例えば、親が賃貸物件を所有している場合、家族信託を利用すれば認知症発症後も家族が賃貸経営を継続できます。
家族信託の主な流れは次のとおりです。
- 信託契約を結ぶ(親が委託者となり、子どもが受託者となる)
- 不動産の名義を受託者に変更
- 親が認知症になった後も、受託者が財産管理や売却を実施できる
ただし、家族信託を利用する場合、信託契約の作成に専門的な知識が必要になります。信託契約の内容を慎重に決めるために、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
生前贈与を利用する
生前贈与とは、親が元気なうちに不動産を子どもや家族に譲渡する方法です。認知症になる前に名義を変更しておけば、将来、本人が意思能力を失っても家族が自由に売却や管理を行えます。
また、生前贈与を活用すれば、相続税の負担を軽減できる場合があります。「贈与税の配偶者控除」や「相続時精算課税制度」などの特例を利用することで、贈与税を抑えながら財産を移転することが可能です。
ただし、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。不動産の評価額によっては高額な税負担が生じることもあるため、税理士に相談しましょう。
認知症が進行すると、不動産売却が難しくなり、成年後見制度が必要になります。事前に対策を講じることで、スムーズな資産管理が可能になります。
適切な方法を選ぶために、法律や税の専門家に相談し、準備を進めましょう。
家の相続の内容については「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」や「相続した家を売るには?手続き・税金・売却方法までわかりやすく解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
認知症の親の不動産売買で起こりやすいトラブル事例
認知症の親の不動産売却には、契約無効や家族間のトラブルなど、さまざまなリスクがあります。ここでは、よくあるトラブル事例を紹介します。
売却契約を結んだが、登記ができず契約無効に
認知症の親の代わりに家族が売却契約を進めたものの、登記手続きの際に親の意思能力がないと判断され、契約が成立せず、買主とのトラブルに発展するケースがあります。
こうした事態を防ぐためには、契約前に親の意思能力を医師に確認してもらい、診断書を取得しておきましょう。もし意思能力が不十分と判断された場合は、成年後見制度を利用し、適法な手続きを踏んで売却を進める必要があります。
売却後の資金管理で家族間トラブルに
不動産を売却した後、売却代金の管理をめぐって家族内で対立が起こることもあります。本来は親の介護費用や生活費に充てるつもりだったものの、別の家族が「自分の取り分がある」と主張し、資金の使い道を巡ってトラブルになる場合があります。
こうした問題を避けるためには、売却前に資金の使い道を明確にし、成年後見制度や家族信託を活用して管理方法を決めておくことが重要です。
親の家を売却する際の内容については「【完全ガイド】親の家を売る方法とは?後悔しないための準備・流れ・税金まで徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
認知症の親の不動産売買に関するよくある質問
認知症の親の不動産売却では、契約の有効性や手続きについて多くの疑問があります。特に、診断後の売却可否や代理人の手続きが可能かどうかは、多くの人が気にするポイントです。
ここでは、よくある質問について分かりやすく解説します。
認知症の親名義の不動産は売却できますか?
親に意思能力があれば、不動産を売却できます。しかし、意思能力が低下すると、本人が単独で売却することはできません。
この場合、成年後見制度を利用すれば、家庭裁判所の審査を得た上で売却可能です。ただし、手続きには時間がかかるため、事前の準備が大切です。
認知症の診断書があると不動産売買契約は無効になりますか?
認知症の診断書があるからといって、すべての売買契約が無効になるわけではありません。契約の有効性は、契約時点の本人の意思能力の状態によって判断されます。
売却を進める際には、契約時の本人の意思能力を証明できるよう、医師の診断書や専門家の立ち会いを活用するのが望ましいです。
認知症の親の代わりに委任状で不動産売買は可能ですか?
認知症の親の代わりに家族が委任状を作成し、不動産を売却することはできません。
委任契約は、親に意思能力がある場合にのみ成立するため、認知症が進行すると委任状による売却は無効になります。
認知症の親の不動産売買は司法書士に相談すべきですか?
認知症の親の不動産売却を検討する際、司法書士に相談することで手続きをスムーズに進められるケースが多いです。司法書士は、不動産登記の専門家であり、成年後見制度の申請手続きや、不動産売却時の登記変更などのサポートが可能です。
ただし、成年後見制度の利用や財産管理に関する総合的なアドバイスを求める場合は、弁護士や税理士と併せて相談するとより安心です。
司法書士は、登記関連の手続きを中心にサポートしてくれるため、不動産売却に関する法律的な不安がある場合は、相談することをおすすめします。
認知症の親の不動産売買は早めの対策をしよう!
認知症の親が所有する不動産をスムーズに売却できるかどうかは、意思能力の有無によって大きく変わります。認知症が進行すると、成年後見制度を利用しなければならず、売却には手間と時間がかかるため注意が必要です。
そのため、任意後見契約や家族信託、生前贈与といった事前対策を活用し、認知症後も適切に不動産を管理・売却できるように備えておくことが重要です。
「今はまだ大丈夫」と先延ばしにせず、計画的に準備を進め、最適な方法を選びましょう。






