相続した土地を売却するには、登録免許税や印紙税など様々な税金がかかります。それだけに「土地を売りたいけど、思ったより利益がでなかったり、むしろマイナスにならないかが心配」と悩む方は少なくありません。 そこで本記事では、相続した土地を売却した時にかかる税金について、まずは計算方法を解説します。そのうえで、使える特別控除や税金を抑える方法もわかりやすく解説します。
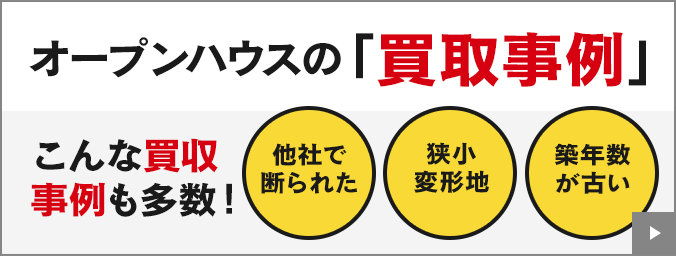
相続した不動産を売却するときにかかる税金の種類
相続した不動産を売却する際には、様々な税金がかかります。これらの税金について正しく理解しておくことは、不動産売却をスムーズに進める上で非常に重要です。ここでは、相続した不動産を売却する際にかかる主な税金の種類について解説します。
譲渡所得税とは
譲渡所得税は、不動産を売却した際に得た利益 (譲渡所得) に対して課税される税金です。この税金は、不動産の所有期間によって税率が異なり、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。
| 区分 | 所有期間 | 税率(所得税+復興特別所得税+住民税) | 税率 |
|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 売却した年の1月1日 時点で所有期間が5 年超 | 20.315%(所得税 15.315%+住民税 5%) | 20.315%(所得税 15.315%+住民税 5%) |
| 短期譲渡所得 | 売却した年の1月1日 時点で所有期間が5 年以下 | 39.63%(所得税 30.63%+住民税%9 ) | 39.63%(所得税 30.63%+住民税9% ) |
不動産の所有期間が長いほど、税率が低くなるため、売却のタイミングを検討する際には、この点を考慮することが重要です。
譲渡所得税は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得税額 = 譲渡所得 × 税率
譲渡所得の計算方法については、後ほど詳しく解説します。
住民税とは
住民税は、都道府県民税と市町村民税(東京23区の場合は特別区民税)を合わせた税金で、個人の所得に応じて課税されます。不動産を売却した場合、その譲渡所得に対して住民税が課税されます。譲渡所得に対する住民税率は、所得の種類(長期譲渡所得または短期譲渡所得)によって異なります。
復興特別所得税とは
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興を目的として、2013年から2037年までの期間に限り、所得税に上乗せして課税される税金です。不動産の譲渡所得に対しても、所得税と合わせて復興特別所得税が課税されます。税率は、所得税額に対して2.1%です。
税金は、不動産売却によって得た利益から算出されるため、売却を検討する際には、税金がどれくらいかかるのかを事前に把握しておくことが大切です。税金の計算方法や税金を抑える方法については、後ほど詳しく解説します。
相続した不動産を売却する際には、解説した税金以外にも登録免許税や印紙税などの費用がかかる場合があります。費用については事前に確認しておくことをおすすめします。
加えて、売却後は登記手続きが必要です。不動産の所有者を証明する権利証(登記済証)については「権利証(登記済証)とは?登記識別情報との違い・取り扱いの注意点を解説」で解説しています。
また、不動産には抵当権が設定されている場合があります。抵当権については「抵当権とは?初心者向けにわかりやすく解説!手続き・メリット・デメリットまで」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益に対して課税される税金です。税額を正しく計算するためには、以下のステップに従って計算を行う必要があります。
Step1.取得費とは
取得費とは、不動産を取得するためにかかった費用の合計額です。具体的には、以下のものが含まれます。
- 購入代金
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
- 仲介手数料
- その他、不動産を取得するために直接かかった費用
これらの費用を合計したものが、取得費となります。ただし、建物の取得費については、減価償却費を差し引く必要があります。減価償却費は、建物の耐用年数に応じて、毎年一定額を費用として計上するものです。減価償却費の計算方法は、建物の種類や構造によって異なります。
取得費が不明な場合は、概算取得費として、売却価格の5%を取得費とすることができます。ただし、概算取得費は、実際の取得費よりも少なくなることが多いため、可能な限り、実際の取得費を調べて計算することをおすすめします。
Step2.譲渡費用とは
譲渡費用とは、不動産を売却するためにかかった費用の合計額です。具体的には、以下のものが含まれます。
- 仲介手数料
- 印紙税(売買契約書に貼付するもの)
- 測量費用
- 建物の解体費用
- その他、不動産を売却するために直接かかった費用
これらの費用を合計したものが、譲渡費用となります。譲渡費用は、譲渡所得から差し引くことができるため、税額を抑える効果があります。領収書などの証拠書類を保管しておきましょう。
Step3.譲渡所得とは
譲渡所得とは、不動産の売却によって得た利益のことです。譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得 = 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
譲渡価額とは、不動産の売却価格のことです。取得費と譲渡費用を差し引いたものが、譲渡所得となります。譲渡所得がプラスであれば、譲渡所得税が課税されます。マイナスであれば、譲渡所得税は課税されません。
Step4.譲渡所得税額の計算
譲渡所得税額は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得税額 = 譲渡所得 × 税率
税率は、不動産の所有期間によって異なります。所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。税率は、以下のとおりです。
- 長期譲渡所得:20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
- 短期譲渡所得:39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
例えば、譲渡所得が3,000万円で、所有期間が5年を超える場合、譲渡所得税額は以下のようになります。
3,000万円×20.315% = 609万4,500円
譲渡所得税額は、非常に高額になる場合があります。そのため、税金を抑えるための対策を講じることが重要です。次に、相続不動産の売却時に使える特例と控除について解説します。
相続不動産の売却時に使える特例と控除
相続した不動産を売却する際には、一定の要件を満たすことで、税金の負担を軽減できる特例や控除が利用できます。適用要件を知っておくことで、手取り額を増やすことが可能です。ここでは、主な特例と控除について解説します。
居住用財産の3,000万円特別控除の特例
住んでいる家を売却した際に、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。この特例は、居住者の住み替えを支援し、税負担を軽減することを目的としています。適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- ご自身が住んでいる家であること
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 親子や夫婦など特別な関係のある人に対して売ったものではないこと
- 売った年の前年、前々年にこの特例の適用を受けていないこと
- この特例の適用を受けることについて、確定申告書に記載して税務署長に提出すること
要件を満たすことで、譲渡所得から3,000万円を限度として控除することができます。この特例を活用することで、マイホームの売却に伴う税負担を軽減することが可能です。
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
相続税を納めた相続人が、相続によって取得した財産を一定期間内に売却した場合、納めた相続税額のうち、一定金額を取得費に加算できる特例です。この特例は、相続税を負担した相続人の税負担を軽減するために設けられました。適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続または遺贈により財産を取得した者であること
- 当該財産を、相続開始の日の翌日から3年10ヶ月以内に売却すること
取得費に加算できる金額は、以下の計算式で算出されます。
取得費に加算できる金額 = 相続税額 × (譲渡した財産の価額 ÷ 相続財産の価額)
例えば、相続税額が1,000万円で、譲渡した財産の価額が2,000万円、相続財産の価額が5,000万円の場合、取得費に加算できる金額は以下のようになります。
1,000万円×(2,000万円÷5,000万円) = 400万円
この特例を利用することで、譲渡所得を減らし、税負担を軽減することができます。
出典:国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
空き家の3,000万円特別控除の特例
被相続人が住んでいた家屋(空き家)を相続し、一定の要件を満たした場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。この特例は、空き家の有効活用を促進するために設けられました。適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続開始の直前において、被相続人が当該家屋に居住していたこと
- 当該家屋が、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものであること
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
これらの要件を満たすことで、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。例えば、譲渡所得が4,000万円の場合、3,000万円を控除することで、課税対象となる譲渡所得は1,000万円となります。この特例を利用することで、税負担を大幅に軽減することが可能です。
出典:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
不動産の売却にかかる税金を抑える方法
不動産を売却する際には、税金が大きな負担となることがあります。ここでは、不動産の売却にかかる税金を抑えるための具体的な方法について解説します。
取得費が不明な場合の概算取得費
不動産の取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費として計算することができます。これを概算取得費といいます。ただし、概算取得費は、実際の取得費よりも少なくなることが多いため、税負担が増える可能性があります。可能な限り、過去の売買契約書や領収書などを探して、実際の取得費を把握するように努めましょう。
居住用財産の買換え特例
居住用財産を売却して、新たに居住用財産を購入した場合、一定の要件を満たすことで、譲渡益に対する課税を繰り延べることができます。これを居住用財産の買換え特例といいます。この特例は、住み替えを促進するために設けられました。適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 売却した不動産が、居住用財産であること
- 売却代金が、新たに購入する居住用財産の購入代金以下であること
- 売却した年の翌年末までに、新たに居住用財産を購入し、居住すること
これらの要件を満たすことで、譲渡益に対する課税を繰り延べることができます。ただし、課税が繰り延べられるだけで、税金が免除されるわけではありません。将来、新たに購入した居住用財産を売却するさいに、繰り延べられた税金が課税されます。
売ってもマイナスになるときは損益通算をする
不動産を売却した結果、譲渡損失が発生した場合、その損失を他の所得と相殺することができます。これを損益通算といいます。
損益通算をすることで、所得税や住民税の負担を軽減することができます。ただし、損益通算ができるのは、譲渡損失が発生した年から3年間です。3年以内に他の所得が発生しない場合は、損益通算の効果を得ることができません。
譲渡費用や取得費用は全て計上する
譲渡所得を計算する際には、譲渡費用や取得費用を全て計上することが重要です。これらの費用を計上することで、譲渡所得を減らし、税負担を軽減することができます。
譲渡費用や取得費用には、仲介手数料、印紙税、測量費用、建物の解体費用などが含まれます。これらの費用の領収書や契約書などを保管しておき、確定申告のさいに忘れずに計上するようにしましょう。
税率が下がる5年超や10年超のタイミングで売る
不動産の譲渡所得税率は、所有期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得の税率は、短期譲渡所得の税率よりも低いため、可能な限り、所有期間が5年を超えるタイミングで売却することをおすすめします。
また、10年を超えて居住していた居住用財産を売却する場合には、軽減税率の特例が適用される場合があります。この特例を利用することで、税負担をさらに軽減することができます。
これらの方法を実践することで、不動産の売却にかかる税負担を軽減することができます。
よくある質問
相続した不動産の売却に関しては、様々な疑問や不安が生じることがあります。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。これらの質問と回答を参考に、疑問や不安を解消し、安心して不動産売却を進めてください。
相続不動産を売却したら確定申告は必要?
はい、相続した不動産を売却した場合、原則として確定申告が必要です。確定申告では、譲渡所得を計算し、譲渡所得税を納める必要があります。
相続放棄した不動産は売却できない?
原則として、相続放棄した不動産は売却できません。相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切相続しないことを選択する手続きです。相続放棄をした場合、その相続人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
したがって、相続放棄をした不動産を売却する権利はありません。ただし、相続放棄をした後でも、一定の要件を満たすことで、不動産を管理する義務が残る場合があります。
相続した不動産を売りたいときはどこに相談すればいい?
相続した不動産を売りたい場合は、以下の専門家に相談することができます。
- 不動産会社: 不動産の査定、売却活動、売買契約の手続きなどを依頼することができます。
- 税理士:譲渡所得税の計算、確定申告の手続きなどを依頼することができます。
- 弁護士・司法書士 相続に関する法的な問題、遺産分割協議、名義変更の手続きなどを依頼することができます。
これらの専門家に相談することで、不動産売却に関する様々な問題を解決することができます。ご自身の状況に合わせて、最適な専門家を選び、相談するようにしましょう。
また、家の相続については「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
これらの質問以外にも、相続した不動産の売却に関しては、様々な疑問や不安が生じることがあります。そのような場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、安心して不動産売却を進めることができます。
まとめ
この記事では、相続した不動産の売却にかかる税金について解説しました。以下に、この記事のポイントをまとめます。
- 相続した不動産を売却する際には、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税がかかる
- 譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が異なる
- 相続不動産の売却時には、居住用財産 (空き家)の売却特例や、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例などが利用できる
- 不動産の売却にかかる税金を抑えるためには、取得費や譲渡費用を全て計上する、税率が下がるタイミングで売るなどの方法がある
- 相続不動産を売却した場合は、確定申告が必要
- 相続放棄した不動産は、原則として売却できない
- 相続した不動産を売りたい場合は、不動産会社、税理士、弁護士・司法書士などに相談することができる
相続した不動産の売却は、税金や手続きが複雑で、不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、この記事を参考に、税金について理解を深め、適切な対策を講じることで、安心して不動産売却を進めることができます。
もし、税金や手続きについて疑問や不安がある場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをおすすめします。
オープンハウスでは、不動産の買取も行っておりますので、売却にお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。






