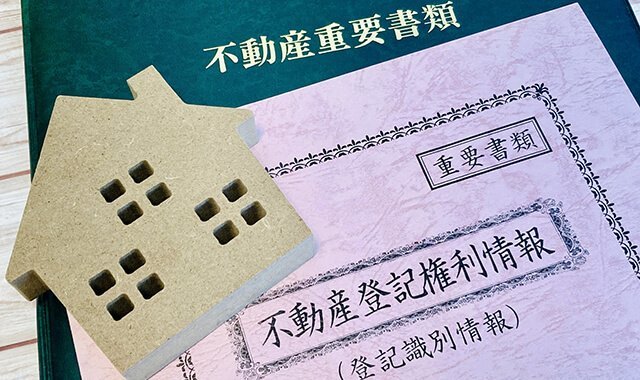家や土地を売買・相続・贈与したときに必要になるのが、「所有権移転登記」です。この登記を行わないと、自分が正式な所有者であることを第三者に証明できず、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。この記事では、所有権移転登記の意味や必要性、かかる費用、手続きの流れ、そしてケースごとの注意点までを、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説します。
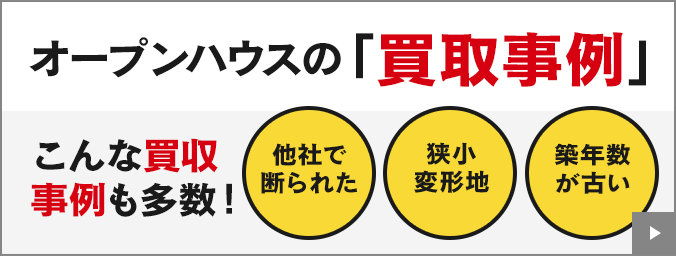
所有権移転登記とは?わかりやすく解説

所有権移転登記とは、土地や建物などの不動産の「持ち主(所有者)が変わったこと」を公的に記録する手続きのことです。たとえば、不動産を売買したときや相続・贈与を受けたときなどに、新しい所有者として登録する必要があります。
日本の民法第177条では、「不動産の所有権は登記しなければ第三者に対抗できない」と定められています。つまり、登記をしていないと、第三者に対して自分の権利を主張することができません。
国土交通省の調査によると、不動産の取引総額は年間で数十兆円にもなるといわれています。こうした中で、所有権を正確に記録し、管理することは安心・安全な取引のために非常に大切です。
所有権保存登記との違い
所有権保存登記とは、建物が新たに建てられたときや、登記簿にまだ所有者の名前が記載されていない不動産に対して、初めて所有者として名義を登録する際に行う手続きです。たとえば、新築の一戸建てや新築マンションを購入したときに必要になります。
これに対して、所有権移転登記は、すでに誰かの名義になっている不動産を売買・相続・贈与などで取得する際に必要となります。
具体的には、以下のような場面で違いが生じます。
- 所有権移転登記:中古の家を購入したとき
- 所有権保存登記:新築の建売住宅で、まだ誰の名義にもなっていないとき
このように、名前は似ていても、登記の対象となる不動産や行うタイミングが異なります。それぞれの登記の違いを正しく理解し、ご自身の状況に合った手続きを進めましょう。
所有権移転登記はどのタイミングで行う?

所有権移転登記は、「いつ手続きを行うか」によって、後々のトラブルを防げるかどうかが大きく左右されます。特に売買や相続、贈与、離婚による財産分与など、不動産の取得理由によって申請のタイミングや注意点が異なるため、正しい知識を持っておくことが大切です。
ここからは、それぞれのケースごとに登記を行うべきタイミングや実務上のポイントについて詳しく見ていきましょう。
不動産を売却・購入するとき
不動産の売買では、残りの代金の支払い(決済)と物件の引き渡しを同じ日に行うことが多く、そのタイミングで所有権移転登記も一緒に行います。
このとき、司法書士が手続きに立ち会い、売主・買主の本人確認書類や印鑑証明書、権利証(または登記識別情報)などを確認して進めます。
不動産を相続するとき
相続による登記(相続登記)は、2024年4月1日から義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わなければなりません。
この登記は相続放棄の手続きとは別で、たとえば相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印と印鑑証明書を添えて申請します。
相続登記をせずに放置すると、次の世代に相続が発生したときに関係者が増えて手続きが難航し、不動産を売ったり担保にしたりすることができなくなる可能性があるため、早めの対応が大切です。
家の相続については「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
不動産を贈与されたとき
不動産を贈与された場合も、すみやかに所有権移転登記を行う必要があります。
贈与には贈与税や登録免許税がかかりますが、特に注意したいのは、登記をしないと「もらった不動産」が他人から見て自分のものと認められないという点です。たとえば、登記前に旧所有者に差押えなどが起こると、不動産が守れなくなるリスクがあります。
贈与契約書や必要な書類を準備し、できるだけ早く法務局で手続きを進めましょう。
離婚で不動産を分与するとき
離婚時の財産分与で不動産を譲り受けた場合も、名義変更の登記は早めに行うことが大切です。
実際には、住宅ローンが残っているケースも多く、金融機関との相談が必要になる場合があります。たとえばローン名義を変更したり、新たなローンを組み直したりする必要があるかもしれません。
法律上、財産分与の請求期限は離婚から2年以内ですが、不動産の登記には明確な期限はありません。そのため、登記がされないまま放置されるケースもあります。
ただし、旧配偶者の名義のままだと、ローン滞納による差押えなどの問題が起こる可能性もあるため、離婚協議書を作成する段階で不動産の登記についてもしっかり話し合っておくと安心です。
所有権移転登記をしないとどうなる?考えられるリスクを解説

不動産の所有者が変わったにもかかわらず所有権移転登記を行わずに放置していると、大きなトラブルにつながる可能性があります。
まず一番大きなリスクは、第三者に対して「自分が所有者だ」と主張できなくなることです。たとえば同じ不動産を別の人に二重で売却されてしまった場合でも、先に登記をした人が正式な所有者とみなされるのが原則です。実際の裁判でも、「登記を先にした側の所有権が認められた」例があります。
また、登記をしていないと前の所有者が勝手に抵当権(借金の担保)を設定することもできてしまいます。その結果、ローンを滞納されてしまうと、あなたが取得したはずの不動産が競売にかけられるといった事態に巻き込まれる可能性もあるのです。
さらに、相続登記は2024年(令和6年)4月から義務化されており、登記を3年以内に行わないと10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性もあります。
こうしたリスクを回避するためにも、不動産の名義が変わるタイミングでは、できるだけ早く所有権移転登記を行うことがとても重要です。
抵当権については「抵当権とは?初心者向けにわかりやすく解説!手続き・メリット・デメリットまで」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
所有権移転登記は自分でできる?具体的な手続きの流れを解説

不動産の所有者が変わったときに行う「所有権移転登記」は、法律上、自分で手続きすることが可能です。自分で申請すれば、司法書士に依頼する際にかかる報酬を節約できるというメリットがあります。
ここでは、所有権移転登記の基本的な流れを、初心者にもわかりやすくステップごとにご紹介します。
①登記事項証明書を取得し、不動産の情報を確認する
登記事項証明書は、「登記簿謄本」とも呼ばれ、不動産の所在地や地番、面積、そして現行の所有者情報が記載された公的書類です。
この証明書を確認せずに登記を進めると、住所や名前を間違えて記載してしまい、訂正(補正)手続きが必要になることがあるので注意が必要です。
登記事項証明書は、法務局の窓口またはインターネットで取得できます。発行手数料は1通600円(令和5年時点)です。
②必要書類を準備する(事前準備)
所有権移転登記には、次のような書類が必要になります。
- 印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 住民票
- 固定資産評価証明書(市区町村で取得)
- 不動産の権利証(または登記識別情報)
このほか、手続きの理由によって追加書類が変わります。
- 相続の場合:戸籍謄本・遺産分割協議書など
- 贈与の場合:贈与契約書など
また、不動産が複数ある場合は、物件ごとに個別に書類が必要になるケースもあります。なお、権利証を紛失している場合は、本人確認書類などを使って別の手続きを取る必要があり、より複雑になることがあります。
③登記申請書を作成する
登記申請書には、次のような項目を正確に記入します。
- 登記の目的(例:所有権移転)
- 原因と日付(例:令和◯年◯月◯日 売買)
- 登記義務者(売主など)
- 登記権利者(買主など)
法務局のウェブサイトには記入例も掲載されているため、参考にしながら進めましょう。
④登録免許税を計算し、納付する
登記には「登録免許税」という税金がかかります。金額は以下のように、不動産の評価額に対して決まる割合です。
- 売買や贈与:評価額の2%(※軽減税率が適用される場合あり)
- 相続:評価額の0.4%
たとえば、3,000万円の土地を購入した場合、登録免許税は60万円になります(税率2%時)。
税金は「収入印紙」で納め、登記申請書に貼り付けて提出します。土地と建物の評価額をそれぞれ足し合わせて計算するため、固定資産評価証明書の内容をもとに正確に計算しましょう。
⑤管轄の法務局に登記申請を行う
必要な書類がそろったら、不動産がある場所を管轄する法務局へ申請書類を提出します。申請方法には以下の2つがあります。
- 窓口での提出:担当者にその場で確認してもらえるので安心
- 郵送での提出:遠方の場合などに便利(返信用封筒の同封が必要)
審査にはおおよそ1週間程度かかりますが、混雑している時期や書類に不備があると、さらに時間がかかることがあります。
⑥法務局による審査を受ける
法務局では、登記官が書類をチェックし、問題がないか確認します。内容に不備や不明点があると、「補正」と呼ばれる修正の手続きを求められます。
国土交通省の調査によると、個人で登記申請を行った方の約20%が補正を経験しているというデータもあります。最近はオンライン申請の制度も整ってきましたが、初めての方は法務局の窓口で説明を受けながら手続きするほうが安心でしょう。
⑦登記完了証と登記識別情報通知書を受け取る
登記が無事に完了すると、次の2つの書類が交付されます。
- 登記完了証
- 登記識別情報通知書
「登記識別情報通知書」は、以前の「権利証」に代わるもので、12桁の英数字が書かれたとても重要な書類です。万が一これが他人に知られると、不正に登記されるリスクもあるため、厳重に保管しましょう。
受け取りは窓口または郵送で行われ、郵送の場合は本人限定受取郵便で届くことが多いです。紛失や情報漏えいがあると、将来的な売却や名義変更の際に支障が出るため、細心の注意が必要です。
登記手続きは専門性が高く、少しのミスでもやり直しやトラブルにつながりかねません。大切な財産に関わる手続きだからこそ、基本的にはご自身で行うよりも、登記の専門家である司法書士に依頼するのが安心です。
所有権移転登記を行うために必要な書類とは

ここでは、不動産の名義を変更する「所有権移転登記」を行う際に必要となる書類について解説します。これらの書類は、主に市役所や法務局で取得できますが、平日の窓口対応が基本のため、事前にスケジュールを立てておくことが大切です。
また、有効期限がある書類も多く、二度手間にならないように順序よく準備を進めましょう。
本人確認書類
本人確認書類としては、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的な証明書が一般的です。
これらは、法務局での審査や「登記識別情報通知書(新しい権利証)」を受け取る際に提示を求められることがあります。原本の提示が必要になるため、コピーではなく必ず現物を持参しましょう。
もし高齢者などで顔写真付きの証明書がない場合は、健康保険証と補助書類を組み合わせて対応できるケースもあります。また、代理人が登記関係の書類を受け取る際には、委任状の提出が必要になるため、あらかじめ法務局に確認しておくと安心です。
印鑑証明書・実印
不動産の売主(または譲渡者)には、実印とその印鑑証明書の提出が求められます。これは、「確かに本人が同意している」ということを公的に証明するためのものです。
印鑑証明書は、市区町村の役所で発行されます。発行から3か月以内のものが有効です。買主(新しい所有者)は必ずしも提出が必要なわけではありませんが、住宅ローンを利用する場合などには金融機関から求められることがあります。
実際の不動産取引では、売主・買主の双方が実印と印鑑証明書を提出することが一般的です。
登記済権利証または登記識別情報
不動産の現在の所有者が持っている「登記済権利証」または「登記識別情報通知書」も、名義変更の際に必ず必要な書類です。
- 「登記済権利証」は、昔の紙の権利証です(主に2005年以前の登記で交付)。
- 「登記識別情報通知書」は、それに代わる書類で、12桁の英数字が記載された大切な通知書です。
これらは、その不動産を所有している証拠として機能します。もし紛失してしまった場合は、「事前通知」や「本人確認情報の提供」などの別の手続きが必要になり、時間も手間もかかるため注意が必要です。
登記済権利証については「権利証(登記済証)とは?登記識別情報との違い・取り扱いの注意点を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書とは、市区町村が不動産の価値を評価した金額を証明する書類で、所有権移転登記の際に納める「登録免許税」を計算するために必要になります。評価額が高いほど税額も大きくなるため、登記にかかる費用を見積もる上で欠かせない資料です。
この証明書は、市区町村の役所で発行してもらうことができ、発行手数料は数百円程度が一般的です。使用するのは原則として最新年度のものとなるため、取得時期にも注意が必要です。
なお、一部の自治体ではオンライン申請が可能ですが、まだ多くの地域では役所の窓口での手続きが必要です。申請から受け取りまでに日数がかかることもあるため、登記のスケジュールに支障が出ないよう、早めに準備を始めることをおすすめします。
住民票の写し
住民票の写しは、新たに不動産の名義人となる人の現住所を確認するために必要となる書類です。登記簿にはこの住民票の情報が反映されるため、住所や氏名に誤りがあると後の手続きに影響が出る可能性があります。
法律上、住民票の有効期限は明確に定められていませんが、登記の現場では、発行日から3か月以内のものを提出するのが望ましいとされています。また、住民票は本籍や続柄などの記載がない「抄本」で問題ありません。記載された情報が登記事項証明書や他の添付書類と一致しているかをしっかりと確認しましょう。
所有権移転登記にかかる費用と計算方法
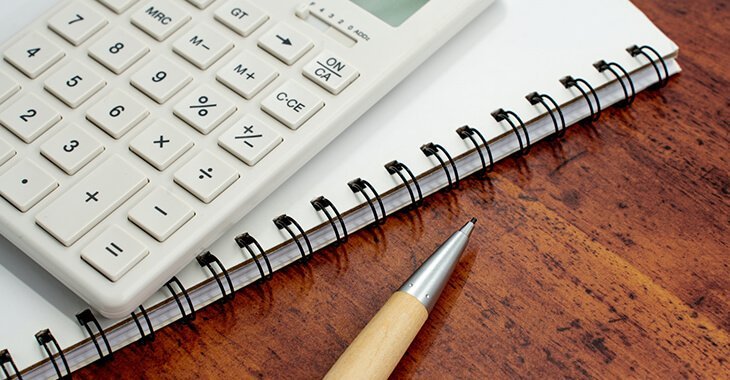
所有権移転登記に必要な費用には、主に3つの項目があります。それは「登録免許税」「必要書類の取得費用」、そして司法書士に依頼する場合の「報酬」です。
ここでは、これらの費用と計算方法について解説します。
登録免許税(不動産価格に応じた税金)
所有権移転登記で最も大きな負担となるのが「登録免許税」です。これは不動産の固定資産評価額に一定の税率をかけて算出されます。
- 売買・贈与:2%(※2025年時点で土地売買は1.5%の軽減税率適用あり)
- 相続:0.4%
たとえば、評価額が3,000万円の不動産を売買で取得した場合、軽減税率1.5%を適用すると約45万円の税金になります。相続であれば、税率0.4%で約12万円です。
取得方法によって税率に大きな差があるため、登記費用の見積もりでは特に注意が必要です。
必要書類の取得費用(証明書類の発行手数料)
登記には複数の証明書類が必要となり、それぞれに発行手数料がかかります。
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 印鑑証明書
- 住民票 など
これらは1通数百円で取得できますが、物件数や提出先が多いと、全体で数千円〜数万円程度になることもあります。
司法書士報酬(手続き代行の費用)
所有権移転登記を司法書士に依頼する場合、報酬として5〜10万円程度が相場です。物件の種類や件数、地域、登記の複雑さに応じて費用は増減します。
自分で手続きすれば司法書士報酬はかかりませんが、書類の準備・記入・提出といった作業に時間がかかるため、平日に動けるかどうかも検討材料になります。
相続で不動産を売却する場合の税金については「相続した不動産の売却にかかる税金は?控除や特例を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
所有権移転登記に関するよくある質問

所有権移転登記は一見すると複雑に思えるかもしれませんが、手続きの流れや必要な書類、費用の目安を知っておくことでスムーズに対応できます。
ここでは、登記に関して特によく寄せられる質問を取り上げ、それぞれ解説します。
所有権移転登記の費用は誰が負担する?
所有権移転登記にかかる費用は、基本的に不動産を取得する側(買主や相続人、贈与を受ける人)が負担するのが一般的です。ただし、契約内容によっては例外もあります。
たとえば、不動産の売買契約に「登記費用は売主が負担する」といった特約を盛り込めば、売主側が費用を負担するケースも可能です。離婚による財産分与の場合も、法律上のルールはなく、どちらが費用を出すかは当事者同士の協議によって決まります。
所有権移転登記に期限はありますか?
不動産を売買や贈与で取得した場合、登記申請の法的な期限はありません。ただし、登記を放置すると、二重譲渡や第三者による抵当権設定といったトラブルの原因になり得ます。名義が変わった際は、できるだけ早めに登記を行うことが望ましいでしょう。
一方、相続による登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。
また、離婚による財産分与には2年間の請求期限がありますが、これは分与そのものに関する期限であり、登記の期限ではありません。いずれの場合も、早めの登記申請が安心につながります。
所有権移転登記を司法書士に依頼できますか?
はい、所有権移転登記は司法書士に依頼することができます。手続きが複雑だったり、平日に時間が取りづらい場合は、依頼を検討するのも有効です。
司法書士に依頼すれば、書類の準備や記入、法務局への提出、補正対応まで任せられるため、手間や時間を大きく削減できます。
また、司法書士によって料金やサービス内容に差があるため、複数の事務所に相談して比較するのもおすすめです。自分に合った専門家を選ぶことで、より安心して登記を進められるでしょう。
トラブルを防ぐために、登記手続きを忘れずに
所有権移転登記は、不動産の名義を正しく変更し、権利を守るために欠かせない手続きです。売買や贈与、離婚による財産分与、相続など、所有者が変わる場面では、登記を通じて公的にその事実を証明することが大切です。
手続きを適切に行わないと、思わぬトラブルや権利関係の混乱を招く恐れがあります。大切な不動産を安心して引き継ぐためにも、本コラムを参考に自分のケースに合った対応を心がけましょう。