不動産を持っている人や、これから売買や相続の手続きをする人にとって、「権利証(登記済証)」はとても大切な書類です。不動産の所有者であることを証明するもので、売却や贈与などの場面で必要になることがあります。しかし、現在ではこの「登記済権利証」は発行されておらず、代わりに「登記識別情報」という新しい仕組みに変わっています。そのため、過去に登記済権利証を受け取った人と、最近登記をした人では、不動産の取引方法が違うことに注意が必要です。この記事では、登記済権利証の役割や特徴をわかりやすく解説し、登記識別情報との違いや、紛失したときの対応方法についても説明します。不動産の取引や管理を安心して行うために、ぜひ最後まで読んでみてください。
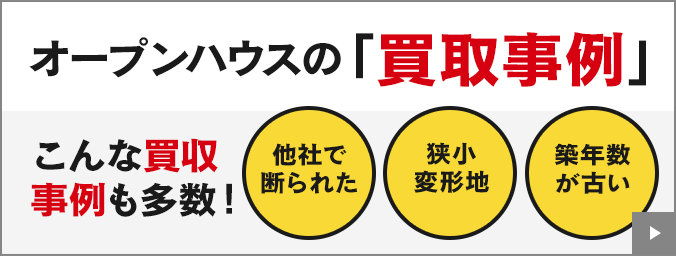
権利証(登記済証)とは?【見本あり】
登記済権利証(以下、権利証)は、不動産の所有権を証明する書類です。法務局で登記の手続きが完了したときに発行され、不動産を売却したり、贈与したりするときに必要になります。
前述している通り、2005年の不動産登記法の改正以降、権利証の発行は廃止され、その代わりに「登記識別情報」という書面が発行されるようになりました。これは、従来の権利証と同じく所有者であることを証明する役割を持ちます。登記識別情報については、このあと詳しく説明します。
移転登記の内容については「所有権移転登記とは?意味・費用・手続きの流れをわかりやすく解説!」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
権利証の基本的な役割
不動産を売るときには、買主に所有権を移転するための登記が必要になります。その際、登記済権利証を提出することで、売主が本当にその不動産の所有者であることを証明できます。もし権利証を紛失してしまうと、本人確認の手続きが複雑になり、スムーズに登記ができなくなることがあります。
また、不動産を担保にしてお金を借りる場合にも、権利証が求められることがあります。住宅ローンを組む際や、金融機関から融資を受けるときに、抵当権を設定する手続きで必要になることがあるため、大切に保管しておくことが重要です。
抵当権の内容については「抵当権とは?初心者向けにわかりやすく解説!手続き・メリット・デメリットまで」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
権利証が必要になる主なケース
- 不動産を売却するとき
- 不動産を家族や親族へ贈与するとき
- 住宅ローンを組むとき(抵当権を設定する場合)
- 不動産を信託するとき
なお、相続の場合は権利証がなくても登記手続きができることが多いですが、スムーズに進めるためには持っていたほうが安心です。
家の相続については「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
権利証の特徴
権利証には、いくつかの特徴があります。形式や記載内容、取り扱いについて理解しておきましょう。
まず権利証は発行された時期や登記の種類によって形式が変わります。例えば、昭和や平成の初めごろに発行されたものは冊子のような形になっていることが多く、平成の中頃からはA4サイズの登記申請書のコピーに「登記済」と押印されたものが主流になりました。
権利証には以下のような情報が記載されています。
| 不動産の所在地や地番 | 登記された土地や建物の情報 |
| 所有者の名前 | 登記名義人 |
| 登記の種類 | 所有権移転、抵当権設定など |
| 法務局の受付印 | 登記済の証明印 |
また、権利証は紛失してしまっても再発行することができません。もしなくしてしまった場合は不動産を売却するときなどに手続きが複雑になり、余分な時間や費用がかかる場合があります。
権利証は再発行ができないですが、不動産の所有権を証明する大事な書類なので、慎重に取り扱いましょう。
登記識別情報とは?その役割と仕組みを解説
登記識別情報とは?
登記識別情報とは、不動産の所有権を証明するための番号が記載された書類のことです。前述している通り、それまでの登記済権利証(権利証)に代わるものとして2005年(平成17年)の不動産登記法改正によって導入されました。
この登記識別情報は権利証に代わり、不動産の所有権を移転する際に必要になります。売却や贈与などで登記をする際に、この情報を法務局へ提出することで、所有者本人であることを証明できます。
登記識別情報には以下のような特徴があります。
- 固有の12桁の英数字が記載されている
- 「登記識別情報通知」として、紙の書類で交付される
- 開封しないと番号が見えないように、目隠しシールがついている
従来の権利証と違い、登記識別情報には所有者の名前や不動産の情報は記載されていません。あくまで「この番号を持っている人が正当な所有者である」と証明するためのものです。
「権利証」と「登記識別情報」は何が違う?知っておきたいポイント
登記済権利証と登記識別情報は、どちらも不動産の所有者を証明する役割がありますが、仕組みが異なります。以下の表で主な違いを整理しました。
| 項目 | 登記済権利証(権利証) | 登記識別情報 |
| 導入時期 | 2005年以前 | 2005年以降 |
| 形式 | 紙の書類(登記申請書の写し) | 12桁の英数字が記載された紙 |
| 再発行 | できない | できない |
| 所有者の情報 | 記載されている | 記載されていない |
| 悪用リスク | 書類が盗まれると不正登記のリスクがある | 漏洩すると第三者が悪用できる可能性がある |
登記済権利証は、所有者の情報が明記されているため、もし紛失しても「本人の実印や印鑑証明と照合することで、ある程度の本人確認が可能」でした。しかし、書類が盗まれてしまうと、所有者や不動産の情報が漏れてしまうリスクがありました。
一方、登記識別情報は固有の番号しか記載がないため、所有者の氏名や不動産情報がばれてしまう心配はありません。しかし番号自体が知られてしまうと不正登記のリスクがあるため慎重に管理する必要があります。
登記識別情報を受け取ったら、目隠しシールを張ったまま大切に保存するようにしましょう。
登記済権利証はなぜ廃止されたのか?
登記済権利証が廃止された理由はいくつかありますが、主な目的は不動産登記手続きの効率化とセキュリティ強化です。
平成17年の不動産登記法改正では、インターネットを利用したオンライン申請が可能になりました。これに伴い新しい仕組みとして登記識別情報が導入されました。
今までの登記済権利証は紙の書類だったため、オンライン申請には対応できていませんでした。しかし、登記識別情報は番号を入力するだけで本人確認ができるため、電子申請がスムーズに行えるようになりました。
また登記識別情報は、所有者の情報が書かれていないため、番号だけでは完全な本人確認ができません。登記手続きをする際には、司法書士の本人確認や印鑑証明書の提出が求められるため、セキュリティが強化されました。
登記識別情報に関するよくあるトラブルと対処法
登記識別情報は、不動産の所有権を証明する大切な情報です。しかし、「受け取っていない」「開封してしまった」「紛失してしまった」「漏えいしてしまった」といったトラブルが発生することがあります。
これらのトラブルが起きると、不動産の売却や相続の手続きがスムーズに進まなくなる可能性があります。ここでは、よくある問題とその対処法について詳しく説明します。
登記識別情報通知をもらってない!【どこで取得したらいい?】
登記の手続きが完了すると、法務局から「登記識別情報通知」が交付されます。しかし、「通知が届いていない」「受け取った覚えがない」といったケースが時々あります。
その場合に考えられる原因はいくつかあります。
- 法務局からの受け取り方法
- 郵送の場合のトラブル
- 申請時の記載ミス
まず受け取り方法についてですが、登記識別情報通知は基本的に法務局の窓口で登記申請者に直接渡されます。もし申請を司法書士や代理人が申請している場合は、代理人が受け取っている可能性もあります。
申請時に郵送での受け取りを希望している場合は、郵便局から簡易書留にて郵送されてきます。もし受取人が不在だった場合、郵便局に一定期間保管されてから返送されることがあります。
もし申請時に住所や受取人の情報を間違ってしまっていた場合、通知が届かない場合もあります。
登記識別情報通知が手元にない場合は、焦らずに順番に確認していきましょう。申請を代理した場合は、依頼をした代理人や司法書士へ連絡して確認しましょう。
代理人に確認してもなかったり、自分で申請をしている場合には法務局に問い合わせをしましょう。申請した法務局へ連絡し「登記識別情報通知を受け取っていない」と伝えます。もし返送されていた場合などは法務局で受け取れる可能性があります。
どうしても登記識別情報が受け取れなかった場合でも、代替え手続きをすることで登記手続きは可能です。
登記識別情報通知の目隠しを開封してしまった!【効力を失う?】
登記識別情報通知には、12桁の英数字が記載されており、目隠しシールで覆われています。このシール開封すると「開けちゃいけなかった?」と不安になるかもしれません。
結論から言うと、登記識別情報は開封しても問題ありません。開封しただけで無効になったりするものではなく、その番号を誰かに知られないことが大事です。実際に手続きするまで開封しないのが一番ですが、もし開封してしまったら金庫など誰かに見られない場所に隠すようにしましょう。
誰かに見られてしまった可能性がある場合は「登記識別情報の失効手続き」を検討しましょう。失効手続きした場合、登記識別情報は無効となり、代わりに事前通知制度を利用して登記手続きができるようになります。
また「開封してしまって心配」という人は司法書士や法務局に相談すると、適切な対応を教えてもらえます。
登記識別情報通知を紛失した!【再発行できる?】
ここまでで何度か解説していますが、登記識別情報通知は再発行ができません。もし紛失してしまっていて、登記識別情報通知を利用したい場合は代替え手続きをする必要があります。
代替え手続きには大きく分けて2通り方法があります。
まずは「事前通知制度」を利用する方法です。事前通知制度を利用すると法務局から所有者あてに書面が送られてきて、適切に対応することによって手続きを進めることができます。
もう一つの方法が「本人確認情報」を提供する方法です。司法書士などの専門家に依頼して、所有者が本人であることを証明する本人確認情報を提出することで手続きができます。ただし、この方法では費用がかかるため、利用する際は慎重に検討するようにしましょう。
権利証(登記済証)、登記識別情報に関するよくある質問
登記済権利証や登記識別情報について、よくある疑問をまとめました。不動産の売買や相続、贈与などの場面でどのように取り扱えばよいのか、事前にしっかりと理解しておきましょう。
家や土地の権利書がないとどうなる?
ここまでも解説してきましたが、不動産の権利証(登記済権利証)や登記識別情報は、所有者であることを証明するための重要な書類です。これがないと、売却や贈与の際に本人確認が難しくなり、手続きが複雑になります。
権利証や登記識別情報がない場合は以下のような影響がでます。
- 売却や贈与がスムーズにできない
- 本人確認のために追加の手続きが必要になる
- 不正登記を防ぐための審査が厳しくなる
もし権利証や登記識別情報を紛失した場合でも「事前通知制度」や「本人確認情報の提供」といった方法で登記手続きを進めることは可能です。ただし、通常より時間や費用がかかるため、できるだけ紛失しないように保管しておきましょう。
登記識別情報って司法書士へ預けて大丈夫?
登記識別情報は、所有者の本人確認に使われる重要な情報です。そのため、基本的には自分で厳重に管理することが望ましいですが、不動産取引をスムーズに進めるために、司法書士に預けることもあります。
司法所へ預けるメリットとしては
- 不動産売買や相続の登記手続きをスムーズに進められる
- 誤って紛失するリスクを減らせる
- 手続きを専門家に任せられるため安心できる
ただし悪用される可能性もあるため、どうしてもでない限り預けるのはおすすめしません。
預ける際の注意点としては
- 信頼できる司法書士かどうか確認する
- 登記が完了したら必ず返却してもらう
- コピーを取るなど、紛失時に備えておく
信頼できる司法書士に依頼すれば問題はありませんが、不安がある場合は事前にどのように保管・管理されるのかを確認しておくと安心です。
登記識別情報があれば、権利証は不要?
登記識別情報と登記済権利証は、どちらも不動産の所有者を証明する役割を持ちますが、現在は登記済権利証の発行が廃止されているため、登記識別情報があれば権利証は必要ありません。
ただし、古い不動産で登記済権利証を持っている場合は、大切に保管しておくことをおすすめします。登記識別情報を紛失してしまった際に、本人確認の手続きをスムーズに進めるための証拠として役立つことがあるためです。
相続や贈与の際、登記識別情報はどうすればいい?
不動産を相続や贈与する際、登記識別情報はどのように扱えばよいのか悩む人も多いです。基本的には、新しい所有者に引き継ぐ必要がありますが、手続きの流れをしっかり理解しておくことが大切です。
相続の場合は以下のような流れで手続きが進みます。
- 被相続人(亡くなった人)の登記識別情報を確認する
- 遺産分割協議が必要な場合は、すべての相続人と話し合う
- 相続登記の際に、新しい名義人(相続人)の名前に変更する
- 登記完了後、新しい所有者のもとに登記識別情報が発行される
原則として相続手続き自体には登記識別情報は必要ありません。ただし被相続人が住所変更をしていなかった場合など、例外的に提出を求められることもあるため適切に保管しておきましょう。
家の相続手続きの内容については「相続した不動産の売却にかかる税金は?控除や特例を解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
贈与の場合では以下の流れになります。
- 贈与契約を締結
- 贈与を受ける人が、新しい所有者として登記手続きを行う
- 登記完了後、新しい所有者のもとに登記識別情報が発行される
2番の登記手続きをする際に、登記識別情報が必要になります。最終的には新しい登記識別情報が発行されるので、そのあとは不要になりますが、手続きが完了するまではしっかりと保管しておきましょう。
登記済権利証と登記識別情報の違いを理解し、適切に管理しよう
登記済権利証と登記識別情報は、不動産の所有権を証明する重要な書類です。平成17年の法改正により、従来の登記済権利証は廃止され、登記識別情報が発行されるようになりました。
どちらも再発行ができず、紛失すると登記手続きが複雑になるため、厳重に保管することが大切です。また、登記識別情報は12桁の番号が記載されているだけなので、第三者に知られないよう慎重に取り扱う必要があります。
不動産の売買や相続、贈与などの際にスムーズに手続きを進めるためにも、それぞれの違いを理解し、適切に管理しましょう。もし紛失やトラブルが発生した場合は、早めに司法書士や法務局に相談することをおすすめします。






