相続した家を売るには、名義変更や遺産分割協議、税金の申告など、複雑な手続きが必要になります。「どんな流れで売れるのか」「どれくらい税金がかかるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、相続不動産を売る際の流れ・税金・注意点を、初めての方でも理解できるように整理して解説します。
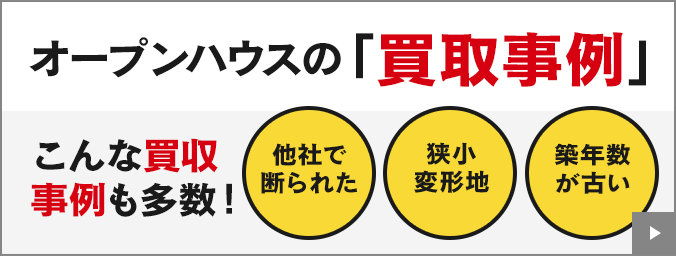
相続した家は売れる?まず知っておくべき基礎知識
相続した家は売却可能ですが、スムーズに進めるには知っておきたい前提があります。
ここでは、売却前に押さえておくべき基本的な3つのポイントを紹介します。
相続登記しないと家は売れない
相続した家を売るには、まず相続登記(名義変更)を完了させておくことが前提です。登記名義が亡くなった親のままでは、法的に売却することができません。相続人のうち誰が家を引き継ぐのかを遺産分割で決めたうえで、自分名義に変更する必要があります。
2024年4月からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく放置すると過料(罰金)の対象になる可能性もあります。売却を考える段階で、名義の確認を忘れずに行っておきましょう。
相続登記の義務化については「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
売る前に遺言書と相続人の確認が必要
家を売る前には、「誰が相続人か」と「遺言書の有無」を確認することが欠かせません。遺言書がある場合は、内容に従って所有者が決まり、相続人全員の合意なしに売却を進めることはできません。
遺言書がないときは、法定相続人による遺産分割協議が必要です。相続人を把握するには、戸籍謄本などの資料を取り寄せて調査します。
兄弟姉妹や認知された子どもなど、予想外の相続人がいることもあるため、できるだけ早い段階で確認しておきましょう。
家を売るには相続人全員の合意が必要
遺言書がない場合、相続人全員の合意がなければ家を売却することはできません。一部が売却に同意していても、誰か一人でも反対すれば手続きは進まないため、協議による合意形成が欠かせません。
売却を急ぐと意見が食い違い、関係悪化につながる恐れもあります。誰が相続するか、売却益をどう分けるかを事前に整理し、遺産分割協議書として書面に残しておくとスムーズに進めやすくなります。
相続した家を売る2つの手段
相続した家の売却には、「仲介」と「買取」という2つの方法があります。どちらを選ぶかで売却価格や完了までのスピードが大きく変わるため、各手法の特徴を理解したうえで、自分たちの状況に合う選択をすることが大切です。
① 仲介業者を通じて相続した家を売る
仲介とは、不動産会社に依頼して買主を探してもらう方法です。物件をインターネットなどに掲載し、内覧や価格交渉を経て契約に至ります。
相場に近い価格で売却できる可能性があるため、「できるだけ高く売りたい」と考える方に向いています。ただし、買主が見つかるまでに時間がかかることもあり、売却まで数ヶ月を要するケースも珍しくありません。
また、内覧対応や契約手続きなどにある程度の手間がかかる点も理解しておきましょう。時間に余裕があり、価格を重視する場合は仲介を検討する価値があります。
② 買取業者を通じて相続した家を売る
買取とは、不動産会社が家を直接買い取ってくれる方法です。買主を探す必要がなく、売却までの期間が短いため、スピードを重視したい場合に向いています。
相続税の納付期限が迫っている、家の管理が難しいといった事情がある場合には、有力な選択肢となるでしょう。また、内覧対応や修繕の手間が不要なケースも多く、手続きも比較的シンプルです。
ただし、仲介に比べて売却価格が下がる傾向があるため、「価格よりも早さ・確実性を優先したいか」が判断のポイントとなります。
「仲介業者」と「買取業者」の違いとは?
仲介と買取の最大の違いは、「誰が買主になるか」です。
仲介では不動産会社が第三者の買主を探しますが、買取は不動産会社自身が買主となるため、契約までが比較的早く進みます。仲介は時間がかかるぶん高値で売れる可能性がある一方、内覧や交渉などの手間が発生します。
対して買取は手間が少なくスピーディーですが、売却価格は低くなりやすい点がデメリットです。「価格を重視するか」「早く確実に売りたいか」といった状況に応じて選ぶのが基本です。
迷ったときは、両方に査定を依頼して比較検討するのもおすすめです。
親の死後、家が売れないときについては「親の死後、相続した家が売れない原因とは?対策や放置するリスクも解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
相続した家を売るまでの手続きの流れ
相続した家を売却するには、相続人の確認や名義変更から、不動産会社との契約、売却活動、税金の申告まで、いくつもの手続きを順を追って進める必要があります。
買取業者と仲介業者によって手続きが異なり、不動産の売却を買取業者に依頼している場合は⑤と⑥の手続きは不要になります。
ここでは、売却までの流れをステップごとに整理し、押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
家を相続する流れについては「家を相続する方へ-不動産を相続する際の必要手続きや書類・方法・費用を徹底解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
①遺言書の有無を確認する
最初に確認すべきは、遺言書の有無です。遺言書が見つかった場合は、内容に従って相続人が決まるため、処分せずに慎重に扱うことが大切です。
一方、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、家の取り扱いについて話し合う必要があります。
② 相続人が自分だけかを調査する
他にも相続人がいる可能性があるため、戸籍をたどって法定相続人を正確に把握することが大切です。配偶者や兄弟姉妹、認知された子などが含まれる場合もあり、思い込みによる判断はトラブルのもとになります。
登記や協議に進む前に、相続関係をしっかり確認しておきましょう。
③ 遺産分割協議で家の扱いを決める
相続人が複数いる場合は、家を誰が相続するかを「遺産分割協議」で決め、全員の合意が必要です。協議の内容は協議書としてまとめ、相続人全員が署名・押印します。
合意が得られなければ名義変更も売却もできないため、早い段階で協議を進めておくことが重要です。
④ 相続登記で家の名義を変更する
遺産分割協議がまとまったら、法務局で相続登記を行い、不動産の名義を相続人に変更します。登記が完了していない状態では、家を売却することはできません。
2024年からは相続登記が義務化されており、放置していると過料(罰金)の対象となる可能性があるため注意が必要です。
⑤ 不動産会社に相談し、家の査定・媒介契約を行う ※買取業者の場合は不要
相続登記が済んだら、不動産会社に査定を依頼し、価格や対応を比較したうえで媒介契約を結びます。
契約後に売却活動が始まりますが、媒介契約にはいくつかの種類があるため、内容や条件はあらかじめ把握しておくことが大切です。
⑥ 家の売却活動(内覧・価格交渉)を行う ※買取業者の場合は不要
媒介契約を結ぶと、不動産会社を通じて内覧や価格交渉を含む売却活動が始まります。
内覧前には簡単な掃除や片付けをして、第一印象をよくしておくのが効果的です。
価格や条件の交渉は無理をせず、不動産会社と相談しながら進めると安心です。
⑦ 売買契約を結び、家を引き渡す
買主との条件がまとまったら、売買契約を締結します。
契約後は引き渡しに向けて、必要書類の準備やローン審査などが進められ、当日は残金の受け取りと所有権の移転、鍵の引き渡しを行って完了となります。
各手続きは不動産会社や司法書士と連携しながら進めると安心です。
⑧ 税務署に申告して税金を納める(確定申告)
売却によって譲渡所得が発生した場合は、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。
また、利益が出なかった場合でも、各種控除や特例を利用するには申告手続きが求められるため、早めの準備が重要です。
不明点があれば、税理士など専門家への相談も検討してみましょう。
相続した家を売るときにかかる主な税金とは?
相続した家を売却すると、状況に応じてさまざまな税金が発生します。
「相続時」と「売却時」では課税のタイミングや内容が異なり、それぞれで申告や納税が必要になる場合もあります。
ここでは、相続と売却に関連する主な税金について、事前に把握しておきたいポイントを整理します。
相続税
相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続した際に発生する税金です。
不動産の評価額や預貯金など、すべての相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると課税対象になります。売却とは直接関係しませんが、相続税の納税資金を用意するために不動産を売却するケースもあります。
申告と納税は「相続の開始を知った日から10か月以内」と期限が決まっているため、相続発生後のスケジュールを意識して進めましょう。
譲渡所得税および住民税
相続した家を売って利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税と住民税がかかります。所有期間によって税率が異なり、相続では被相続人が取得した日を引き継ぎます。
- 所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は約20%です。
- 所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は約39%です。
特例や控除を使えば税額を抑えられることもあるため、事前に条件を確認しておきましょう。
印紙税
不動産売買契約書には印紙税がかかり、契約金額に応じた収入印紙を貼って消印する必要があります。
税額は取引額によって異なり、誰が印紙税を負担するかは契約時に取り決めておくと安心です。
復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源として導入された税金で、所得税額に2.1%を上乗せして課税されます。
2037年まで適用され、確定申告時に自動的に計算・加算されるため、特別な手続きは必要ありません。しくみだけは事前に把握しておきましょう。
登録免許税
登録免許税は、相続登記を行う際にかかる税金で、不動産の固定資産評価額の0.4%が基本となります。
相続登記を放置すると過料の対象になるため、名義変更とあわせて税額の目安も早めに確認しておくと安心です。
家や土地を相続したときに活用できる特例・控除
相続した家や土地を売却する際、条件を満たせば税金を抑えられる特例や控除が適用されることがあります。譲渡所得税や相続税の負担を軽くできる可能性があるため、あらかじめ制度の内容を把握しておくことが大切です。
ここでは、特に活用される代表的な3つの制度を紹介します。
相続税の取得費加算の特例
相続税の取得費加算の特例は、相続した不動産を売却する際に、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。譲渡所得の計算上、利益を抑える効果があるため、適用できれば税額を軽減できる可能性があります。
取得費加算の特例は、相続開始から3年10か月以内に売却した場合に限られ、加算できる相続税額は不動産に対応する部分のみです。
適用には確定申告が必要で、書類の準備や計算が複雑になりがちなので、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
空き家の3,000万円特別控除
被相続人が一人暮らしをしていた家を相続し、その家を売却した場合、一定の条件を満たせば「空き家の3,000万円特別控除」が適用されます。制度を利用すると、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができ、譲渡所得税や住民税の負担を大幅に軽減できます。
適用には、「昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること」「売却時に耐震リフォームを行うか更地にしていること」「相続人がその家に住んでいないこと」など、いくつかの要件があります。
確定申告が必要で、要件の確認や書類の準備も複雑になりやすいため、事前に専門家に相談しておくと安心です。
居住用財産の3,000万円控除
相続した家に一定期間住んだあとで売却する場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用されることがあります。これは、自宅を売却した際に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度で、空き家控除とは別の仕組みです。
相続してすぐに売却する場合は対象外ですが、相続した家に住み替えて一定期間居住したのちに売却するケースでは、活用できる可能性があります。他の控除制度との併用ができないこともあるため、売却前に制度の条件や適用可否を慎重に確認しておきましょう。
売却のタイミングや利用条件によって税額が大きく変わることもあるため、制度の内容をよく理解しておきましょう。
相続した家の売却に関するよくある質問
相続した土地や建物の売却では、税金や手続きの時期について悩む人も少なくありません。
ここでは、特によくある3つの疑問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
① 相続した家をいつ売ればよいですか?
相続した家を売るタイミングに明確な決まりはありませんが、税金や手続きの観点から注意すべき点があります。たとえば、「相続税の取得費加算の特例」は相続開始から3年10か月以内の売却が条件であり、「空き家の3,000万円特別控除」なども適用時期に制限があります。
一方で、無理に急いで売却すると、相場より安く手放してしまうこともあるため、売却の目的や状況に応じて判断することが大切です。
税制や不動産市場の動向をふまえつつ、専門家と相談しながら適切なタイミングを見極めましょう。
② 相続した家を売ったら税金はいくらかかりますか?
相続した家を売却した場合にかかる税金は、主に「譲渡所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つです。これらは、売却で得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。
譲渡所得は「売却価格 −(取得費+諸経費)」で計算され、所有期間によって税率が変わります。一般的には、所有期間が5年を超えると約20%、5年以下だと約39%の税率がかかります。
「空き家の3,000万円特別控除」や「相続税の取得費加算の特例」を活用すれば、課税額を大きく減らせる場合もあります。
実際の税額は取得費や適用する制度によって大きく変動するため、売却前に一度試算しておくとよいでしょう。
③相続した家を売る場合、確定申告は必要ですか?
はい、相続した家を売って譲渡所得が発生した場合は、原則として確定申告が必要です。譲渡所得は「売却価格 −(取得費+諸経費)」で計算され、利益に対して課税されます。
利益が出ていない場合でも、「3,000万円の特別控除」や「取得費加算の特例」などを利用するには申告が必要です。申告をしないと控除が受けられず、結果的に税額が増えてしまうおそれがあります。
申告の時期は、売却した翌年の2月16日〜3月15日が一般的です。
相続した家を売るために、今からできる準備を始めよう
相続した家を売るには、相続人の確認や名義変更、税金の知識など、注意すべきポイントが数多くあります。また、仲介と買取の違いや、特例・控除の活用次第で、手続きや納税額に大きな差が出ることもあります。
スムーズな売却のためには、できるだけ早く状況を整理し、必要な準備を整えておくことが重要です。不安な点があれば、不動産会社や税理士などの専門家に相談しながら進めることで、トラブルや後悔を避けやすくなります。
この記事を参考に、ご自身の状況に合った方法を見つけ、納得のいく売却を目指してみてください。
相続する前に親の家を売る流れについては「【完全ガイド】親の家を売る方法とは?後悔しないための準備・流れ・税金まで徹底解説」や「認知症の親が所有する不動産を売却する方法とは?手順から注意点まで解説」にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。






